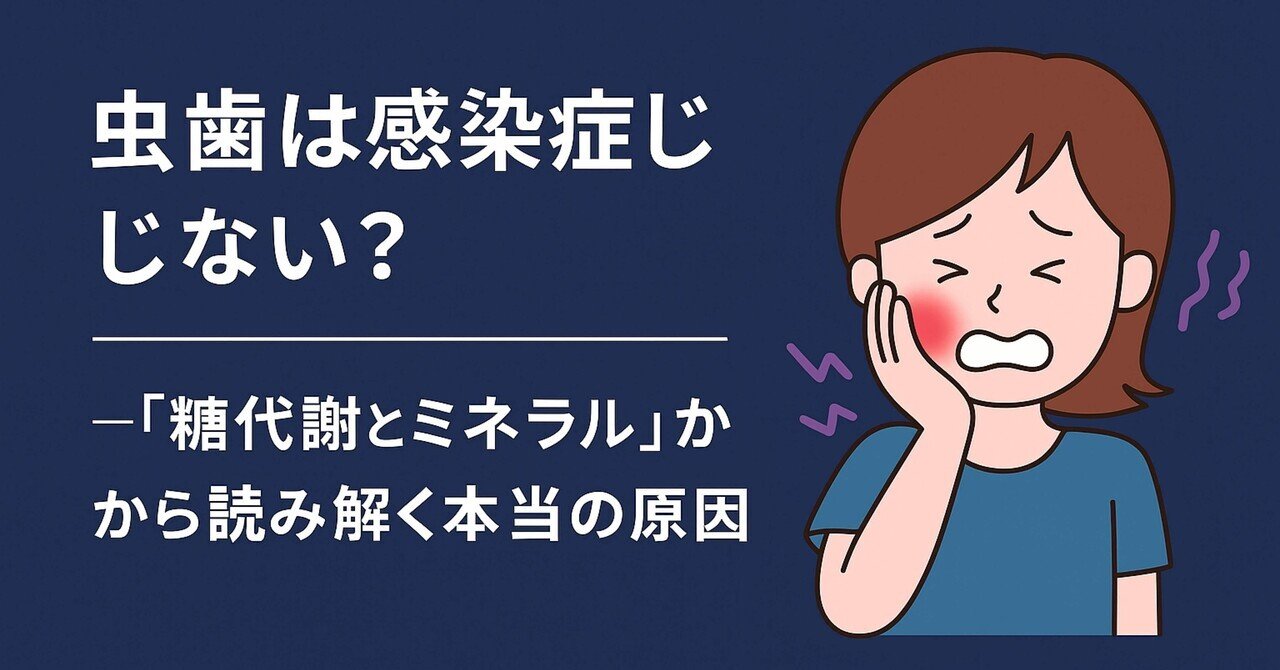「虫歯は感染症です」
「ミュータンス菌が原因です」
「赤ちゃんに“口うつし”はNG」──
そう教わってきた方、多いと思います。
実際、歯科の現場でもこの考えは一般的ですし、
私も歯科衛生士として現場に立つ中で、
ずっとそう信じてきた時期がありました。
でもある時、ふと思ったのです。
⸻
✅同じ菌がいても、虫歯になる人とならない人がいるのはなぜ?
✅きちんと歯を磨いていても、虫歯になる人がいるのはなぜ?
✅甘いものを控えているのに、虫歯が進行する人がいるのはなぜ?
この違いに、“菌”だけで説明できるのでしょうか?
⸻
じつはこの構造、がんやアレルギー、自己免疫疾患とも似ています。
たとえば──
「がんは遺伝子のせい」
「アレルギーは体質だから」
「ウイルスに感染したから病気になった」…
これらはどれも一部は正しいけれど、
それだけでは“結果の説明”にはならないのです。
⸻
菌も、ウイルスも、遺伝子も、
私たちの体に影響を与えることは事実です。
でも──
それらの“スイッチを入れるかどうか”は、自分次第。
同じように、
ミュータンス菌が口の中にあったとしても、
歯が強く、唾液が整い、pHが保たれ、ミネラルが十分なら──
虫歯にはならない人もいるのです。
⸻
最近では、欧米の予防歯科を中心に、
体の代謝・ホルモン・栄養・ミネラルバランスなどから
“虫歯や歯ぐきの異変”を見直すアプローチも増えています。
これは「機能性医学(Functional Medicine)」と呼ばれ、
私たちのような歯科や医療の現場でも、
「症状の奥にある“原因”」にアプローチする新しい流れとして注目されています。
⸻
つまり──
虫歯もまた「結果」ではなく、「サイン」かもしれないのです。
• 精製糖や血糖変動によって、体が酸性に傾いている
• ミネラルの吸収や代謝がうまくいっていない
• 再石灰化が追いつかず、歯が“修復されない状態”になっている
• 自律神経のバランスが崩れ、唾液が出づらくなっている
こうした“体の声”が、
虫歯や歯肉炎として現れている可能性があるとしたら…?
⸻
私たちは、「虫歯を削って詰める」だけではなく
「なぜ、そこに虫歯ができたのか?」を考える必要があります。
• それは、歯の磨き方だけの問題ではなく、
• フッ素を塗れば安心という単純な話でもなく、
• 体の内側にある“再石灰化の力”を支える土壌にまで目を向けること──
それこそが、これからの“本当の予防歯科”につながるのではないかと私は感じています。
⸻
そんな視点から、
「虫歯は感染症じゃない?」という問いをきっかけに、
“糖代謝とミネラルの視点”で深掘りしたnoteを書いてみました🌿
note 👇
従来の歯科的な考え方に、
代謝・栄養・免疫の観点を組み合わせた“ちょっとマニアック”な内容かもしれません。笑
でも、今後の医療や歯科にとって必要な“視点の転換”になると思っています。
⸻
「虫歯ができるのは、菌のせい」
そう思っていた方にこそ、
知ってもらえたらうれしいです。
きっとそこから、歯も体も“変わるきっかけ”が見えてきます。