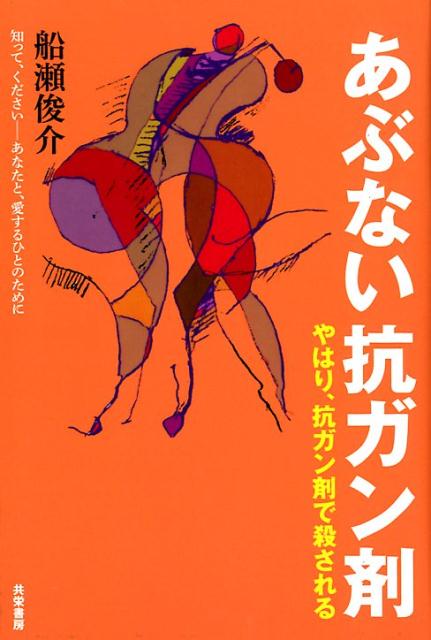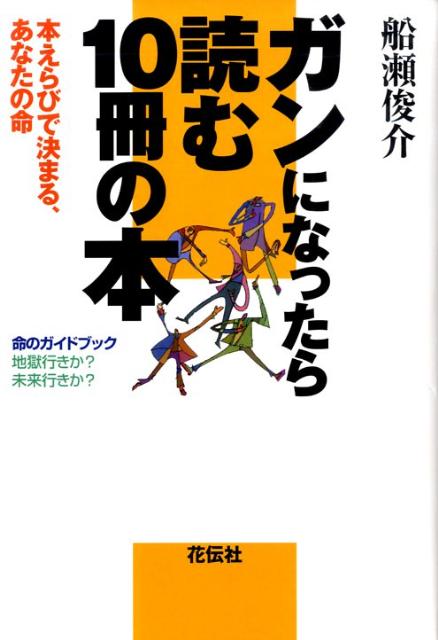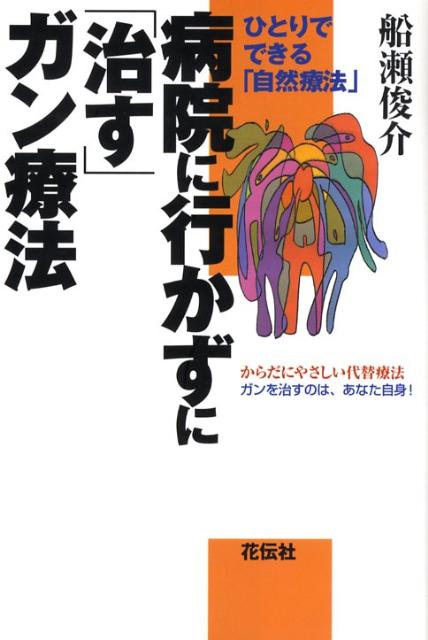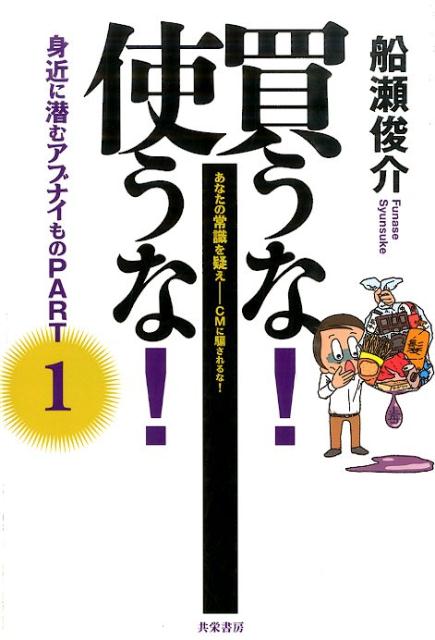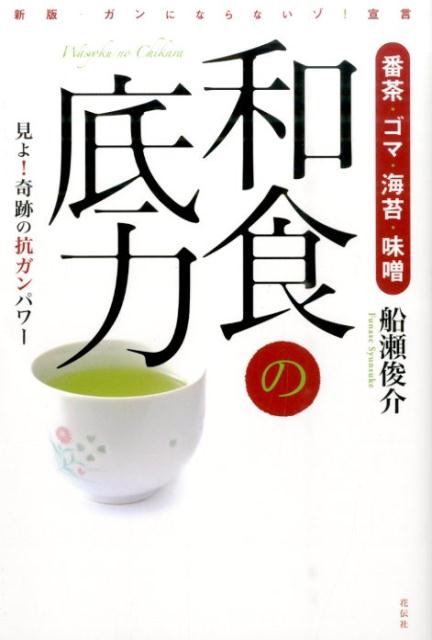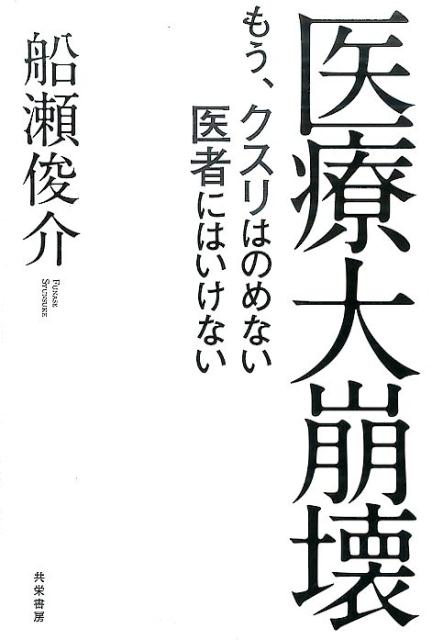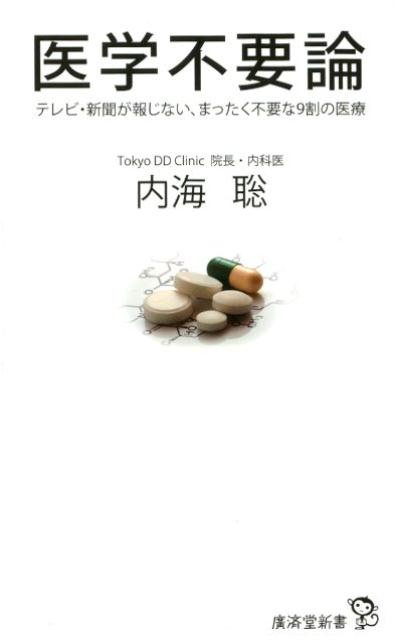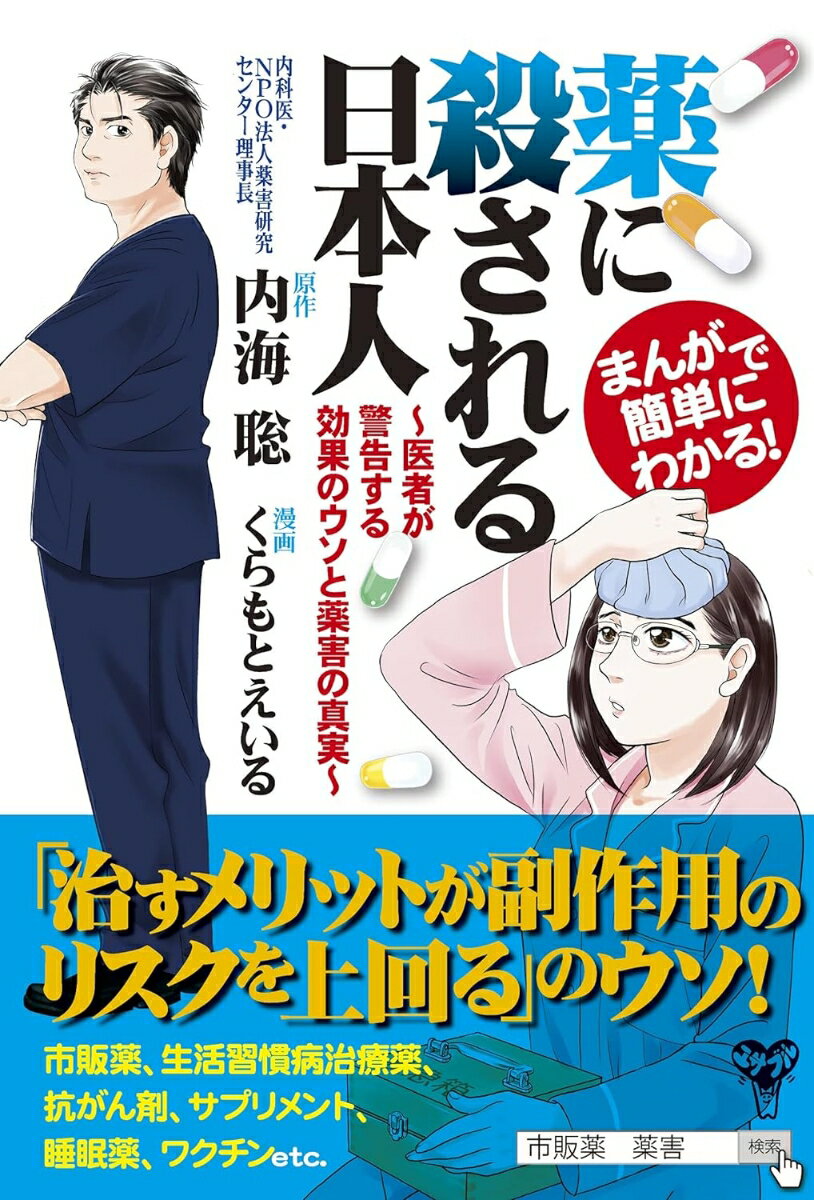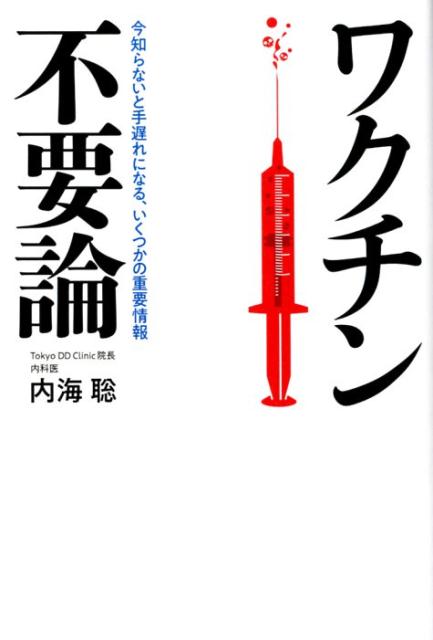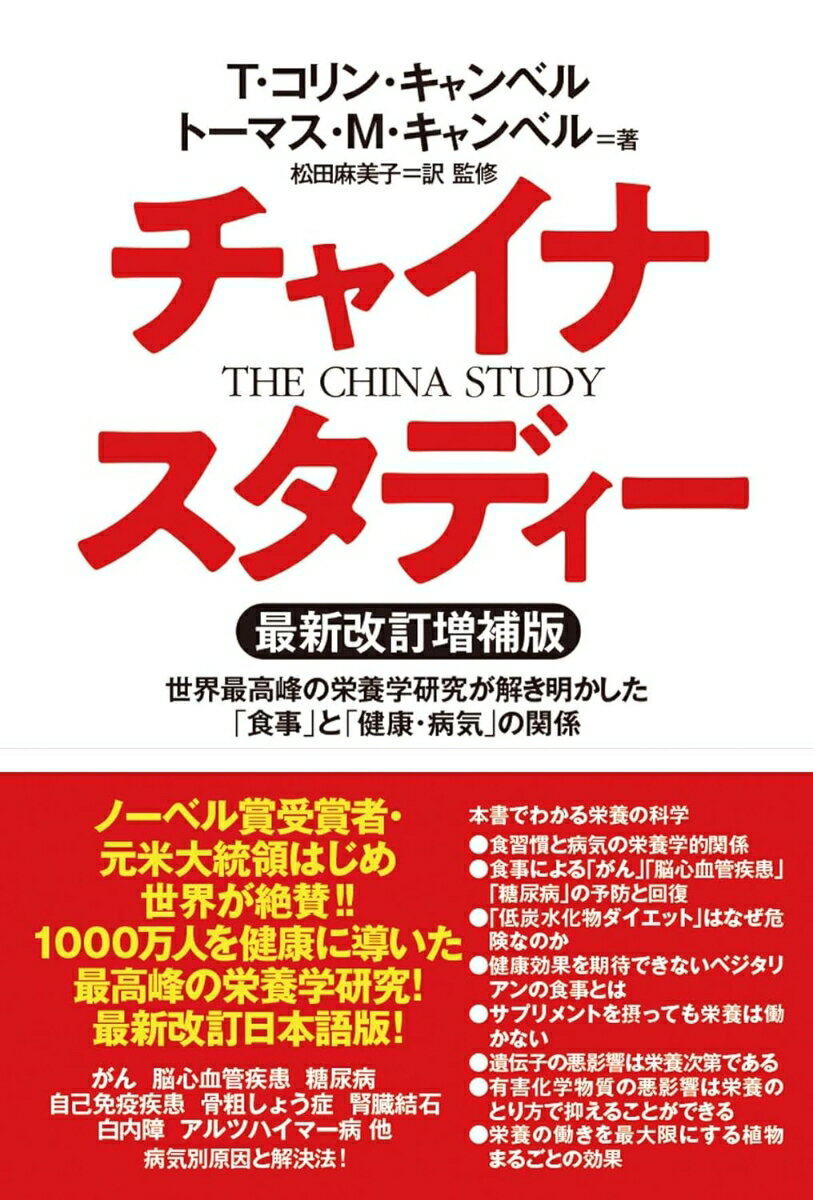── 非浸潤がん(DCISなど)/近藤誠氏の主張と臨床の現場感から考える
🔷 「早く見つけて、早く治す」──
がんに対して、そう思っている方は多いのではないでしょうか。
たしかに一部の進行がんにとって“早期発見・早期治療”は重要です。
しかし今、がん医療の現場では**「見つけたけれど、進行しないがん」**が注目されるようになってきました。
乳がんでよく知られる「DCIS(非浸潤性乳管がん)」や、甲状腺がん、前立腺がんなど──
放置しても命に関わらない“静かながん”が、過剰に治療されているケースがあるのです。
このテーマを語る上で避けて通れないのが、近藤誠医師が提唱した「がんもどき論」。
医療界では賛否が分かれるものの、今の過剰診断・過剰治療の流れを早くから指摘していた人物でもあります。
今回は、“がんもどき”とは何か?本当に治療すべきがんとの違いは?
そして「見つけたから治す」という常識が、逆に命の質を下げてしまうリスクについて考えていきます。
🔹 がんもどきとは何か?──近藤誠氏の主張
「がん」と聞くだけで、ほとんどの人が心を揺さぶられます。
見つけた瞬間から「すぐに切除しなきゃ」「抗がん剤を始めなきゃ」と、考える間もなく治療に突き進むのが現代医療の現場です。
そんな常識に真っ向から異を唱えたのが、医師・近藤誠氏。
彼は、がんには「命を脅かす本物のがん」と、「見つかっても進行せず、死ぬまで問題を起こさない“がんもどき”」の2種類があると主張しました。
たとえば、乳がんの**DCIS(非浸潤性乳管がん)**や、
前立腺がん・甲状腺乳頭がんなどの多くは、一生かけても症状を出さずに終わる可能性が高い。
けれど、がんという名前がついた時点で、どんな性質であろうと“治療の対象”にされてしまう──
それが、現代の「見つけたから治す」という医療構造の落とし穴です。
近藤医師の言葉を借りれば、
「がんもどきは“がん”というラベルを貼られた無害な細胞の集まりにすぎない」
…というもの。
彼の意見には賛否がありますが、彼の発信によって多くの人が「この“がん”は、本当に治療が必要なのか?」と立ち止まるきっかけを得ました。
“がん=全部敵ではない”という視点。
それは、これからの予防医療や、QOL(生活の質)を守る医療に欠かせない大切な問いなのです。
🔹 DCIS・甲状腺・前立腺…“止まっているがん”たち
すべての「がん」が、命を脅かすわけではありません。
医療の現場でも、実際には「進行しない」「転移しない」「発症しない」まま一生を終える“がん細胞”が数多く見つかっています。
代表的なのが、乳がんのDCIS(非浸潤性乳管がん)。
このタイプの乳がんは、がん細胞が乳管の中にとどまり、周囲に浸潤せず転移もしないことが大半です。
けれど名前に“がん”がついてしまうため、告知された瞬間から多くの人が恐怖に駆られ、すぐに手術や放射線、抗がん剤を選んでしまうのです。
ほかにも、前立腺がんや甲状腺乳頭がんなどは、欧米では「がんと共に生きる(Watchful Waiting)」という経過観察の選択肢が当たり前になっています。
たとえ見つかったとしても、進行も転移もせず、むしろ治療の副作用の方が生活の質を損ねるケースが多いためです。
これらは近藤誠氏が唱えた“がんもどき”の代表例とも言えるものであり、船瀬俊介氏も著書で「がんの9割はもどき」と大胆に表現しています。
もちろん“9割”という数字には賛否ありますが、「全てのがんが即・治療の対象ではない」という視点を持つことが命を守る一歩になる──という本質に、異論を唱える人は少なくなってきています。
実際に、アメリカやカナダ、イギリスでは過剰診断・過剰治療を避けるガイドラインが次々と見直され、“命に関わらないがん”は、定期モニタリングの中で慎重に見守る方針が推奨されるようになっています。
だからこそ、私たちに必要なのは「検診を受けるな」という話ではなく──
見つけた“それ”が、どんな性質を持っているのか?
その治療で得られる未来と、失うものは何か?
そんな問いを、自分で立てる“考える力”なのです。
🔹 「見つけたから治す」が生む心身のダメージ
「早期発見・早期治療が命を救う」──
これは一見、疑う余地のない正論のように思えます。
けれど、その“正しさ”が、すべてのケースに当てはまるとは限りません。
たとえば、命に関わらない非浸潤がんや、進行の非常に遅い良性腫瘍であっても、がんと名のつく診断を受けた瞬間から、多くの人は恐怖に包まれます。
この「がん」という言葉の持つ圧倒的なインパクトこそが、心にストレスを与え、免疫力を下げ、本来眠っていた病気の芽を動かしてしまうことすらあるのです。
さらに問題は、「治療の副作用」にもあります。
手術による損傷、放射線による二次がんのリスク、抗がん剤による骨髄・腸管・神経への影響…。
“がんの進行を抑えるため”に行った治療が、日常生活の質(QOL)を著しく下げてしまうことも少なくありません。
そして、医療費・通院・職場や家庭への影響など、社会的ダメージも大きな負担になります。
医学的に「今すぐ治療する必要はない」と言える状態でも、医療制度や医師の立場、保険の仕組みによって「とりあえず切っておこう」「念のため薬を始めよう」と誘導されてしまう現実も存在します。
あなたの身体の“腫瘍”は、本当に「今、叩くべき敵」なのか──
それとも、**共存しながら見守れる“静かな同居人”**なのか──
「見つけたから治す」の前に、一度だけ、立ち止まって考える。
それだけで、守れる未来があるかもしれません。
🔹 内海聡・船瀬俊介氏らの視点──がんとは何か?
がんは“悪い細胞が勝手に暴れ出す病気”だと思われがちです。
けれど、本当にそうでしょうか?
「がんもどき」という概念を提唱した近藤誠氏に続き、医師の内海聡氏やジャーナリストの船瀬俊介氏は、がんそのものの見方を根底から問い直しています。
内海氏は、がんを「体の機能低下や排毒力の限界によって現れる代謝異常の最終形」と捉えています。
つまり、がんは突然生まれるのではなく、**“出せなかったもの”の蓄積と、代謝の狂いの結果として現れる“沈黙のメッセージ”**だというのです。
また、船瀬氏は「がんの9割は“もどき”」とし、そもそも「がんという病気は存在しない。生活と精神の乱れが細胞の異常を育てるだけ」とも表現します。
この言葉には賛否あるかもしれませんが、“細胞を敵視する”視点ではなく、“育ててしまった環境を見直す”という発想には、多くの共感が寄せられています。
たとえば──
子宮筋腫は一般的に良性とされ、悪性化の確率は非常に低いとされています(0.1〜0.5%程度)。
けれどそれでも、“できている”ということ自体が、代謝・ホルモン・血流・解毒力などの不調のサインであることは変わりません。
同じく、前立腺や甲状腺、乳腺のしこりも「悪性ではないから安心」という考え方だけでは不十分です。
腫瘍ができる環境そのもの──それが生活習慣や心の状態と深く関わっている以上、“良性”というラベルに安心してしまい、生活を見直さなければ、将来的に悪性化する可能性もゼロではないのです。
だからこそ、彼らの共通メッセージはこうです:
「がんを治す」のではなく、
「がんを育てない体に戻す」こと。
そのために必要なのは、食や排泄だけではありません。
感情・思考・ストレスへの向き合い方、社会との関係性、体との距離感──
つまり、“生き方そのもの”が問われているのです。
そしてそれは、決して医者任せにできることではありません。
🔹 “選ばない医療”という勇気
診察室で医師に「がんです」と告げられた瞬間、多くの人は自動的に「治療する」という選択をしてしまいます。
それはもう、考える間もないくらい自然な反応です。
でも、がんのすべてが命を奪うものではない──
もしそれが事実だとしたら、「治療を“選ばない”という勇気」もまた、選択肢のひとつとしてあっていいのではないでしょうか。
「なにもしない=放置」ではありません。
「選ばない」というのは、“今の体と丁寧につきあいながら、自分で判断する時間を持つ”という行為です。
実際に、前立腺がんや甲状腺がん、DCISのように、
**経過観察(watchful waiting)**がスタンダードになりつつあるがんも存在します。
海外では「あなたのがんは今すぐ治療が必要とは限らない」と伝えられ、“治さない勇気”が尊重される医療の場も増えてきました。
一方、日本ではどうでしょう。
検診で「がんの疑い」と言われただけで即手術。
本人が悩む余地すらなく、治療がスタートすることも珍しくありません。
不安を煽られ、納得できないまま身体にメスを入れ、その後、「やっぱりあれはやらなくてもよかったのかもしれない」と気づく──そんな声も少なくないのです。
“選ばない”というのは、逃げることではありません。
「自分で決めること」を選ぶ強さであり、
「本当にこの治療が今の自分に必要か?」と問い直す尊厳ある選択です。
医師の説明を受けたあと、こう言ってもいいのです。
「少し時間をください」
「ほかの選択肢も調べてみたいです」
「自分の体の声を、もう一度聞いてみます」
誰もが、命に関わる選択を“委ねる”のではなく、
“共に決める”ための知識と感性を持つ時代に来ています。
「選ばないこと」も、あなたの大切な“選択”なのです。
🔹 “治す”ではなく、“どう生きるか”を取り戻す
がんと告げられることは、たしかに衝撃です。
けれど、それは“命の終わり”を意味するものではありません。
それはむしろ、「このままでいいですか?」という体からの静かな問いかけかもしれません。
今の医療は、“見つけたら治す”が当たり前。
けれど、その一歩手前にある「これは本当に治すべきものなのか?」という視点は、あまり語られることがありません。
がんもどき、非浸潤がん、良性腫瘍──
たとえ「治療対象」として分類されたとしても、それがあなたにとっての最善とは限らないのです。
だからこそ、必要なのは医療情報だけではありません。
**あなたが自分の体と向き合うための“感性”と“選ぶ力”**です。
治療するのか、しないのか。
経過観察なのか、積極的に体質改善に取り組むのか。
いずれにしても、それは「自分で考えて決めた」と思える選択であってほしいのです。
がんの本質は、「どう生きてきたか」の積み重ね。
そしてこれからは、「どう生き直すか」の問いでもあります。
医療に委ねきるのではなく、自分で選ぶこと。
それが、がんと共に生きる時代における、新しい“治療”のかたちなのかもしれません。