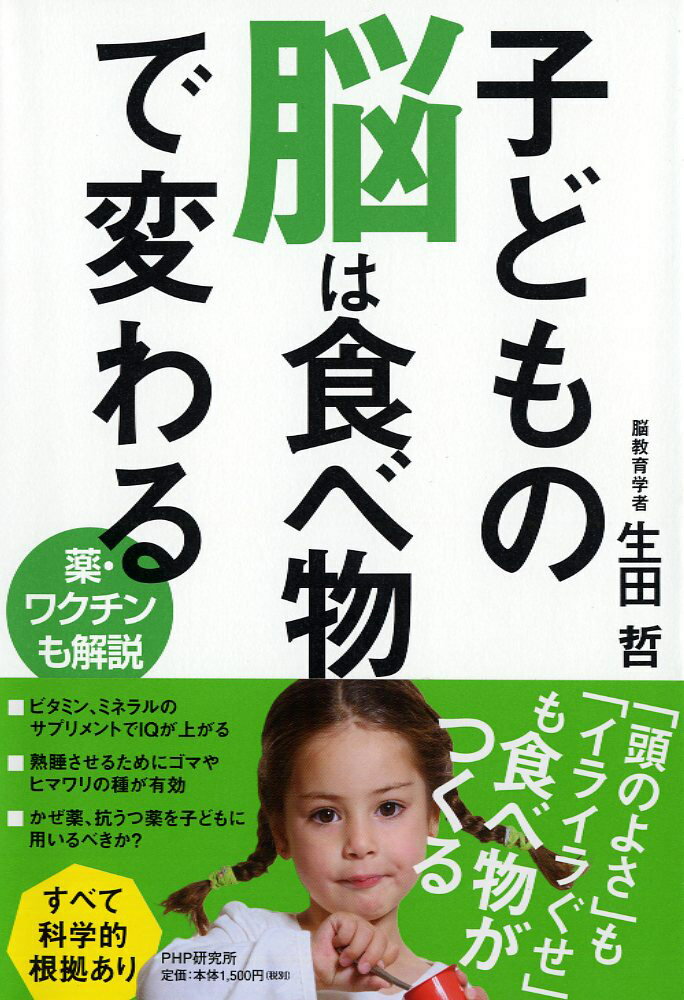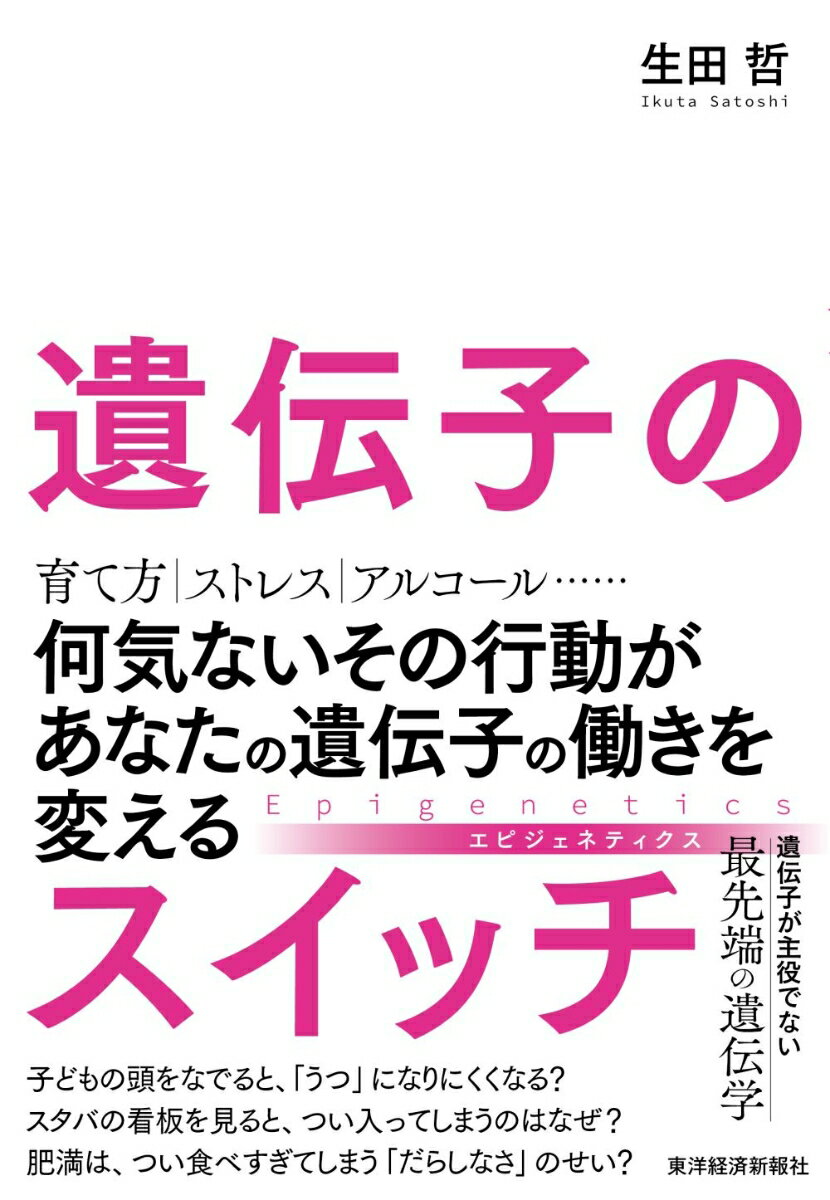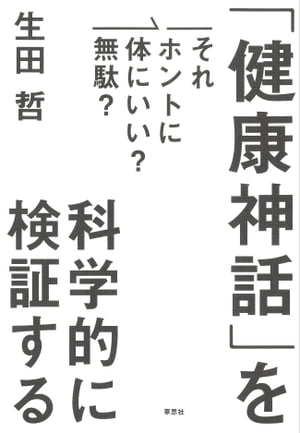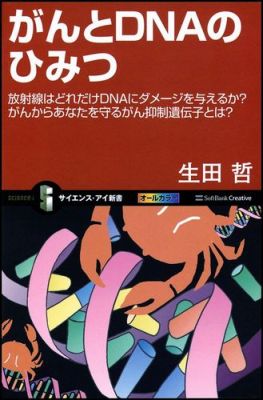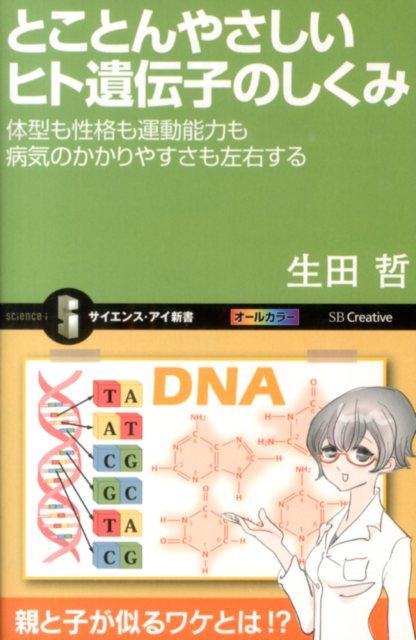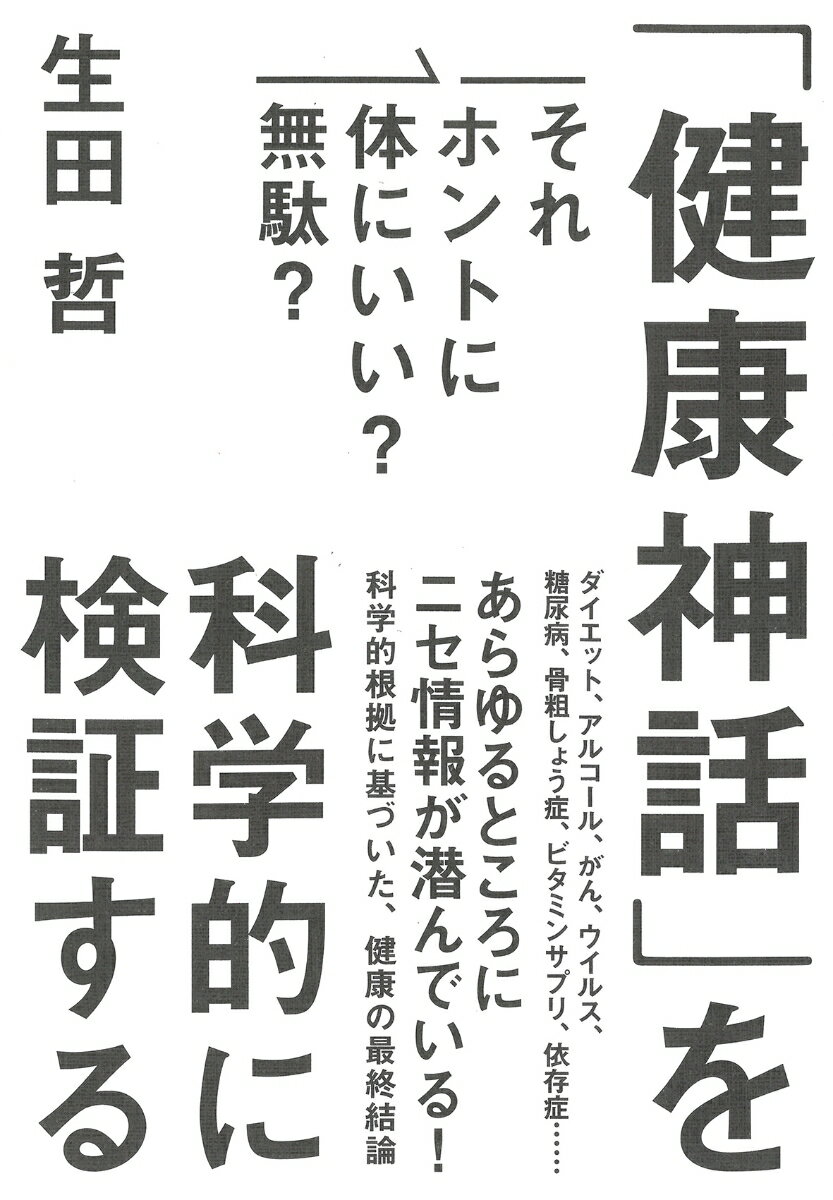自分が子供の頃は、各学校にはなかった特別支援学級のクラスが、今では各学校にクラスがあり、またそのようなクラスも満員で入る事ができないお子さんが多くいらっしゃるようです…
文部科学省のデータによると、平成5年の通級(特別支援学級の人数はまた別です)の児童数は12.259人、平成30年123.095人…。
25年で10倍…💧💧💧
(平成19年から特別支援学級、平成30年から通級など指導が導入されているようですが、私はこの辺の詳しい区分けなどはわかりません。)
癌と同じくらいのの勢いで増えていますよね…
これもやっぱり、食と大きな関係があります。
…ということは、食を見直せば改善する可能性はかなり高いと思います。 実際、グレーのお子様のお母様とお話しすると、やはり朝からパン、お菓子を食べたがる等々…原因が垣間見れます。
生田先生の、こちらのご著書のまえがきの一部をシェアさせて頂きます。
まず、第1章では、頭の良しあしは、遺伝子で決まるのではなく、腸内細菌など体内の微生物の影響のほうが大きいこと、子どもが食べる毎日の食事によって大きく変わることを述べます。
つぎに第2章では、子どもの脳を健やかに育てる食べ物を紹介します。子どもの知能を高める食べ物、子どもを落ち着かせ、熟睡させるミネラル、ADHDなどの発達障害を防ぐ食べ物も紹介します。
第3章では、子どもの脳を悪くする食べ物を紹介します。砂糖、トランス脂肪酸、食品添加物を多く含んだ食品の摂取が脳に悪影響を与えますが、健康によいと思われている養殖サーモンには大量の有害物質が含まれていることも解説します。
第4章では、脳が発達途上にある子どもに薬を飲ませることの問題点を明らかにします。たとえば、発熱した子どもに解熱薬を飲ませてよいのでしょうか、カゼをひいた子どもに感『薬や抗生物質を飲ませてよいのでしょうか。子どもの気分が低下した、子どもに落ち着きがない、というので、抗うつ薬やADHDの薬を服用させていいのでしょうか。
第5章では、子どもにワクチンを注射することのメリットとデメリットを解説します。ワクチン接種は医療行為であり、リスクをともないます。それぞれのワクチンのメリットとデメリットを検証していきます。