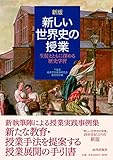 |
新版 新しい世界史の授業: 生徒とともに深める歴史学習
3,080円
Amazon |
『新版 新しい世界史の授業』より、井上先生の磁器とパクス=タタリカを題材とした授業を紹介する。はじめに実践のアウトラインを紹介する。
1.授業の構成
井上は、モンゴル帝国に関する学習をすでに終えていることを前提に、元代に完成された青花磁器に焦点を当ててモンゴル帝国による東西の一体化がもたらした文化交流について考察する授業を提案している。
井上は、モンゴル帝国に関する学習をすでに終えていることを前提に、元代に完成された青花磁器に焦点を当ててモンゴル帝国による東西の一体化がもたらした文化交流について考察する授業を提案している。
最初に導入でサントス宮殿の「磁器の間」の写真を生徒に見せる。これは天井一面に青花磁器が飾られている写真で、ネットで検索したもののヒットする画像はなかった。『新しい世界史の授業』の口絵にカラーで掲載されている。この写真の「不思議だなぁ」をきっかけに、「なぜ青花はこのように天井に飾られ、また、どのようにポルトガルへもたらされたのだろうか」という発問をして本時の内容にはいっていく。
当時の磁器は中国でしか生産がされていなかった。また青色の塗料として用いられるコバルトは、イランやアフガニスタンなどの西アジアでしか見つかっていなかった。青花磁器は中国の磁器の技術と西アジアのコバルトが合わさって完成する。その時期は元代に東アジアと西アジアがモンゴル帝国によって結ばれた時期であった。このような過程で完成した青花磁器は、東西交易を通してヨーロッパに輸入されて高値で取引されていた。冒頭の「磁器の間」は、ポルトガルやスペインが東西交易で手に入れた富の象徴であった。
その後、青花磁器はフィレンツェ焼などのかたちでヨーロッパで模倣される。そして元代後期に完成した青花磁器は、日本でも模倣され伊万里焼がつくられる。
画像はドイツのシャルロッテンブルク宮殿の磁器の間
2.感想など
導入のサントス宮殿の「磁器の間」の写真はとてもインパクトがある。最初は何なのかわからないが、次第に壁(天井)に皿(青花磁器)がはられているのがわかる。青花磁器の実物を持っていくと面白いかもしれない。また、東西文化の融合の結実として、青花磁器を取り上げたことも興味深い。生徒は有田焼や伊万里焼などの磁器については中学で学んでおり、聞いたことはあるであろう。その源流をたどる旅と位置付けてみても面白いかもしれない。
しかし本実践はあくまで講義形式をベースにしており、生徒が共同して学ぶという場面は少ないように感じた。クイズ形式での発問やまとめの部分で「これまでの授業を総合して、青花が成立した背景と、そこにモンゴルが果たした役割を、自分の言葉で説明してみよう」という発問をしているが、基本的には教師が説明をして生徒がそれを聞くといった授業形式だ。そういう意味では伝統的な授業の一例としてみるべきであろう。
またそもそも生徒が磁器に興味を持つのか?という疑問もある。これについては、前述したように青花磁器の実物をもっていくことや中学の授業を思い出させて興味関心を引き出すことが必要であろう。

