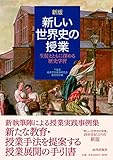 |
新版 新しい世界史の授業: 生徒とともに深める歴史学習
3,080円
Amazon |
今回は『新版 新しい世界史の授業』より、遠藤先生の唐代の文化について扱った2時間の実践を紹介する。詳しくは『新しい世界史の授業』を読んでいただければわかると思うので、はじめに実践のアウトラインだけ紹介する。
1.授業の構成
遠藤ははじめに導入として、世界史資料集を活用して生徒に唐代の長安の特徴を考えさせている。この活動のなかで、従来の文化の深化と外来文化の流入がおこったことを生徒に読み取らせて、学習目標「唐代の文化の深化や多様化が進んだ背景には何があるかを考えて、理解しよう」を提示する。
遠藤はジグソー法を取り入れている。ジグソー法については、熊本大学のHPが詳しい。
ジグソー法とは、協同学習を促すために開発された方法であり、本来的には1つの長い文章を3つの部分に切って、それぞれを3人グループの1人ずつが受け持って勉強する。それを持ち寄って互いに自分が勉強したところを紹介しあって、ジグソーパズルを解くように全体像を協力して浮かび上がらせる手法である。
文章の断片の代わりに互いに異なる事例を勉強したあとで、自分が勉強した事例のグループの代表として他の事例を勉強した代表と一緒にジグソーグループを編成する。そして、相互の共通性や相違点を比較検討する。それぞれ自分の勉強した事例については自分しか詳しく知っている者がいないので、他のメンバーに教える必然性が生じるところがミソだ。
(熊本大学教授システム学研究センターHPより、一部改変)
ジグソー法は2つのステップに分かれている。ステップ1では、各グループに異なる資料を配布し、そのグループでその資料を検討する。ステップ2では、ステップ1で編成したグループを分解して新しいグループを編成する。そして新しいグループではステップ1で配布されたそれぞれに異なった資料をもちよって課題について検討する。
遠藤は以下の4点の資料を用意して、ジグソー法を実践した。
① 唐の羈縻政策:文化的発展を支えたのは皇帝?
② 羈縻政策下のソグド人:文化的発展を支えたのはソグド人?
③ 朝貢がもたらした国際関係:周辺諸国にとっての外交的魅力?
④ 朝貢による朝貢国内への影響:朝貢返礼品の魅力?
上記のステップ2のあと、まとめとして「唐の文化的発展の理由」に関する結論を生徒に書かせる。それを全体で発表したのちに、改めて個人で「唐の文化的発展の理由」について文章を作らせる。最後に教員から羈縻政策と冊封体制について補足説明をして授業を終えている。
