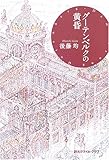グーテンベルクの黄昏とザンジバル島の教会
探検ロマン世界遺産という番組はさりげなく
サヌア旧市街のときも感じたのだけれども
大胆な映像を映し出すことがあるように思う。
「グーテンベルクの黄昏」を読んでいて、ザンジバル島の英国国教会の
シーンを思い出した。
http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cardr128.html
・Memo
~英国史の庭園~ http://www.kingdom-rose.net/Kaikaku2.html
1588~9年にかけて流布されたロラード派のマープレリット文章は「女王陛下の
大権を奪い、力づくで打倒しようとしている」「女王陛下の財産である主教制度の
解散を目論んでいる」として弾圧の対象となった。
「そう、なぜ主教が必要かと言う者は、次にはなぜ王が必要かと問うだろう」
(マープレリット文章)
サヌア旧市街のときも感じたのだけれども
大胆な映像を映し出すことがあるように思う。
「グーテンベルクの黄昏」を読んでいて、ザンジバル島の英国国教会の
シーンを思い出した。
http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cardr128.html
グーテンベルクの黄昏 (創元クライム・クラブ)/後藤 均
¥2,100
Amazon.co.jp
チューダー朝とその百余年に亙る治世はまさに波乱の時代と呼べた。
ウェールズのプリンスの血筋とは言っても、
チューダー家がイングランドの王家となることが出来るとは、
当初誰も予想していなかった。
国内をランカスターの赤ばらと白ばらの二つに分けたばら戦争のお陰で転がり込んできた王座だった。
1458年8月のボズワースの戦いでリチャード3世を破ったヘンリー7世が即位し、
チューダー朝が歴史のページを先に進めることとなった。
チューダー朝の時代を華麗に彩ったのは、並外れた体力と知力で38年もの間
王座に君臨したヘンリー8世であった。
取り替えた王妃は6名。宰相3人を含め著名な貴族や聖職者だけでも50人余を
処刑。しかもローマ法王と断絶し、破門され、結果として英国国教会を設立した。
このことが後々イングランドのみならずスコットランドも巻き込んで、カトリックと
プロテスタントの間に様々な軋轢を生むこととなる。
ヘンリー8世とアン・ブーリンの娘であるエリザベスが新しい女王に即位したとき、
イングランドはフランスやスペインなどの強大国に比べて、二流の弱小国に過ぎなかった。
国力はどん底の状態で、街には浮浪者が溢れ、労働者は安い賃金で働かされていた。
人々は不衛生な生活環境と貧困の中で、伝染病や栄養失調による死の恐怖と日々
向かい合っていた。
宗教面でもエリザベスの前の女王であった姉のメアリーがカトリックへの復帰を
目指したために、国内は国教会とカトリックの間でばらばらになっていた。
それだけに人々がこの青白い細面のプロテスタントの女王の手腕に期待するものは
大きかった。カトリックの強国に囲まれながらも、エリザベスがこの国難に立ち向かうのに
最適な女王であることがまもなくはっきりしてきた。彼女には運もあった。
ウィリアム・セシル、その息子のロバート・セシル、豪腕のフランシス・ウォルシンガム
ら有能な臣下に恵まれた。それに加え、何より彼女は君主としての最も重要な資質を備えていた。
決断力と実行力だった。
エリザベスはイングランドを強国にするために、内外カトリック勢力との戦いに力を注いだ。
カトリックの司教の解任と国教会の主教の任命をイングランド中で行い、
ノーフォーク公爵の叛乱を含むいくつかの女王暗殺計画を凌いだ。
来るべきカトリックの最強国スペインとの雌雄を決する瞬間が刻々と近づく中、
二正面戦争を避けるためかスコットランドの女王メアリー・スチュアートの処刑にまで
踏みこんだ。
・・・
ジェームズの母メアリーはエリザベスの死刑執行書の署名によって断頭刑に処されていた。
カトリック教徒によってメアリーは殉教者であった。その息子がイングランドの王と
なったのである。
・・・
新国王の即位と共に、清教徒がまう動いた。
彼らはピューリタンとしてより深い改革を求めていた。
<千人嘆願書>を王に提出し、ハンプトン・コート会談へと持ち込んだ。
だが、その期待は思わぬ形で裏切られた。
清教徒の復権どころか、彼らの期待とは正反対に、
国教会側の猛反対により、清教徒とカトリックの双方を排除する旨が宣言された。
こうして会議は「主教なければ国王なし」の言葉とともに閉会となった。
Chained to History
・Memo
~英国史の庭園~ http://www.kingdom-rose.net/Kaikaku2.html
1588~9年にかけて流布されたロラード派のマープレリット文章は「女王陛下の
大権を奪い、力づくで打倒しようとしている」「女王陛下の財産である主教制度の
解散を目論んでいる」として弾圧の対象となった。
「そう、なぜ主教が必要かと言う者は、次にはなぜ王が必要かと問うだろう」
(マープレリット文章)