日本の中世 戦乱の世のことを書いてある本が『太平記』
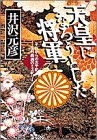
井沢元彦氏の「逆説の日本史」シリーズは何冊も読んでいて、
それぞれ面白かった。
出世作の 「猿丸幻視行」 はさすがに力作。
そして、この「天皇になろうとした将軍―それからの大平記 足利義満のミステリー 」
はかなりいいと思う。
売り文句の「著者会心の歴史ノンフィクション」はうそではない。
どうやら、この作品は氏が
「歴史ノンフェクションの道に進むきっかけを作った、思い出深い作品」
であるらしい。
日本の中世の歴史などあまり興味がない部分だったけれども、この一冊で
随分とみえてきたような気がする。
なぜ戦乱記を『太平記』と呼ぶのか?
『太平記』に22巻目が無いという点に注目したことである。
これが、『太平記』の最大の謎のきっかけであるからである。
考古学では、「あるべきものが無い」とか、「あるべきでないものがある」
ということは大変なことで、これを解決しないと次に進めない。
歴史学では、あるべきものがなくても、あるものだけで十分論考できると
考えているようで、そのため、今まで多くの歴史学者によって『太平記』
にある多くの謎が解かれなかったのであろう。
戦乱の世のことを書いてある本が、『太平記』という名ではおかしいという
理由をつきとめてしまうから愉快だ。
その結論は、「朝敵を滅ぼして、四海を太平ならしめんと思う」といいう
ところにあると結論づける。
(解説 吉村作治 より)
 それに、体制にとって都合のよくないものは無視される、焼かれる、隠されている、のが常かも。
それに、体制にとって都合のよくないものは無視される、焼かれる、隠されている、のが常かも。「義満の野望を金閣寺の奇妙な三層構造から
解読するという大胆な説」
随分前にもどこかで以下のような説明を聞いた
ことがあったような記憶がかすかにあるのですが、
どこでだったか....
まず、一階が公家風の寝殿造りであり、
しかも金箔が押されていないことがポイントだ。
つまり”金”もない、"粗末な公家”の上(二階)に
”金箔の武家”がある。
と考えればいい。
・・・
だから結局この金閣は、寝殿造りに住む公家 (あるいは天皇)よりも
武家が上で、さらにその上で一番エライのはこのオレ様だということを言っている。
第8章 金閣寺に塗り込められた足利義満の「野心」