ソロモンの秘宝とシバの女王
Tintoretto: «The Queen of Sheba and Solomon» (ca. 1555). Prado Museum

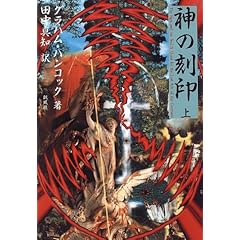 なにげなく、ハンコックの「神の刻印
」を手にしたら、
なにげなく、ハンコックの「神の刻印
」を手にしたら、
きっかけは、
この間、日本のテレビで四国の剣山にあるかもと放映されいた、
失われたアークはエチオピアにあるという噂。
これをきいて、超古代の世界に入り込んでいったらしい。
シバの女王 が見物にでかけ、そのときの子である
メネリク1世 が聖櫃をエチオピアに持ち帰ったという。
とにかく、「ファラシャ」という、古い古いユダヤ教徒が
エチオピアにいて、イスラエルに何万人も移住したけれども....
というのは事実。
【動画】故郷を捨て、イスラエル移住を待つ「ファラシャ」たち - エチオピア
「契約の箱」見つかる?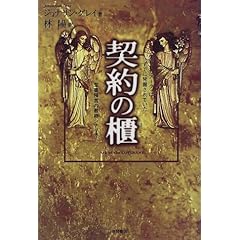
この蓋は贖いの座とよばれ、そこに犠牲獣の血を注ぐ
ことによって、神と人との交わりが回復されるとされた
http://dateiwao.fc2web.com/arkoftheconvenant.htm
* このRon Wayatt 氏(1933-1999)は The Ark of the Covenant 以外にも
The true Noah's Ark なども Claimed discoveries にある。
契約の櫃―「失われたアーク」はすでに発掘されていた (単行本)
ジョナサン グレイ (著), Jonathan Gray (原著), 林 陽 (翻訳)

この本の表紙にあるように、聖櫃は日本のお神輿に似ている。
失われたアークで検索してヒットした本。この著者が
ハンコックの「神の刻印」の日本語訳をして、あとがきを
書いている。
以下 「神の刻印」 訳者(田中真知) あとがきより
1. アークを追い求めた人々の歴史
12世紀の聖杯物語の代表作『パルチヴァール』の解読 アークの探求が受け継がれている
聖杯物語、テンプル騎士団、プレスター・ジョン伝説、大航海時代、フリーメイソンの成立、
ジェイムズ・ブルースの青ナイル水源探検
ここには従来の西洋史研究の死角をつく斬新な見方がちりばめられている。
「聖杯」がアークの隠喩として「発明」されたという説。
プレスター・ジョンの新書が、エチオピア王によって意図的に作成されたものであるする説。
テンプル騎士団廃絶の原点を、騎士団とエチオピアとの確執とみる説。
アークにまつわる知識や情報が中世から近代まで連綿と伝わってきたという説。
今世紀半ば、聖杯文学の研究者ヘレン・アドルフは、聖杯伝説とエチオピアの伝説との関連に
言及していた。
2. アークそのもののだとったルートの探求
ハンコックは
アークが7世紀半ばにエレサレムの神殿から失われ、上エジプトのエレファンティネ島を経て、その後
ナイル川を遡ってエチオピアに入ったと推理する。
エレファンティネのユダヤ人がエチオピアに入り、ファラシャの祖先となったという説は、これまでにも
唱えられていた。しかし、現在の定説では、ファラシャは、西暦1世紀頃、南アラビアを経てエチオピアに
やってきたユダヤ人に由来するとされている。
だが、ハンコックは
ファラシャが、当時の南アラビアでユダヤ人が行なっていた儀式より明らかに古い習慣を残していること。
エレファンティネ・ユダヤ人とファラシャの言語上の類似
アークのルートにまつわるファラシャの伝承内容と考古学的事実の一致
エレファンティネのユダヤ神殿の崩壊伝説と伝説上のアークのエチオピアイリの時期の一致
著者の仮説はみごとな説得力を帯びてくる。
3. アークの実体 アークとは何か
旧約聖書の記述に従えば、アークは大変な威力を持った箱であり、そこから時に応じて炎や光が
放たれ、人間を打ち倒したり、腫れ物を生じさせたりするとされる。
「学問的」には、奇跡そのものの真偽が正面から問題にされることはない。
アークの奇跡はあくまでも比喩として解釈されるのがふつうである。
そればかりか、預言者モーセを架空の人物とする見方も多い。
モーセの実在を裏付ける史料が、旧約聖書のほかには何も見つかっていないからである。
このことから「出エジプト記」は史実ではなく、古代イスラエルの祭儀劇、もしくは穀物霊再生の
祝祭神話であると主張する学者も多い。
実際、1967年から82年にかけて、イスラエルの考古学者によって、当時占領中だったシナイ半島の
集中的な調査が行なわれたが、そこからモーセとイスラエル人の40年間の彷徨の痕跡は何一つ
見出されなかった。
けれども、その一方で近年、旧約聖書の内容を裏付けるような多くの考古学的発見が相次いでいる
のも事実だ。
1986年には、預言者エレミヤの弟子として「エレミヤ書」を記したバルクの印章発見
1990年には、ガザ地区の北のアシュケロンで「出エジプト記」に記されている黄金の子牛像によくにた
像が発掘された。
1993年には、「イスラエルの王」「ダヴィデの家」と書かれた紀元前9世紀頃のアラム語の碑文が
テル・ダンで発見され、ダヴィデ王の実在を疑うことは、もはやむずかしくなった。
1996年には「岩のドーム」内での契約のアークの安置場所を明らかにした画期的論文が発表された
("The Ark of the Covenant: Where is Stood in Solomon's Temple"
Biblical Archaeology Review, January/Feburary 1996)
論文の著者のリトメイヤーによれば、基礎石の北西側に、「出エジプト記」に記さえたアークの寸法と
一致する長方形のくぼみがあるという。
・・・
訳業のさなか、カイロ博物館や上エジプトの神殿郡を足繁くおとずれた。そのあと、調査や確認のため
ふたたびエチオピヤやイスラエルに出かけ、ラリベラでは「ティムカット」を見た。
そのとき(1996年1月)の見聞から、本書の内容に関連することを、いくつかつけくわえておきたい。
まず、本書に登場するアクスムのアークの番人のゲブラ・ミカイルは1991年の半ばに亡くなり、
アッバ・テスファマリアムとうい名の修道僧が現在、跡を継いでいる。彼もまた歴代の番人の例にならい、
礼拝堂から一歩も外にでない暮らしを送っている。
ゴンダール周辺のファラシャの村は、本書にも登場するウェレカ、アンボベル、それにコソイェの3つが
現在でも残っているが、いずれも人口は半減し、僧もいない。ウェレカはゴンダールからの観光コース
になっており、粗末なダヴィデの星を飾った数軒の小屋の前では、いまだに粘土板のシェバの女王と
ソロモンの像の類が売られていた。
なぜイスラエルの移送作戦のときに移住しなかったのか、と聞いたところ、飛行機に乗るのが恐かった
からちおう答えが返ってきた。
一方、希望に燃えてイスラエルに移住したファラシャたち --その数は6万人にのぼる -- にしても、
かならずしも幸せになっているわけではないようだ。
メモ
契約の聖櫃 /『日猶同祖論的な視点から眺めた神風』 http://www.geocities.co.jp/Berkeley/6261/hirohiko.html

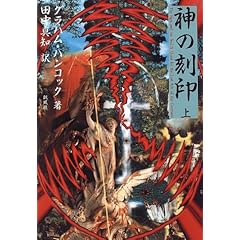 なにげなく、ハンコックの「神の刻印
」を手にしたら、
なにげなく、ハンコックの「神の刻印
」を手にしたら、きっかけは、
この間、日本のテレビで四国の剣山にあるかもと放映されいた、
失われたアークはエチオピアにあるという噂。
これをきいて、超古代の世界に入り込んでいったらしい。
- 実際は一生エチオピアのシオンのマリア教会からはなれない
- アクスム
のアークの番人の僧がいて、
この番人は以前テレビかなにかで見たことがある。
- 実物をみることはできない。このあたりは、日本の伊勢神宮の
八咫の鏡 と似ている。
シバの女王 が見物にでかけ、そのときの子である
メネリク1世 が聖櫃をエチオピアに持ち帰ったという。
とにかく、「ファラシャ」という、古い古いユダヤ教徒が
エチオピアにいて、イスラエルに何万人も移住したけれども....
というのは事実。
【動画】故郷を捨て、イスラエル移住を待つ「ファラシャ」たち - エチオピア
「契約の箱」見つかる?
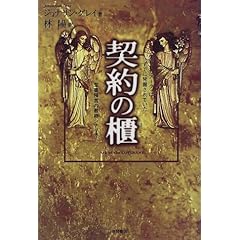
この蓋は贖いの座とよばれ、そこに犠牲獣の血を注ぐ
ことによって、神と人との交わりが回復されるとされた
http://dateiwao.fc2web.com/arkoftheconvenant.htm
* このRon Wayatt 氏(1933-1999)は The Ark of the Covenant 以外にも
The true Noah's Ark なども Claimed discoveries にある。
契約の櫃―「失われたアーク」はすでに発掘されていた (単行本)
ジョナサン グレイ (著), Jonathan Gray (原著), 林 陽 (翻訳)

この本の表紙にあるように、聖櫃は日本のお神輿に似ている。
失われたアークで検索してヒットした本。この著者が
ハンコックの「神の刻印」の日本語訳をして、あとがきを
書いている。
以下 「神の刻印」 訳者(田中真知) あとがきより
1. アークを追い求めた人々の歴史
12世紀の聖杯物語の代表作『パルチヴァール』の解読 アークの探求が受け継がれている
聖杯物語、テンプル騎士団、プレスター・ジョン伝説、大航海時代、フリーメイソンの成立、
ジェイムズ・ブルースの青ナイル水源探検
ここには従来の西洋史研究の死角をつく斬新な見方がちりばめられている。
「聖杯」がアークの隠喩として「発明」されたという説。
プレスター・ジョンの新書が、エチオピア王によって意図的に作成されたものであるする説。
テンプル騎士団廃絶の原点を、騎士団とエチオピアとの確執とみる説。
アークにまつわる知識や情報が中世から近代まで連綿と伝わってきたという説。
今世紀半ば、聖杯文学の研究者ヘレン・アドルフは、聖杯伝説とエチオピアの伝説との関連に
言及していた。
2. アークそのもののだとったルートの探求
ハンコックは
アークが7世紀半ばにエレサレムの神殿から失われ、上エジプトのエレファンティネ島を経て、その後
ナイル川を遡ってエチオピアに入ったと推理する。
エレファンティネのユダヤ人がエチオピアに入り、ファラシャの祖先となったという説は、これまでにも
唱えられていた。しかし、現在の定説では、ファラシャは、西暦1世紀頃、南アラビアを経てエチオピアに
やってきたユダヤ人に由来するとされている。
だが、ハンコックは
ファラシャが、当時の南アラビアでユダヤ人が行なっていた儀式より明らかに古い習慣を残していること。
エレファンティネ・ユダヤ人とファラシャの言語上の類似
アークのルートにまつわるファラシャの伝承内容と考古学的事実の一致
エレファンティネのユダヤ神殿の崩壊伝説と伝説上のアークのエチオピアイリの時期の一致
著者の仮説はみごとな説得力を帯びてくる。
3. アークの実体 アークとは何か
旧約聖書の記述に従えば、アークは大変な威力を持った箱であり、そこから時に応じて炎や光が
放たれ、人間を打ち倒したり、腫れ物を生じさせたりするとされる。
「学問的」には、奇跡そのものの真偽が正面から問題にされることはない。
アークの奇跡はあくまでも比喩として解釈されるのがふつうである。
そればかりか、預言者モーセを架空の人物とする見方も多い。
モーセの実在を裏付ける史料が、旧約聖書のほかには何も見つかっていないからである。
このことから「出エジプト記」は史実ではなく、古代イスラエルの祭儀劇、もしくは穀物霊再生の
祝祭神話であると主張する学者も多い。
実際、1967年から82年にかけて、イスラエルの考古学者によって、当時占領中だったシナイ半島の
集中的な調査が行なわれたが、そこからモーセとイスラエル人の40年間の彷徨の痕跡は何一つ
見出されなかった。
けれども、その一方で近年、旧約聖書の内容を裏付けるような多くの考古学的発見が相次いでいる
のも事実だ。
1986年には、預言者エレミヤの弟子として「エレミヤ書」を記したバルクの印章発見
1990年には、ガザ地区の北のアシュケロンで「出エジプト記」に記されている黄金の子牛像によくにた
像が発掘された。
1993年には、「イスラエルの王」「ダヴィデの家」と書かれた紀元前9世紀頃のアラム語の碑文が
テル・ダンで発見され、ダヴィデ王の実在を疑うことは、もはやむずかしくなった。
1996年には「岩のドーム」内での契約のアークの安置場所を明らかにした画期的論文が発表された
("The Ark of the Covenant: Where is Stood in Solomon's Temple"
Biblical Archaeology Review, January/Feburary 1996)
論文の著者のリトメイヤーによれば、基礎石の北西側に、「出エジプト記」に記さえたアークの寸法と
一致する長方形のくぼみがあるという。
・・・
訳業のさなか、カイロ博物館や上エジプトの神殿郡を足繁くおとずれた。そのあと、調査や確認のため
ふたたびエチオピヤやイスラエルに出かけ、ラリベラでは「ティムカット」を見た。
そのとき(1996年1月)の見聞から、本書の内容に関連することを、いくつかつけくわえておきたい。
まず、本書に登場するアクスムのアークの番人のゲブラ・ミカイルは1991年の半ばに亡くなり、
アッバ・テスファマリアムとうい名の修道僧が現在、跡を継いでいる。彼もまた歴代の番人の例にならい、
礼拝堂から一歩も外にでない暮らしを送っている。
ゴンダール周辺のファラシャの村は、本書にも登場するウェレカ、アンボベル、それにコソイェの3つが
現在でも残っているが、いずれも人口は半減し、僧もいない。ウェレカはゴンダールからの観光コース
になっており、粗末なダヴィデの星を飾った数軒の小屋の前では、いまだに粘土板のシェバの女王と
ソロモンの像の類が売られていた。
なぜイスラエルの移送作戦のときに移住しなかったのか、と聞いたところ、飛行機に乗るのが恐かった
からちおう答えが返ってきた。
一方、希望に燃えてイスラエルに移住したファラシャたち --その数は6万人にのぼる -- にしても、
かならずしも幸せになっているわけではないようだ。
メモ
契約の聖櫃 /『日猶同祖論的な視点から眺めた神風』 http://www.geocities.co.jp/Berkeley/6261/hirohiko.html

