『ダ・ヴィンチ・コード』はなぜ問題なのか
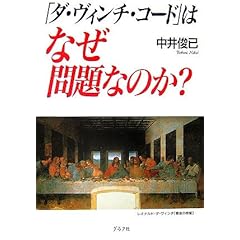
「『ダ・ヴィンチ・コード』はなぜ問題なのか? 」
何冊か『ダ・ヴィンチ・コード』の解説本を読んだけれども、
この本がシンプル(?) でわかりやすい。
イエスとマグダラのマリアの結婚説は
この本が元だということで
これは(エヴァンゲリオンで死海文書を知って、以前、半分くらいは読んだはず..)
手元にあったので、探してみたら、確かに記述がありました。
ただこの「『ダ・ヴィンチ・コード』はなぜ問題なのか? 」 では「カトリック教会では7月22日を彼女の記念日として、世界中で彼女の功徳を称え続けてきた。」とありますが...
確か本流としては今世紀になってから見直したのではないかと。
以下はWikipdia マグダラのマリア より
第2バチカン公会議 を受けて1969年にカトリック教会がマグダラのマリアを「罪深い女」から区別するなど、
その地位の見直しが始まった。 20世紀の半ばに、異端の書としてこれまで姿を消していた書物がナグ・ハマディ写本
の発見など、その姿を現してきた。 これも契機になっているであろう。 しかし、娼婦でなければ妻とするのは「同じ見方の裏と表」と、エレーヌ・ペイゲルス(Elaine Pagels
)は指摘する。 ペイゲルスによれば、「男たちは、マグダラのマリアがイエスの弟子でも、リーダーでもなく、性的な役割だけを与えようとして、このようなファンタジーを作っているのではないかとさえ思える」と。
あと、この「『ダ・ヴィンチ・コード』はなぜ問題なのか? 」で印象的だったのが
以下のオプス・デイに関する質疑応答。
問2 映画(小説)に出るような苦行は実際するのですか?
いいえ、ただし、約3分の1の独身メンバーが小さな鞭やしリス(鎖)を使う苦行をする習慣があります。
こうした苦行はカトリック教会においては非常に伝道的であり、かつ現代でも行われていることです。
例えば、マザーテレサも自分がそのような苦行をしていることを公言していました。
日本でも断食や滝に打たれるといった苦行はなじみ深いものです。
そういえば、マザーテレサのこの鞭の話は当時聞いたとき、ちょっと驚いたことを思い出しました。
Wikipedai のオプス・デイ の項目(日本語)には鞭や鎖の文字はさすがにみあたりません。
しかし、カトリックにはいろいろな組織があるのに、「グノーシスの薔薇」にあったように、
まさか、ルターで真っ二つに割れることになるとは、誰も思ってもいなかったのでしょう。
割れた原因は神学論争ではなく、政治とお金だったようなことが「グノーシスの薔薇」でも
ペッペにより語られていましたが。
映像はあまり興味はないけれども、そもうちにまた
- ダ・ヴィンチ・コード〈上〉/ダン・ブラウン

- これは再読してみなければ。
