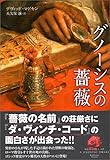西欧の叡智
 そういえばモーニングにイタリアを舞台にしたものが連載されていた、程度の
そういえばモーニングにイタリアを舞台にしたものが連載されていた、程度の認識でした。
ボルジア家とういのは、どこのことかと思ったら、スペインなんですね。
Wikipedia の「アレクサンデル6世」には以下のように、かなり辛辣なことが
明記されています。
当時の高位聖職者たちのように彼のモラルは堕ちきっており、
金と女に情熱を傾けていた。このころには、
すでに数人の子供が愛人たちから生まれていた。
こうして彼が教皇アレクサンデル6世を名乗ることになる。
このコンクラーヴェ における贈収賄は広く世に知られ、
彼が三重冠を金で買ったと非難される原因になった。
教皇は自らの地位を手にいれるためにあらゆる同盟を結んだが、孤立を恐れる余りフランスのシャルル8世 の助けを求めた。さらにナポリ王が孫娘をめあわせたミラノ公との提携を図るようになると、シャルル8世をそそのかしてナポリ王国 を狙わせている。
フランスが勝手にイタリアを占領しようとしたわけでもなかったようです。かけひきですね。
西欧は、こんなことを延々と何百年も前からやってきているのですから、たちまわりが上手なわけです。
また、宗教上のトップになる人に子供がいたりすると、危険ですね。
カトリックはこうした数々の試練を乗り越えてきているけれども、新しいところのものは
世代交代のあたりが、やはり危なそうで、よって政治と宗教の分離は過去の歴史をみても重要。
こういうところは、西欧の叡智。
そういえば、先日、ちょとした記事がありました。
誰も気づかずに見すごされてしまうには大きすぎる小さな記事 より
週刊実話の5月29日号に、先般来日した中国の胡錦涛主席が創価学会の池田大作名誉会長を持ち上げて、
彼は立派な政治家だ、などと繰り返し発言した、
これ に、あわてた創価学会関係者は、外務省と一緒になって、
この発言が広まらないように奔走した、という趣旨の記事があった。
胡錦涛主席のこの言葉は大手新聞やテレビでは一切報道されていない。
いうまでもなく、政教分離は憲法20条で原則禁止されている。
創価学会は日蓮正宗系の宗教団体だ。
その一方で創価学会は連立政権党である公明党の支持母 体である事は周知の事実だ。
だから、これは政教分離の原則にもとることにならないか、という問題は、
これまで折に触れて取りざたされてきた。
そんな中で、 中国の元首が、創価学会の名誉会長は政治家だと言ったという。
これが事実ならば、やはり外部の人間が客観的にそのように受け止めているのか、と言うことに なる。
政教分離問題が再び問題視されかねない。
週刊実話の記事は、見過ごされてしまうには大きすぎる小さな記事だ。
以下
グノーシスの薔薇/デヴィッド マドセン からの抜粋
この時代、イタリアは戦乱と混沌で引き裂かれていた。
1498年、ジョバンニ・デ・メディチが枢機卿に任じられてから6年後、
ボルジア家出身のアレクサンドル6世が教皇の座に収まった6年後、
そしてオルレアン公ルイがシャルル8世の後を襲ってフランス王に就いた
(彼はついでにエレサレムとシチリアの王でありミラノ公でもあると名乗った)
その年のこと。フランス人たちは、ミラノを略取しようとイタリア半島に再度侵攻してきた。

グノーシスの薔薇/デヴィッド マドセン より
ナポリ王国やさらに南部の地域は、フランス人に侵略された傷跡を癒している最中だった
(シャルル8世がナポリの聖堂で「シチリアとエレサレムの王」を戴冠したのは、
ほんの3年前のことだった)。
較べれば、ペルージア、ウルビーノ、シエナといった共和国もほうが、まだ期待が持てたのだ。
なるほど、シャルルが帰国した後、フランス軍第一次侵略部隊はすぐさま撃退されてしまっていたが、
南部地方にはいまだ不安と恐怖が色濃く残っていた。それに、ひとたびミラノを手に入れたとなれば、
ルイ12世がナポリに食指を動かすのは時間の問題だと誰もが知っていた。
それに引き換え、アレクサンドル6世の庶子チェーザレ・ボルジアが、権力への渇仰に駆られて
ロマーニャ一帯を恐怖のどん底にたたき込むだろうとは、誰も予想していなかった。
チェーザレ・ボルジアを唆(そそのか)し、手助けしたのは、他ならぬルイだった
(アレクサンドル6世は、彼の結婚を教皇権限で無効にし、おかげでルイは晴れて
アンン・ド・ブルターニュと結婚することができた)。
チェーザレ・ボルジアは、ルイに従ってミラノに出征した。彼が程なく引き起こす混乱状態は、
まだ姿を現していなかった。
・・
メジチ家は1497年に愛するフィレンツェの町から追放され、17年後まで帰還することが
かなわなかった・・
1503年のことである。色々な意味で重要な年だった。ロマーニャ地方では、血なまぐさい戦いを経て、
チューザレ・ボルジアが覇権を確立した。形の上ではフランスの支配下にあったが、実質は彼が、
彼一人が支配者だった。実際、彼は為政者としては極めて優秀で、それまでの混乱状態を一掃して
(まあ、混乱状態の過半は彼が自ら引き起こしたものだったのだが)、立派な秩序を築き上げた。
だが、父親の教皇アレクサンドル6世が死ぬと(愛用の毒薬を誤って飲み込んだと、まことしやかに
噂された)、チューザレの没落も始まった。
ルイ12世が死んで、フランソワ1世が王位に即と、事態は全く予期せぬ新しい局面を迎えた。
フランソワは若く野心に溢れていたが、権力亡者のくそ婆である母親ルイーズ・ド・サヴォアに
唯々諾々と従っていた。
これが政治的な駆け引きでしかないことは、笑うほか無い自明の理、なぜならフィリベルタは
実に醜く、ジュリアーノの配偶者としてはあり得ないほど年を食っていたからだ・・・が、
ジュリアーノとフィリベルタは1515年6月25日、本当に結婚してしまった。
今やフランソワ1世の叔母の夫となったジュリアーノは、当然レオにフランス側に立つように
進める
P204
和平交渉は長引いたが、フランソワは驚くほど寛大なところを見せた。おそらくは、
マクシミリアンとイングランド王ヘンリー8世(トーマス・ウルジーを枢機卿にしたおかげで、
彼はレオの忠実な友となっていた)の間の同盟が成立して、彼から勝利の果実を奪ってしまう
ことを恐れていたのだろう。 P210