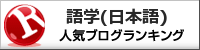いままでに書いたことをまとめておく。
文章を書く時、「やわらかい感じがする文章」ってことは常に意識にある。あまり徹底すると頭の悪い子の文章のようになる可能性は否定できない。格調の高さを目指すなら、正反対の方向を考えるべき(こういう場合も、誤用と言われる危険をおかして「べし」にはしない)、ってこともわかってはいる。それでも読み手に苦痛を与えるような書き方をするよりはマシと考えて深みにはまっていく(泣)。
まず発端は「赤い本」だろう。足跡帳の日付は2008年11月09日になっている(笑)。
【伝言板 板外編3──文語調の表現は避ける】
http://
「押しも押されぬ」という表現に関して質問をいただいたので、「赤い本」の記述から抜粋します。質問内容に関しては、下記をご参照ください。
【足跡帳NO.4】
http://
【練習問題33】
次の表現を、読みやすい印象の表現に書きかえてください。
1)可及的速やかに
2)~という特徴を有しています
3)明日、会議を行います
4)会議を開始します
ここであげたのは、「文語調」で堅苦しく感じられる表現です(「文語調」というのは適切な表現ではありませんが、こう呼ぶことにします)。
まず、書きかえ案をあげておきます。
1)可能な限り速やかに
2)~という特徴をもっています
3)明日、会議を開きます
4)会議を始めます
1)の「可及的速やかに」は、「お役所言葉」などと呼ばれる類の表現です。ふつうの文章の中で、このような表現を使う人はいないでしょう。書きかえ案でも構いませんが、「できるだけ速く」ぐらいにすれば、もっと読みやすい印象になります。
2)の「有する」という言葉は、たいていの場合、「もつ」に書きかえても問題がありません。ただしこの例文の場合は、「~という特徴がある」にしたほうがもっと読みやすい印象になります。
3)の「行う」という言葉も、できるだけ避けたほうが無難です。とくに過去形の「行った」は「オコナった」とも「イった」とも読めてしまうので、使うべきではありません。「明日、会議をします」としても構いませんが、ニュアンスが少しかわる気がします。
4)「開始する」は、「開」と「始」という意味が似ている言葉をダブらせている動詞です。こういう動詞は、片方の言葉などを使って書きかえたほうが読みやすい印象になります。
・停止する→止める/やめる
・使用する→使う/用いる
・軽減する→軽くなる/減る
・提示する→示す
ただし、書きかえることによってニュアンスが大きくかわる場合もあるので、無理をしてまで徹底する必要はありません。
【Coffee Break】
文語調の誤用
【練習問題34】
次の文のどこがヘンなのか考えてください。
1)この旅館には、同じ間取りの部屋がひとつとない。
2)ホームラン王になった彼は、押しも押されぬ4番打者に成長したといえるだろう。
ここであげた表現はデス・マス体で使うことが少ない気がするので、例文をデアル体にしました(このあとも同様の理由で例文をデアル体にする場合があります)。
「立派に見える」と考えられるためか、文語調の表現はとくに必要がないときにも使われることが多いようです。誤用もよく目にするのは、意味をよく考えずに形だけをマネしようとするせいでしょうか。
1)は「ひとつと」の使い方がヘンです。「ふたつと」にするべきでしょう。「ふたつとない」にすれば間違いではなくなりますが、依然としてヘンです。「ふたつとない」は、「(世界中を探しても)めったに例がない」ぐらいの強い表現ですから、この程度のことで使うべきではありません。「この旅館は、すべての部屋の間取りが違う。」ぐらいで十分でしょう。
2)の「押しも押されぬ」を、「押すに押されぬ」としている誤用もよく目にします。正しい使い方は、「押しも押されもせぬ」です。
この場合も、「押しも押されもせぬ」に直してもヘンな感じが残ります。「押しも押されもせぬ」という強い表現と、文末の「~だろう」がチグハグな印象になっているからです。「不動の4番打者」ぐらいで十分でしょう。「ホームラン王」になったほどの選手ですから、「球界を代表する4番打者」としてもよいかもしれません。
【追記】
文中で「押すに押されぬ」を誤用としているのは間違いです。
下記をご参照ください。<(_ _)>
http://
伝言板 板外編3──文語調の表現は避ける〈2〉
下記の仲間。
日本語アレコレの索引(日々増殖中)
http://
日本語アレコレの索引(日々増殖中)【7】
http://
mixi日記2011年11月23日から
下記の続き。
【伝言板 板外編3──文語調の表現は避ける】
http://
ちいと必要があって、「いえよう言葉」関する「赤い本」の記述から抜粋します。
●「~といえよう」は避ける
【練習問題35】
次の表現を、読みやすい印象の表現に書きかえてください。
1)問題といえよう
2)問題となろう
3)問題があろう
4)問題がなかろう
ここにあげた文末は、いずれも避けたほうが無難です。それぞれ、次のように書くほうが読みやすい印象になります。
1)問題といえよう↓問題といえるだろう
2)問題となろう ↓問題となるだろう
3)問題があろう ↓問題があるだろう
4)問題がなかろう↓問題がないだろう
もう少し細かく見ていきましょう。1)~3)は、デス・マス体で次のように書くこともできます。
1)問題といえましょう
2)問題となりましょう
3)問題がありましょう
ふつうの文章では避けたほうが無難という点は、「~といえよう」などの文末と同様です。
少しよけいなことを書くと、2)のような使い方の「と」は、原則として「に」にしたほうが読みやすい印象になります。すべてを「に」にしたほうがよい、ということではありません。本書では、「と」でも「に」でもよい場合には「に」を使っていますが、例外もあります。たとえば、この項の冒頭近くで〈「避けたほうが無難」などとして〉〈「避けたほうが無難」として〉と、2カ所も「と」を使っています。「に」にするべきか迷いましたが、語感が悪くなる気がしてやめました。このほか、「一体となる」「一丸となる」のような慣用句も、「に」にすると不自然です。
3)の「問題があろう」は、同じ「あろう」を使っていても「問題であろう」なら、堅苦しい感じがずっと軽くなります。ふつうの文章でも、目にすることが多い形です(【Coffee Break】参照)。
3)4)の「あろう」と「なかろう」は、文末以外でも使われることがあります。「問題があろうがなかろうが、とにかくやるしかない」という使い方なら、例文とは用法が違うのでさほど堅苦しさが感じられません。これも「問題があってもなくても、とにかくやるしかない」ぐらいにしたほうがよい気はしますが。
【Coffee Break】
「~といえよう」はよく見かけるが……
●「~といえよう」を毛嫌いするきわめて個人的な理由
「~といえよう」に類する表現は、乱用しなければ問題はないのかもしれません。きわめて個人的な理由で、この表現を毛嫌いしているところがあります。気になりはじめたのは、第2章でも書いたレジャー関係の業界誌の仕事したことがきっかけです。
業界関係者が書いた原稿の中に、「~といえよう」に類する文末が頻繁に出てきました。【練習問題35】としてあげたもののほか、「できよう」「わかろう」「されよう」「輝こう」「明るかろう」……など、「だろう」という言葉が禁句になっているような印象でした。「いくらなんでもこんな使い方をしない」と思った表現もあります。
前項で「どんなにむずかしい故事でも、それにふさわしい雰囲気の文章の中で使うのなら」ヘンではない、と書きました。文語調の言葉も、同様です。それなりの文章の中で適切に使うのならヘンではありません。ただし、ふつうの文章の中ではむやみに使わないほうが無難です。
下記も少し関係あるかも。
【「~だ」と「~である」はどう違うか】
http://
【「~だ」と「~である」はどう違うか2──やわらかい感じがする文章を書くために】
http://
カテゴリーがわからん。
【伝言板】の気もするし、下記の仲間って気もする。
下記の仲間。
【日本語アレコレの索引(日々増殖中)】
http://
下記の続き。
http://
mixi日記2009年09月02日から
デアル体の文末に来る「~だ」と「~である」には意味の違いはないが、ニュアンスに微妙な違いがある。こういう微妙なニュアンスの違いの積み重ねが、文章全体の印象に与える影響ってバカにできないと思う。文末に「~である」が多用されている文章って、読んでいて異様な感じがする。
「やわらかい感じがする文章」を書くためのヒントを少し書いてみたい。
いつも書いていることだけど、「やわらかい感じがする文章」のための心得を裏返すと「かたい感じがする文章」のための心得になる。そういう文章のほうが「立派な文章」に見える可能性は否定できない。そういう文章を書きたがる人は多いけど、個人的には、一般人はやめたほうがいいと思う。学者や年寄りっぽい文章を装いたいなら話は別だけど。
●『理科系の作文技術』(木下是雄)の教え
先日アップした読書感想文http://
================================
【引用部】
(前略)「よい」、「ゆく」、「より」、「のみ」は、私の語感では、話しことばとしてはもう死語になっているからだ。実をいうと私は「10時より午前の部の講演をはじめます」、「これより先、空港待合室では……」などと言われるとぞっとするのである。
「よい」に関しては、ちょっと疑問が残る。デス・マス体の場合、これが実に悩ましい。「ゆく」に関しては注があり、goの場合には「行く」と書き、読み方は読み手にまかせるそうな。同じ考えにブチ当たるとうれしくなってしまう。
それにしても、この著者の言語感覚の若々しさは異常なほど。
================================
著者は、この直前には、できるだけ「~である」を使わずに「~だ」を使うとしている。この人の感覚は信頼できる。
「よい」については注釈が必要だろう。個人的には、原稿を書くときには、デス・マス体のときには「よい」を使い、デアル体のときには「いい」を使っている。
デス・マス体のときに「いい」を使うと、「いいでしょう」「いいかもしれません」などの形が妙に感じられる。個人的な感覚なので、強く主張する気はない。
デアル体の場合は、文末にくるときは原則として「いい」。「よい本」などのように直接名詞にかかる形容詞として使う場合は「よい」を使う(実際には別の言葉に置き換えることが多い気がする)。
ここまでを箇条書きにしておく。
1)「~である」を使わずに「~だ」を使う(理想を言えば「~だ」もできるだけ使わない)
2)「よい」は使わず「いい」を使う(ex.「いい方法がある」「こうすればいい」)
3)補助動詞の「ゆく」は使わず「いく」を使う(ex.生きていく私)
※これは現代では「ゆく」とか「ゆう」を使う人は少数だろう
4)「起点のヨリ」は使わず、「から」を使う
※参照日記
http://
http://
5)「のみ」を使わず「だけ」を使う(ex.問題はこの点だけ)
●ある方へのメッセージ
以前、とあるコミュに文章の添削を依頼するトピが立った。トピ主はかなりまともな日本語を使う中国人だったが、雇用主から「大学出にふさわしい日本語を書くように」と言われたとのこと。このリクエストがよくわからない。要は「もう少し幼稚じゃない文章」を求められたのだろう。それは相当の無理難題だよ。
いつにもまして懇切丁寧なコメントを書いて投稿しようとしたら、トピが消えていた(泣)。コンタクトをとって事情を確認すると、添削を依頼した文章が業務週報なので、公開するのは差し障りがあるのでは、と指摘を受けたとのこと。そりゃそうだな。せっかくだからメッセージの形で発信した。下記はその一部。
================================
大前提として、「子供っぽい文章」でない文章とか、「大学卒業生らしい文章」が何を意図しているのかがわかりません。
・用語の問題(これは当方の個人的な感覚で、一般性はないかもしれません)
一般に、難しい言葉を使うと文章が難解になります。
「9 ○○さん」がおっしゃるように漢字語(?)を増やす方法もありますが、それだけ文章が難しい印象になります。たとえば、「~すること」や「~するもの」の「こと」や「もの」を漢字にする書き方もありますが、あまり一般的ではありません。
このほか、細かい点で文章を少し難しそうにする方法はあると思います。
結果を表す「に」を「と」にする(「~することにしました」を「~することとしました」にする)
起点などを表す「から」を「より」にする(「心から」を「心より」にする)
など、いろいろありますが、おすすめはできません。それだけ文章が古くさい印象になります。
・文体の問題
デアル体を使うかデス・マス体を使うかはケースバイケースですが、週報ならデアル体でいいと思います(混在するのはよくありません)。デス・マス体は、文章が子供っぽくなる傾向があります。いくつかの理由があって、デス・マス体で文章を書くのはむずかしいので、デアル体を使うほうがいいでしょう。
・一文の長さの問題
一般に、一文が短いと稚拙な文章に見えます。しかし、ムヤミに一文を長くすると文章がわかりにくくなります。
週報なら、一文の長さをできるだけ60字以内にするように心がけてはどうでしょうか。
================================
ありゃ。「いいでしょう」って使ってる……orz。
漢字をどこまで増やすかは微妙な問題。とりあえずhttp://
================================
「開始する」は、「開」と「始」という意味が似ている言葉をダブらせている動詞です。こういう動詞は、片方の言葉などを使って書きかえたほうが読みやすい印象になります。
・停止する→止める/やめる
・使用する→使う/用いる
・軽減する→軽くなる/減る
・提示する→示す
ただし、書きかえることによってニュアンスが大きくかわる場合もあるので、無理をしてまで徹底する必要はありません。
================================
こちらも箇条書きにしておこうか。4)は重複するので除く。
6)むやみに漢字を使わない
7)結果を表す「と」は使わず「に」を使う(ex.「~することとした」を「~することにした」にする)
※参照日記
【日本語アレコレ──「自然に」と「自然と」の違い1】
http://
http://
【追記】
8)「行う」はできるだけ使わない。
とくに過去形の「行(おこな)った」は「行(い)った」とまぎらわしい場合があるので、極力避ける。
ex.みんなで行った花火大会。
個人的には本則ではないことを承知で「行なう」と書くことにしている。
【追記2】
いくつも抜けている……orz。
9)重文のつなぎの「~おり」(正確にはなんと言えばいいかわからないorz)は使わず「~いて」を使う。
ex.この件はすでに解決していて、~
10)接続詞の「また」は極力つかわない
だいたい削除できる。助詞の「も」をうまく使う。
「それもまた一理ある」のような副詞は許容(個人的にはまず使わない)。
あと一般的な話は下記あたりかな。
【表記の話12──「ください」と「下さい」をめぐるホニャララ合戦】
http://
【表記の話13──補助動詞&ほぼ補助動詞(後項動詞)の表記】
http://
#日本語 #敬語 #誤用 #慣用句 #言葉 #問題 #間違い #二重敬語 #参考書