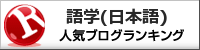質問の内容。
==============引用開始
「あける」について質問です。
ネットで調べてみると「時間をあける」の場合、
「時間を空ける」が正解のようですが異議ありです。
辞書がそうなっているから却下って言われそうですが
ある種の意味を込めて「開ける」もありではないか思っています。
(時間は閉じたりしないから開くことも無いって言われそうですが…)
例えば「席をあける」と言えば「席を空ける」であり、
決して「席を開ける」ではない。
これが辞書的な正解ですよね。
しかし席に人が居るかどうかでは無く、
席と席の間隔を広げる場合、つまりopen spaceを作る場合は
「席を開ける」と言ってもいいのではないでしょうか?
(spaceは空白だから「空ける」ですって言われそう…)
つまり「時間をあける」の場合も
その時間に空白を作るというよりも
結果的に空き時間が出来るという同じ事であっても
ニュアンス的に時間の間隔を広げるという意味で
「時間を開ける」を使い分けてもいいように思うのですが…
例えば「週末土曜までの約束だったのに時間が開いてしまいました。」とか。
やっぱり何が何でも「時間を空ける」が正解なんでしょうか?
==============引用終了
No.10
- 回答者: 1311tobi 回答日時:2015/07/12 12:45
結論だけを書くなら、まぎらわしいものはかな書きすることをおすすめします。
あえて漢字の使い分けにこだわる……ということでしょうか。
書き手が使い分けても、読む人には伝わらない可能性が高いような……。
『記者ハンドブック』によると、時間の場合は、どちらの場合も「空ける」になっています(ちょっとまぎれあり)。
個人的には疑問も感じますが、逆らう気はありません。
理由は……慣例の要素が大きく、理屈で考えても意味がない気がします。
たとえば、「足が速い(「早い」とする説もあります)」で「足早に」になる理由なんて、論理的には説明できません。
『大辞林』は〈歩いたり走ったりするのが速い。〉ことを「足が早い」にしています。
突然ですが問題です【日本語編8】──いろいろな書き方 誤った/謝った/過った 足が早い/足が速い
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-2566. …
詳しくは下記をご参照ください。
【表記の話19扱い】 ──あける あく 開ける/開く 空ける/空く 明ける/明く(?)
http://ameblo.jp/kuroracco/entry-12049475186.html
表記の使い分けに関しては、国語辞典はまったくアテにしていない。ただ、「あける/あく」に関しては相当詳しいので驚いている。今回のような微妙な話だと解決するのかしないのか。辞書の引用は末尾に。
やはりこういう場合は、プロの校正者が使う共同通信社の『記者ハンドブック』をひくのが正解だろう(朝日新聞社のものもほぼ同じ内容だった)。だってほぼそのための書籍なんだから。
意味はアッサリしたもので、もっぱら用例を並べている。表記の問題は理屈で考えてもどうにもならない場合が多いからだろう。
『記者ハンドブック』には以下のように出ている。
==============引用開始
あく・あける
空〔からになる〕空き缶・瓶(中略)、時間を空ける、席が空く、手空き、中身を空ける、間が空く
明〔明るくなる、内容が明らかになる、片が付く〕(略)
開〔ひらく〕明いた口がふさがらない(中略)、幕が開く、店を開ける
==============引用終了
質問の表記は下記の4つだろう。
1)時間をあける(あき時間をつくる)
2)時間をあける(インターバルをおく)
3)席をあける(席から離れる)
4)席をあける(席の間隔をあける)
1)は「時間を空ける」が一般的。↑参照。
3)も「席を空ける」が一般的。↑参照。
微妙なのは2)と4)。
2)に関しては、↑に「間が空く」という例がある。なんでルビをふらない。マかアイダかわからないじゃないか(泣)。
「間(マ)が空く」と読むのなら、3)も「時間が空く」になる気がする。
「間(アイダ)が空く」なら、4)が「席を空ける」になる気がする。
ただし、アイダと読ませるなら「間(アイダ)を空ける」にするのでは。
個人的には、「間(マ)が空く」→「時間が空く」と解釈したい。
そもそも、「時間をあける」はちょっと不自然に感じる。その場合は「インターバルをあける(これも「空」なんだろうか)」「時間をおく」とかでは。
「時間が空く」なら、「お前と会うのは5年ぶりか、今回はずいぶん時間が空いたな」などと使えそう。
個人的にはかな書きにするが、どうしても漢字にするなら「開」を使いたい。でも逆らうだけの根拠がない。さすがに『記者ハンドブック』に逆らう度胸なんてないよ(泣)。
4)は「開ける」だろう。ただ、「席を開ける」はちょっと不自然。「(椅子の)間隔を開ける」くらいでは。〈間隔を「からにする」でもはく間隔を「ひらく」〉だから。
でもそうなると、「しばらく会わないことにする」は、会う時間が空(あ)いて、会う間隔が開(あ)くのか?
個人的には、「あく/あける」のまぎらわしいものはかな書きにする。「あらわれる/あらわす」あたりはかな書きに異和感があるが「あく/あける」ならかな書きしても1字なのでさほど抵抗がない。
最難関「かわる/かえる」に関しては下記参照。
突然ですが問題です【日本語編37】──お金にはかえられない【解答?編】
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-1839. …
==============引用開始
表現を変えるか、別の言葉に言い換えるか、別の言葉と入れ替えるか、代わりの言葉を探すか、そんなの使い分けられるか。
朝日新聞は〈「替」か「換」か迷うときは「替」を使うこと〉にしているが、当方なら迷うときはひらがなで書く。キッパリ<( ̄- ̄)>
==============引用終了
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%81%91%E3%8 …
==============引用開始
デジタル大辞泉の解説
あ・ける【明ける/開ける/空ける】
[動カ下一][文]あ・く[カ下二]
1 (明ける)あるひと続きの時間・期間・状態が終わって、次の時間・期間・状態になる。
㋐朝になる。「夜が―・ける」⇔暮れる。
㋑年が改まる。「年が―・ける」⇔暮れる。
㋒ある期間が終わる。「喪が―・ける」「梅雨(つゆ)が―・ける」
2 (空ける)今までそこを占めていたもの、ふさいでいたものを、取り除いたり、なくしたりする。
㋐穴をつくる。「錐(きり)で穴を―・ける」
㋑使っていた場所から他へ移り、そのまま使わないでおく。あったものを出し、新たに入れないで、からの状態にする。「一〇時までに部屋を―・けてください」
㋒すいている空間や空白をつくる。間隔を置いたり、広げたりする。「間を―・ける」「一行―・けて書く」
㋓器の中のものを出したり、他の器や他の場所へ移したり、また、使い尽くしたりしてからにする。「水筒の水をバケツに―・ける」「大ジョッキを―・ける」
㋔ある時間を、拘束なしに使えるようにしておく。暇な時間をつくる。「その日は君のために―・けておく」
㋕留守にする。「旅行で家を―・ける」
3 (開ける)
㋐隔てや仕切りになっているものを取り除く。閉じていたものを開く。「窓を―・ける」「封を―・ける」「鍵(かぎ)を―・ける」「目を―・ける」⇔閉める。
㋑営業を始める。営業を行う。「午前一〇時に店を―・ける」⇔閉める。
[補説]2は「明ける」とも書く。
[用法]あける・ひらく――「窓を開ける(開く)」は相通じて用いられる。◇「開ける」は空間をふさいでいる仕切りや覆いなどを取り除く意で、「ふたを開ける」「かばんを開ける」のように用いる。◇「開く」は「包みを開く」「本を開く」のように、重ねて結び合わせたり、折り畳んだりしてあるものを広げて、中が見えるようにすること。◇「開く」はまた、「運命を開く」「心を開く」など物事をよい方向に進めていこうとする意で比喩的に用いられることもある。◇「口を開ける」「目を開ける」は、上下の唇やまぶたを離し広げることであるが、また「話しはじめる」「自覚する、知識を得る」の意にもなる。また、「道をあける」は邪魔になるものを除いて通れるようにすることだが、「道を開く」は新しく道を作ることであり、さらに「問題解決への道を開く」のようにも用いられる。
[下接句]穴をあける・風穴(かざあな)を開ける・手を空ける・泣く子も目を開(あ)け・年季が明ける・蓋(ふた)を開ける・水をあける・夜も日も明けない・埒(らち)を明ける
==============引用終了