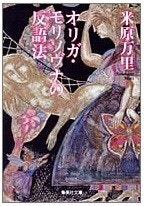こんなすごい小説があったんだって、最近読んだ中でも秀逸な作品。
著者の米原万里さん、テレビでも見たことあるかな、エリツイン来日の時に通訳をしたんだそうです。
彼女のプラハにいた時の体験をもとにしたフィクション
概略は、amazonから借りてきました。
ロシア語通訳の第一人者としても、またエッセイストとしても活躍している米原万里がはじめて書いた長編小説である。第13回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞した。
1960年代のチェコ、プラハ。主人公で日本人留学生の小学生・弘世志摩が通うソビエト学校の舞踊教師オリガ・モリソヴナは、その卓越した舞踊技術だけでなく、なによりも歯に衣着せない鋭い舌鋒で名物教師として知られていた。大袈裟に誉めるのは罵倒の裏返しであり、けなすのは誉め言葉の代わりだった。その「反語法」と呼ばれる独特の言葉遣いで彼女は学校内で人気者だった。そんなオリガを志摩はいつも慕っていたが、やがて彼女の過去には深い謎が秘められているらしいと気づく。そして彼女と親しいフランス語教師、彼女たちを「お母さん」と呼ぶ転校生ジーナの存在もいわくありげだった。
物語では、大人になった志摩が1992年ソ連崩壊直後のモスクワで、少女時代からずっと抱いていたそれらの疑問を解くべく、かつての同級生や関係者に会いながら、ついに真相にたどり着くまでがミステリータッチで描かれている。話が進むにつれて明らかにされていくのは、ひとりの天才ダンサーの数奇な運命だけではない。ソ連という国家の為政者たちの奇妙で残酷な人間性、そして彼らによって形作られたこれまた奇妙で残酷なソ連現代史、そしてその歴史の影で犠牲となった民衆の悲劇などが次々に明らかにされていく。
読んでいて、次々に明らかになる事実。ところどころ涙した僕です。
人が人として生き抜くくする時代は嫌ですね
気が付いてみると、最近、東欧を舞台とした物語を読むことが多い。
アゴタ・クリスオフ「悪童日記」「ふたりの証拠」「第三の嘘」
ミラン・クランデ「存在の耐えられない軽さ」
須賀しのぶ「革命前夜」
米原万里「オリガ・モリソヴナの反語法」