Dave Brubeck『Aurex Jazz Festival '82』
日本で1982年に開催された「Aurex Jazz Festiva」での実況録音盤です。出演者は、デイヴ・ブルベック・カルテットにジャコ・パストリアス・ビッグ・バンド、ウディ・ハーマン・オーケストラというものだったらしい(ライナーノーツ氏参照)。ここの収められている曲も、日本各地を回った各会場の実況録音で、以下の5曲がそれぞれの都市での演奏です。
1 Someday My Prince Will Come ・・・東京
2 You Don't Know What Love Is ・・・大阪
3 Big Band Basie ・・・・・・・・・・ 横浜
4 Take Five ・・・・・・・・・・・・・大阪
5 St. Louis Blues ・・・・・・・・・・大阪
曲名を見てもわかるように、スタンダードもしくは十八番の曲を演奏し、よく演奏会の「祭り」という主旨を理解したというか、ここまで名が売れれば、特に奇をてらったことをしなくても十分に観客を喜ばすことができたということなのだろうと思います。
ライブと言うこともあり、またさほど革新的なことを行っているわけでもなく、ちょっと緊張感に欠けた、よく言えば、楽しい演奏です。特に、3曲目「Big Band Basie」は、曲名のとおりにカウント・ベイシーにデイヴ・ブルーベックが捧げた曲で、ベイシー調の弾むような小粋なピアノ演奏を聴かせてくれています。お客さんもずっと手拍子をしていて、会場の雰囲気がよく伝わってくる楽しい演奏です。
あまり、ジャズがどうのこうという理屈を考えずに、素直に楽しむ。それに尽きる演奏です。しかし、モンクは慕われても、彼の演奏スタイルを真似ようとするピアニストはあまり知りませんが、ベイシーは慕われもし、なおかつこのように演奏スタイルを実際に演奏してオマージュすることが結構多いような気がします。それだけ、多くのピアニストにとって、カウント・ベイシーは愛すべき偉大な先駆者だったのでしょうかね。
一方、モンクは、近寄りがたい、どちらかというと「愛すべき」ではなく、畏敬すべき存在ということなのでしょうか。
最後に、デイヴ・ブルーベックの十八番の「Take Five」は、やはり聴き所は、サックスの演奏なのでしょうね。ノリの良いメロディーの変拍子に乗って、如何にアドリブを展開するのか、ポール・デスモンドの曲なので、当然と言えば当然なのでしょうが、彼が如何にこういう曲を演奏したかったのか、わかります。それだけに、テナーのマイケル・ペディスンはやりずらさもあり、反面やりがいもあるということなのでしょうが、ここでの演奏は無難でしょうか。デスモンドライクではないですが、デスモンドの枠を抜けてはいない印象です。結構、各演奏者のソロの機会もあり、メリハリのある聴き所のある演奏です。

にほんブログ村

1 Someday My Prince Will Come ・・・東京
2 You Don't Know What Love Is ・・・大阪
3 Big Band Basie ・・・・・・・・・・ 横浜
4 Take Five ・・・・・・・・・・・・・大阪
5 St. Louis Blues ・・・・・・・・・・大阪
曲名を見てもわかるように、スタンダードもしくは十八番の曲を演奏し、よく演奏会の「祭り」という主旨を理解したというか、ここまで名が売れれば、特に奇をてらったことをしなくても十分に観客を喜ばすことができたということなのだろうと思います。
ライブと言うこともあり、またさほど革新的なことを行っているわけでもなく、ちょっと緊張感に欠けた、よく言えば、楽しい演奏です。特に、3曲目「Big Band Basie」は、曲名のとおりにカウント・ベイシーにデイヴ・ブルーベックが捧げた曲で、ベイシー調の弾むような小粋なピアノ演奏を聴かせてくれています。お客さんもずっと手拍子をしていて、会場の雰囲気がよく伝わってくる楽しい演奏です。
あまり、ジャズがどうのこうという理屈を考えずに、素直に楽しむ。それに尽きる演奏です。しかし、モンクは慕われても、彼の演奏スタイルを真似ようとするピアニストはあまり知りませんが、ベイシーは慕われもし、なおかつこのように演奏スタイルを実際に演奏してオマージュすることが結構多いような気がします。それだけ、多くのピアニストにとって、カウント・ベイシーは愛すべき偉大な先駆者だったのでしょうかね。
一方、モンクは、近寄りがたい、どちらかというと「愛すべき」ではなく、畏敬すべき存在ということなのでしょうか。
最後に、デイヴ・ブルーベックの十八番の「Take Five」は、やはり聴き所は、サックスの演奏なのでしょうね。ノリの良いメロディーの変拍子に乗って、如何にアドリブを展開するのか、ポール・デスモンドの曲なので、当然と言えば当然なのでしょうが、彼が如何にこういう曲を演奏したかったのか、わかります。それだけに、テナーのマイケル・ペディスンはやりずらさもあり、反面やりがいもあるということなのでしょうが、ここでの演奏は無難でしょうか。デスモンドライクではないですが、デスモンドの枠を抜けてはいない印象です。結構、各演奏者のソロの機会もあり、メリハリのある聴き所のある演奏です。
にほんブログ村

ながら聴き(2014年8月23日早朝)
ときどき、インターネットラジオの「Piano Trios」チャンネルで印象に残った曲を紹介します。どれも、1曲だけ聴いただけの感覚的な感想です。
8月23日午前5時10分頃から
1 Masha Stepina - Bylina
ロシア出身で、オランダで活躍しているピアニストMasha Stepina のリーダー作です。メロディー感覚が、淡い色をしている印象です。耽美的なタッチと音の響きを紡ぎ出す、そんな印象。買って聴いて面白そうです。
Place We’re Longing for/CD Baby

¥1,889
Amazon.co.jp
2 Jay McShann - A Night In Tunisia
ジェイ・マクシャンは、1916年~2006年で生涯を終えた人です。ピアノは独学、ジェームズ. P .ジョンソンやアール・ハインズの影響を受けた人のようです。そして、最大のジャズへの功績は、自信の演奏ではなく、チャーリー・パーカーの才能を最初に認めた人。パーカーのレコードデビューはこのジェ・マクシャンの作品でだそうです。この辺りの詳しいことはここで読んでください。とても聴きやすく、親しみのもてる演奏です。
Swingmatism/Sackville Records

¥1,889
Amazon.co.jp
3 Herbie Hancock - La maison Gor
ハンコックとしては、ちょっと歯切れの悪い演奏ですね。ベースの音がちょっと大きすぎかな。ロン・カーターとトニー・ウイリアムスのバランスの悪さが気になる演奏です。こうなんていうか、推進力のない、要するに技巧的にはうまいのでしょうが、肝心のスイングをしていない。
Trio With Ron Carter + Tony Williams/WOUNDED BIRD

¥1,556
Amazon.co.jp
4 Travis Wesley - Slip Slidin' Away
懐かしい響きが聞こえてきそうな演奏です。シンプルです。メンバーは、Travis Wesley(P)、Matt Hughes(b)、Tom Marko(ds)。イリノイ出身のピアニストのようです。e.s.t.的なアプローチにも挑戦している作品を出しているようです。ここでは、素朴な演奏を聴かせてくれていますが、引き出しが多い、まだ自分探しの段階なのでしょうか。
Natural Diversion/CD Baby

¥1,778
Amazon.co.jp
5 John Bunch - Pannonica
どこぞのハウスピアニストのような演奏です。ディナータイムやなナイトラウンジでのおしゃれなピアノ演奏です。気品がありますね。ちょっと、お茶目もあり、楽しませてくれそうです。1921年アメリカ生まれ2010年にお亡くなりになっています。ズート・シムズとかともやっています。アメリカでの草の根のクラブミュージシャン(そんな言葉があれば)って感じですね。リラックスして聴くにはもってこいでしょうか。
Special Alliance/Arbors Records

¥1,333
Amazon.co.jp
6 Lenny Marcus - Moonlight Sonata
ノリの良い演奏です。クラシカルなメロディーを軽快に、そして厳かに弾いています。どこか、ラフェスタみたいな演奏です。ヴァージニア州出身のピアニストだそうです。名前は、レニー・マーカスです。自主制作でアルバムを20枚以上出しているとのこと。引き出しが多そうです。これ1曲で、どうのこうのと言えないですね。
Jazz of Beethoven/CD Baby

¥2,223
Amazon.co.jp
7 Michel Petrucciani - Days of Wine and Roses
こやって、ずっとピアノトリオを聴いて、ペトルチアーニの演奏が挟まると、情感の表し方が半端じゃないですね。奥深いというか、表現が素晴らしいです。やはり、人を引きつけるミュージシャンは、一皮違いますね。
Michel Petrucciani/Sunny Side
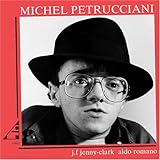
¥1,889
Amazon.co.jp
8 Jimmy Rowles - Moon of Manakoora
ジミー・ロウズは、結構日本でも名が売れているピアニストではないかと思うのですが、地味ですが、玄人肌の堅実なピアノを弾く方という印象を持っています。でも、kumacはあまり聴いたことがないかもしれません。なんで、名前の記憶があるのかな?よくわかりません。5番目に紹介した John Bunch みたいな感じなのでしょうね。
Our Delight/Vsop Records

¥1,889
Amazon.co.jp
9 Noah Baerman - Bye Bye Backhand
ジャケットからすると結構アグレッシブな演奏をやりそうな気がしますが、これはおとなしめの正当な演奏です。その分、おもしろみに欠けます。1973年コネチカット州生まれ、ケニー・バロンに師事したという方です。ここのレビューを読むと、引き出しが多そうです。
I’m Beginning to See the Light/Lemel

¥価格不明
Amazon.co.jp
10 Zoe Rahman - J'Berg
癖のある、深遠な音のピアノを弾く方ですね。ちょっと、とらえどころがない感じ。エモーショナルな叩きつけた方をしたと思えば、ズレを起こすし、なにを演奏に狙っているのか、正直、イマイチわからない。イメージを結べない方です。だからこそ、面白いといえます。イギリス、ロンドンの女流ピアニストとのこと。
J’Berg/Manushi Records

¥価格不明
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Keith Jarrett『Vienna Concert』
「荘厳」という言葉がまさに当てはまる演奏である。冒頭の「Part Ⅰ」の出だし。キース・ジャレットのソロは、その場の精神状態、場から感じる雰囲気などで、最初の一音目が決まるのだろうか?そうだとしたら、次の二音目は、どのように導かれ、次々と鳴らされる音の羅列は、どのように起承転結の曲として成立してゆくのだろうか。
自己陶酔と言ってしまえば、それまでなのだが、それを可能にして、支えるのはその場を同等の立場として共有している一人ひとりの観客ということになる。その感謝の念、それをしっかりと音に込める、その意識なしには、こんな作業の繰り返しを続けることは到底できないのではないか。突き詰めれば、何者かと魂を通わすということなのだろう。
kumac はキース・ジャレットのCDとなった即興のソロコンサートは、ほとんど繰り返しては聴かない。ケルンコンサートも、二度しか聴いたことは無い。これからも、再度聴こうとは思わない。それだけの一回限りの絶対性を大事にしたいと思っている。
だから、結局、あまりキース・ジャレットの即興のソロコンサートは、聴いていない。ライブは、一度だけ。持っているCDは、最初の『ソロコンサート』と『Radiance』のみで、『ソロコンサート』はレコードなので、再生装置はもう家にない。
ということで、どのコンサートがどうのこうのという、善し悪しの話には絶対にならない。最低限、私の中では。

にほんブログ村
ウィーン・コンサート/ユニバーサル ミュージック

¥1,944
Amazon.co.jp
自己陶酔と言ってしまえば、それまでなのだが、それを可能にして、支えるのはその場を同等の立場として共有している一人ひとりの観客ということになる。その感謝の念、それをしっかりと音に込める、その意識なしには、こんな作業の繰り返しを続けることは到底できないのではないか。突き詰めれば、何者かと魂を通わすということなのだろう。
kumac はキース・ジャレットのCDとなった即興のソロコンサートは、ほとんど繰り返しては聴かない。ケルンコンサートも、二度しか聴いたことは無い。これからも、再度聴こうとは思わない。それだけの一回限りの絶対性を大事にしたいと思っている。
だから、結局、あまりキース・ジャレットの即興のソロコンサートは、聴いていない。ライブは、一度だけ。持っているCDは、最初の『ソロコンサート』と『Radiance』のみで、『ソロコンサート』はレコードなので、再生装置はもう家にない。
ということで、どのコンサートがどうのこうのという、善し悪しの話には絶対にならない。最低限、私の中では。
にほんブログ村
ウィーン・コンサート/ユニバーサル ミュージック

¥1,944
Amazon.co.jp
Chick Corea & Gary Burton『In Concert , Zurich』
昨日も、先週もそうですがこのところ ECM レーベルの作品が続いています。ヨーロッパの古典音楽専門レーベルとして出発したマンフレッド・アイヒャーが設立した ECM レーベルは、ジャズの大きな歴史のうねりの中における重要性はさておき、kumac のジャズとの関わりにおいては、最も大きな影響を与えてくれたレーベルです。それは、ヴァーヴ、ブルーノート、プレステッジ、リバーサイドといったジャズが発展する上での直系の系譜としての王道のレーベルと、kumac のジャズ歴が現在進行形で重なっていないことが大きな理由です。
しかし、ECM レーベルはそのジャズとの関わりのほぼ始まりから、kumac の軌道とほぼ一致して成長しています。故に、マンフレッド・アイヒャーの向く視線の方向が、kumac のジャズ遍歴に大きく影響を及ぼしていると言えます。それは、追随ということではなく、反面教師的意味合いも含めてです。ある時期は、ECM レーベルの作品に嫌悪感を覚えたことは事実ですが、結局、なんやかんや言っても、ジャズを聴かなくなった期間、アルボ・ペルトを ECM の作品とはあまり意識せずに集中して聴いていたし、今、現在はニック・ベルチェが一番のお気に入りになっている事実は否定できないものです。
キース・ジャレットの『フェイシング・ユー』しかり、ポール・ブレイの『オープン・トゥ・ラブ』もしかし、チック・コリアの『リターン・トゥ・フォエバー』などの音の刷り込みが kumac の始原的触覚にあり、ついそっちの方向に触手が伸びるのはどうしようもないことであります。
ECM レーベルのジャズにおける最大の功労は、ジャズという表現形式から俗性を切り離し、鑑賞芸術に高めたことではないかと思っています。かなり、怪しい書きっぷりですが、誤解を恐れずに言わせていただければ、それに尽きるのではないかと思っています。
話が逸れましたが、チック・コリアは結構ピアノの二重奏が好きなようですね。例えば、イタリアのステファン・ボラーニとの作品、上原ひろみとの作品などが頭にすぐに浮かびます。ゲーリー・バートンも同じ鍵盤楽器です。元々相性が良いのでしょうね。テクニックも凄いのでしょうが、音の駆け引きというか、共演者との音のやりとりに対する自分と他人の音の違いに対する垣根が低いのかもしれないと思ったこの演奏を聴いていて考えていました。つまり、相手の音をしっかりと聴くのは当然なのですが、その音も自分の音にしてしまうというアプローチの仕方を持ている。だから、kumac の耳が悪いだけなのかもしれませんが、ステファン・ボラーニとのデュオを聴くと、どちらの演奏がどっちか全くわからなくなる。自分を際立たせようとする意識が希薄です。共演なので、両者で一つの音の世界を作り上げるのは当然の作業になるのでしょうが、そこに互いの個性がぶつかり合って、そこで起きる偶然性やコントラストやアクシデントを楽しむということではなく、あくまで渾然一体となって一つの音の世界を作るということに集中する。そんな姿勢を感じます。
ということで、ライブコンサートという粗さはありますが、楽しく聴ける娯楽調の作品です。

にほんブログ村
チック・コリア&ゲイリー・バートン・イン・コンサート/ユニバーサル ミュージック

¥1,728
Amazon.co.jp
しかし、ECM レーベルはそのジャズとの関わりのほぼ始まりから、kumac の軌道とほぼ一致して成長しています。故に、マンフレッド・アイヒャーの向く視線の方向が、kumac のジャズ遍歴に大きく影響を及ぼしていると言えます。それは、追随ということではなく、反面教師的意味合いも含めてです。ある時期は、ECM レーベルの作品に嫌悪感を覚えたことは事実ですが、結局、なんやかんや言っても、ジャズを聴かなくなった期間、アルボ・ペルトを ECM の作品とはあまり意識せずに集中して聴いていたし、今、現在はニック・ベルチェが一番のお気に入りになっている事実は否定できないものです。
キース・ジャレットの『フェイシング・ユー』しかり、ポール・ブレイの『オープン・トゥ・ラブ』もしかし、チック・コリアの『リターン・トゥ・フォエバー』などの音の刷り込みが kumac の始原的触覚にあり、ついそっちの方向に触手が伸びるのはどうしようもないことであります。
ECM レーベルのジャズにおける最大の功労は、ジャズという表現形式から俗性を切り離し、鑑賞芸術に高めたことではないかと思っています。かなり、怪しい書きっぷりですが、誤解を恐れずに言わせていただければ、それに尽きるのではないかと思っています。
話が逸れましたが、チック・コリアは結構ピアノの二重奏が好きなようですね。例えば、イタリアのステファン・ボラーニとの作品、上原ひろみとの作品などが頭にすぐに浮かびます。ゲーリー・バートンも同じ鍵盤楽器です。元々相性が良いのでしょうね。テクニックも凄いのでしょうが、音の駆け引きというか、共演者との音のやりとりに対する自分と他人の音の違いに対する垣根が低いのかもしれないと思ったこの演奏を聴いていて考えていました。つまり、相手の音をしっかりと聴くのは当然なのですが、その音も自分の音にしてしまうというアプローチの仕方を持ている。だから、kumac の耳が悪いだけなのかもしれませんが、ステファン・ボラーニとのデュオを聴くと、どちらの演奏がどっちか全くわからなくなる。自分を際立たせようとする意識が希薄です。共演なので、両者で一つの音の世界を作り上げるのは当然の作業になるのでしょうが、そこに互いの個性がぶつかり合って、そこで起きる偶然性やコントラストやアクシデントを楽しむということではなく、あくまで渾然一体となって一つの音の世界を作るということに集中する。そんな姿勢を感じます。
ということで、ライブコンサートという粗さはありますが、楽しく聴ける娯楽調の作品です。
にほんブログ村
チック・コリア&ゲイリー・バートン・イン・コンサート/ユニバーサル ミュージック

¥1,728
Amazon.co.jp
Keith Jarrett『Standards Live』
キース・ジャレットのスタンダードトリオは気まぐれに聴いているだけで、系統立てては聴いていない。なので、その演奏がどういう位置づけでとらえて良いのかは、全くわからないし、果たしてこのトリオでどこが良い演奏なのか、どこが特異な演奏なのか、区別も判断も付かない。作品として世に出るからには、海賊版でも無い限り、それなりにキース・ジャレットが良いと判断したものであるから、何かしら納得できる部分、敢えて世に出す意味があるのだろうが、それが何か、どこにあるのか、全くわからない。
スタンダード曲を中心に演奏するトリオだということを考えると、これまで演奏してCDに収めなかった曲を出すということだけでも意味はありそうだし。かなり自由度の高い演奏をするトリオなので、同じ曲にしても別な演奏、特にライブの演奏での違いを聴かせるのも意味は大きいと思うのですが。
前回のこのブログの記事では、このスタンダードトリオの結成のきっかけとなったゲーリー・ピーコックの ECM での作品を取り上げたが、それと今日の作品を比較すると、ゲーリー・ピーコックはおおらかな、つまりリラックスした弾き方をしている。ジャック・ディジョネットは手数が多くなって、つまり遠慮なく自由に叩いている。最初の切っ掛けとなった作品よりも三人がより明確に、そしてより自由に自己主張を行っていることは間違いない。そうなると、エバンスのトリオと比較したくなるのが人情という物なのですが、エバンス~ラファロ~モチアンのトリオと決定的に違うのは、演奏を一つのスタイルとしてまとめ上げようとしないことがスタンダードトリオであり、その点が決定的に両者では違うことなのかなと思ってしまう。
だから、このスタンダードトリオは長年活動を続けられたのだと思う。方や、エバンスはラファロの死を持って意思にかかわらず強制的に終わりを遂げたということがあったにせよ、エバンスのいわゆる黄金のトリオはスタンダードトリオほどまでに長続きはしなかったと思う。仮に、ゲーリー・ピーコックが健康的に問題なければ、スタンダードトリオはもっと続いたと思うし、それぞれの個性がぶつかるという演奏スタイルは全く変わらなかったと思う。
一曲、一曲感想を書くことに、どれほどの意味があるのか、全くもって意味はないと思わずには居られない。どの演奏も素晴らしの一言ですね。だからといって、彼らの演奏をすべて聴きたいとは思わないところがジャズという音楽の面白いところでもあると感じるのです。

にほんブログ村
星影のステラ/ユニバーサル ミュージック
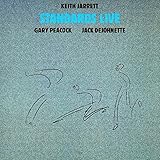
¥1,080
Amazon.co.jp
スタンダード曲を中心に演奏するトリオだということを考えると、これまで演奏してCDに収めなかった曲を出すということだけでも意味はありそうだし。かなり自由度の高い演奏をするトリオなので、同じ曲にしても別な演奏、特にライブの演奏での違いを聴かせるのも意味は大きいと思うのですが。
前回のこのブログの記事では、このスタンダードトリオの結成のきっかけとなったゲーリー・ピーコックの ECM での作品を取り上げたが、それと今日の作品を比較すると、ゲーリー・ピーコックはおおらかな、つまりリラックスした弾き方をしている。ジャック・ディジョネットは手数が多くなって、つまり遠慮なく自由に叩いている。最初の切っ掛けとなった作品よりも三人がより明確に、そしてより自由に自己主張を行っていることは間違いない。そうなると、エバンスのトリオと比較したくなるのが人情という物なのですが、エバンス~ラファロ~モチアンのトリオと決定的に違うのは、演奏を一つのスタイルとしてまとめ上げようとしないことがスタンダードトリオであり、その点が決定的に両者では違うことなのかなと思ってしまう。
だから、このスタンダードトリオは長年活動を続けられたのだと思う。方や、エバンスはラファロの死を持って意思にかかわらず強制的に終わりを遂げたということがあったにせよ、エバンスのいわゆる黄金のトリオはスタンダードトリオほどまでに長続きはしなかったと思う。仮に、ゲーリー・ピーコックが健康的に問題なければ、スタンダードトリオはもっと続いたと思うし、それぞれの個性がぶつかるという演奏スタイルは全く変わらなかったと思う。
一曲、一曲感想を書くことに、どれほどの意味があるのか、全くもって意味はないと思わずには居られない。どの演奏も素晴らしの一言ですね。だからといって、彼らの演奏をすべて聴きたいとは思わないところがジャズという音楽の面白いところでもあると感じるのです。
にほんブログ村
星影のステラ/ユニバーサル ミュージック
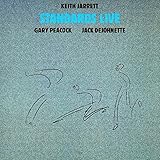
¥1,080
Amazon.co.jp
Gery Peacock『Tales Of Another』
キース・ジャレットのスタンダードトリオ結成のきっかけとなったゲーリー・ピーコックの ECM の作品です。iTunesに入れると、CDのデータのアーティストがキース・ジャレットになってしまうのはご愛敬でしょうが、ゲーリー・ピーコックの評価が、このキースのスタンダードトリオだけに終始するのはいかがな物かと思ったりもします。
ゲーリー・ピーコックは、一時期、京都に住んでおり、その頃は演奏活動は控えめで、精神的な安住を求めていたようです。kumac がジャズにのめり込み始めた高校生の頃はすでにジャズシーンの第一線からは半ば引退しており、彼のジャズへの復活となったポール・ブレイ・トリオでの活動は、仙台のヤマハの音楽スタジオでライブを聴きました。ポール・ブレイ目当てでしたが、メンバーを知って、ゲーリー・ピーコックが音楽活動を再開したのだと、思った記憶があります。
スタンダードトリオでは至極まっとうなベースを弾いているゲーリー・ピーコックですが、この作品ではまだ精神性の強い、音の空白を意識した演奏を行っています。例えば2曲目「Tone Field」は、フリーフォームの演奏です。メロディアンスな音は一切排除されています。その代わり、意識の集中のみで支えている音を空間の関係性だけではじき出しています。結構、こういう精神性の高まりだけでの演奏は、キース・ジャレットも得意とする分野だけに、この二人はかなり意気投合をしたのではないかと想像ができます。
たぶん、こういう演奏は二人ともこれまで嫌と言うほど繰り返して演奏しているはずで、その意味からはただこういうスタイルを延々と続けても、楽しくはないだろうなということも想像に難くないです。3曲目「Major Major」を聴いていると、そういう雰囲気を強く感じます。自由に気持ちよく歌うという感覚です。決まり事の中ではなく、あくまで自由にです。だから、一つの曲がどう発展してゆくのか演奏してみないとわからないというおもしろさがあるのではないでしょうか。
それを突き詰めれば、聞き慣れて、口ずさむ見たくなるした下のあるスタンダードの曲を、三者で自由に演奏という枠に収まらない自由な行為の中で、即興で作り上げることになるのかなと思います。
決して聴きやすい作品ではないと思いますが、彼らの原点を押さえておく意味では、どこかでいつか聴いておくことが良いのかもしれません。

にほんブログ村
テイルズ・オブ・アナザー/ユニバーサル ミュージック クラシック

¥1,851
Amazon.co.jp
ゲーリー・ピーコックは、一時期、京都に住んでおり、その頃は演奏活動は控えめで、精神的な安住を求めていたようです。kumac がジャズにのめり込み始めた高校生の頃はすでにジャズシーンの第一線からは半ば引退しており、彼のジャズへの復活となったポール・ブレイ・トリオでの活動は、仙台のヤマハの音楽スタジオでライブを聴きました。ポール・ブレイ目当てでしたが、メンバーを知って、ゲーリー・ピーコックが音楽活動を再開したのだと、思った記憶があります。
スタンダードトリオでは至極まっとうなベースを弾いているゲーリー・ピーコックですが、この作品ではまだ精神性の強い、音の空白を意識した演奏を行っています。例えば2曲目「Tone Field」は、フリーフォームの演奏です。メロディアンスな音は一切排除されています。その代わり、意識の集中のみで支えている音を空間の関係性だけではじき出しています。結構、こういう精神性の高まりだけでの演奏は、キース・ジャレットも得意とする分野だけに、この二人はかなり意気投合をしたのではないかと想像ができます。
たぶん、こういう演奏は二人ともこれまで嫌と言うほど繰り返して演奏しているはずで、その意味からはただこういうスタイルを延々と続けても、楽しくはないだろうなということも想像に難くないです。3曲目「Major Major」を聴いていると、そういう雰囲気を強く感じます。自由に気持ちよく歌うという感覚です。決まり事の中ではなく、あくまで自由にです。だから、一つの曲がどう発展してゆくのか演奏してみないとわからないというおもしろさがあるのではないでしょうか。
それを突き詰めれば、聞き慣れて、口ずさむ見たくなるした下のあるスタンダードの曲を、三者で自由に演奏という枠に収まらない自由な行為の中で、即興で作り上げることになるのかなと思います。
決して聴きやすい作品ではないと思いますが、彼らの原点を押さえておく意味では、どこかでいつか聴いておくことが良いのかもしれません。
にほんブログ村
テイルズ・オブ・アナザー/ユニバーサル ミュージック クラシック

¥1,851
Amazon.co.jp
Grachan Moncur III『Some Other Stuff』
グレシャン・モンカー3世は、その王様のような奇妙な表記から、名前だけは知っていましたが、どんな演奏をするのかは聴いたことがないので、知りませんでした。聴かなかった理由は、あまり良い評判を聞いたことがないからです。
どんなミュージシャンも、レコードデビューをして日本でも作品が発売される方は、誰かしか褒めているわけで、そういう文章を読めば、聴きたくなる訳で、そうならなかったのはどうしてか?なのですが、1960年代中期以降のいわゆるフリージャズの嵐の中で、アイラーやドルフィーのような名盤が、これといってなかったからなのかなとも思ったりするし、この時期の新感覚派なり、フリージャズは大方、似たり寄ったりで、あまり食指が動くようなものはなかった。どちらかといえば、ロックの影響を受けた演奏にシフトしてゆく感じだったのでしょうね。
というわけで、この1964年7月6日録音のグレシャン・モンカー3世の作品『Some Other Stuff』ですが、まずもってメンバーが凄いです。ウェイン・ショーターの(ts)、ハービー・ハンコックの(p)、セシル・マクビーの(b)、トニー・ウイリアムスの(ds)です。この年代では、いずれも新進気鋭で、セシル・マクビーを除けば、かなり注目を浴びていたミュージシャンです。
そのメンバーで、完全なフリーフォームのジャズを演奏しています。冒頭「Gnostic」は、とにかく緊張感のある演奏です。それは、聴く側にも求められます。イメージできる音が続かない状況が、行き止まりが見えない状況で延々と引っ張られてゆく感覚です。2曲目「Thandiwa」は、簡単なリフのようなミデアムテンポのリズミカルなテーマがあり、次に各人のソロに移ります。ウエイン・ショーターは、ロングソロが kumac は好きです。自分でエモーションを作ってゆくんですね。その過程を聴いていると面白いミュージシャンです。ハービー・ハンコックもとてもキレのある演奏をしています。こういうメロデアィスでないけど鋭角なピアノ演奏が好きですね。トニー・ウイリアムスのブラッシュワークも面白いです。
一曲一曲丁寧に、集中して聴いてゆくと、とても楽しい演奏です。たまには、こういう硬派なフリージャズもいいですね。

にほんブログ村
どんなミュージシャンも、レコードデビューをして日本でも作品が発売される方は、誰かしか褒めているわけで、そういう文章を読めば、聴きたくなる訳で、そうならなかったのはどうしてか?なのですが、1960年代中期以降のいわゆるフリージャズの嵐の中で、アイラーやドルフィーのような名盤が、これといってなかったからなのかなとも思ったりするし、この時期の新感覚派なり、フリージャズは大方、似たり寄ったりで、あまり食指が動くようなものはなかった。どちらかといえば、ロックの影響を受けた演奏にシフトしてゆく感じだったのでしょうね。
というわけで、この1964年7月6日録音のグレシャン・モンカー3世の作品『Some Other Stuff』ですが、まずもってメンバーが凄いです。ウェイン・ショーターの(ts)、ハービー・ハンコックの(p)、セシル・マクビーの(b)、トニー・ウイリアムスの(ds)です。この年代では、いずれも新進気鋭で、セシル・マクビーを除けば、かなり注目を浴びていたミュージシャンです。
そのメンバーで、完全なフリーフォームのジャズを演奏しています。冒頭「Gnostic」は、とにかく緊張感のある演奏です。それは、聴く側にも求められます。イメージできる音が続かない状況が、行き止まりが見えない状況で延々と引っ張られてゆく感覚です。2曲目「Thandiwa」は、簡単なリフのようなミデアムテンポのリズミカルなテーマがあり、次に各人のソロに移ります。ウエイン・ショーターは、ロングソロが kumac は好きです。自分でエモーションを作ってゆくんですね。その過程を聴いていると面白いミュージシャンです。ハービー・ハンコックもとてもキレのある演奏をしています。こういうメロデアィスでないけど鋭角なピアノ演奏が好きですね。トニー・ウイリアムスのブラッシュワークも面白いです。
一曲一曲丁寧に、集中して聴いてゆくと、とても楽しい演奏です。たまには、こういう硬派なフリージャズもいいですね。
にほんブログ村
Pat Martino『Stone Blue』
1998年2月22日に録音されたギター奏者、パット・マルティーノの作品です。パット・マルティーノは、あまり聴いたことがないです。前回、Date FM のジャズストラッチンで聴いて、ちょっと興味を持ちました。この作品は、病気でしばらく演奏活動から遠ざかり、復帰後にそれまでのスタイルを捨てて、フィージョン系の音楽を演奏し始めた時期、らしいです。その前も、後も知らないkumacにとてっては、さしたる感想に影響を与える情報ではないです。
あまり自己主張をしない音だと思います。さらりと流している、という感じでしょうか。でも、ちゃんと壺は押さえていますね。ギターの蕩けるような音色を上手に活かしている演奏です。アーバンな雰囲気を持っています。テナーのエリック・アレキサンダーが、以外と無機質な演奏をするのが、とても興味深いです。この二人、相性がいいですね。フュージョンと言うよりも、都会のすえた臭いがすてくるようで、嫌み(悪臭)でないところが、かっこいいです。こういう風にさりげなく、一陣の風のように先に進んでゆく音の切れの良さは、好きです。
3曲目「With All The People」なんかは、やりたいことを思う存分、弾いた印象があり、とても雰囲気のある楽しい演奏です。
もっと野性味を帯びた音を出すのかなと思いましたが、この作品ではそれは垣間見られないです。一貫して、アーバンなステディな小気味よい音の連続技を聴かせてくれています。いいですね。エリック・アレキサンダーも好演です。乗りの良い、激しさもあり、飽きさせない作品に仕上がっています。
現代なら、こういう音楽は作らないだろうなと思いますが、じっくりと聞けば、味わいのあるソロ演奏が心に響いてきます。
Stone Blue/Blue Note Records

¥4,340
Amazon.co.jp

にほんブログ村
あまり自己主張をしない音だと思います。さらりと流している、という感じでしょうか。でも、ちゃんと壺は押さえていますね。ギターの蕩けるような音色を上手に活かしている演奏です。アーバンな雰囲気を持っています。テナーのエリック・アレキサンダーが、以外と無機質な演奏をするのが、とても興味深いです。この二人、相性がいいですね。フュージョンと言うよりも、都会のすえた臭いがすてくるようで、嫌み(悪臭)でないところが、かっこいいです。こういう風にさりげなく、一陣の風のように先に進んでゆく音の切れの良さは、好きです。
3曲目「With All The People」なんかは、やりたいことを思う存分、弾いた印象があり、とても雰囲気のある楽しい演奏です。
もっと野性味を帯びた音を出すのかなと思いましたが、この作品ではそれは垣間見られないです。一貫して、アーバンなステディな小気味よい音の連続技を聴かせてくれています。いいですね。エリック・アレキサンダーも好演です。乗りの良い、激しさもあり、飽きさせない作品に仕上がっています。
現代なら、こういう音楽は作らないだろうなと思いますが、じっくりと聞けば、味わいのあるソロ演奏が心に響いてきます。
Stone Blue/Blue Note Records

¥4,340
Amazon.co.jp
にほんブログ村
Date FM Jazz Struttin 2014.07.12
【1曲目】キャノンボール・アダレイ「アラバマに星墜ちて」
振り返ってみると、キャノンボール・アダレイはあまり聴いていないです。こう、改めて聴いてみると、フィル・ウッズ、ソニー・クリス辺りの匂いがします。明らかに、パーカーやステットは違いますね。もちろん影響はもろに受けているでしょうが、なにがどう?と言われても理屈じゃないです。音楽理論はわからないから。
キャノンボ-ル・アダレイ・クインテット・イン・シカゴ/ユニバーサル ミュージック クラシック

¥1,851
Amazon.co.jp
【2曲目】トニー・ハーパー「アイ・クッド・ライト・ア・ブック」
唄もの。自分を、ふわりと空に放り投げたような、そんな緩さがいいですね。でも、個性はないです。オスカー・ピーターソン、いいですね。
WITH THE OSCAR PETERSON QUARTET / DIZZY GILLESP.../FRESH SOUND

¥2,335
Amazon.co.jp
【3曲目】グラント・グリーン「ブルー・ムーン」
グラント・グリーンは、大学生の頃、よく聴きました。最初、ケニー・バレルが好きだったのですが、バレルのブルージーな方向を追い求めると、必然のようにぶち当たったギタリストです。ワンパターンと言えなくもないのですが、ホーンライクなソロは好きです。でも、やっぱりソニー・クラークかな。
グッデンズ・コーナー/ユニバーサル ミュージック

¥1,620
Amazon.co.jp
【4曲目】パット・マルティーノ「青春の光と影」
ふくよかな情感がすてきなギタリストですね。それでいて、結構、ぶった切ったようなノイズを持った音も出せる。いいですね。それに比べ、唄の女性は、ちょっとニュアンスが乏しいです。これでは、ジャズとは言えない、ただのアレンジをなぞっただけですね。よくある、勘違いするパターンです。
何もしたくない時のジャズ/ユニバーサルミュージック

¥2,057
Amazon.co.jp
【5曲目】ウエス・モンゴメリー「 アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー」
こちら
・・・ここで録音は切れちゃっています・・・・・・
お終い。
にほんブログ村
さようなら、チャーリー・ヘイデン。
私の知る限り、最も個性的なベーシスト、そして最も好きなベーシストの一人、チャーリー・ヘイデンがお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈りいたします。
彼を初めて聴いたのは、多くの方が同じだろうと思いますが、キース・ジャレットのアメリカンカルテットの演奏ででした。
まず、FM から流れてきたキース・ジャレットの『ソロコンサート』で衝撃を受け、キースの音楽を聴くようになり、インパルスの『Fort Yawuh』を聴いたのが初めてだったような気がします。そこで、初めてチャーリー・ヘイデンという名前を知りました。ジャズの正当派のべーシルトとは全く違うベースライン、キースのアメリカンカルテットの音楽の中では、全く自然な音なのですが、客観的にジャズのメインストリームの音楽からみると、異端児であることは kumac にも理解できました。
その異端児という印象は、彼の代表作である『リベレーション・ミュージック』を聴いたことで決定的なものとなりました。そして、kumac の中で、最高のベーシストの一人となったのです。
ジャズは「抵抗の音楽」という姿勢を貫いたミュージシャンではないかと思います。最初は、左翼、つまり資本主義社会への警鐘を鳴らしているのではないかと思ったのですが、晩年にグラミー賞の「グラミー賞生涯功労賞」を受けるに至って、kumac はちょっと違和感を感じたのでした。「あっ、アメリカってチャーリー・ヘイデンを表彰するんだ。懐が深いな」と思ったのでした。しかし、それは、kumac の認識不足であり、彼はアメリカの中におけるいわゆる抵抗勢力ではなく、政治的なことよりも、もっと大きな精神を持ち、その根底にあったのは人道主義、人間性を守るという、人々を感動させる温かな心、徹底的な集団主義への抵抗ではなかったのかと今では思っています。
チャーリー・ミンガス、スコット・ラファロに匹敵するほどの個性の強い、奏でるベースラインで自己主張ができる数少ないベーシストではなかったかと思います。
生演奏を聴いたのは、アメリカンカルテットでの最初の来日公演における仙台での演奏、それとケニー・バロンとのブルーノート東京でのデュオ演奏の2回だけでしたが、彼と同じ場所と同じ時間をほんのちょっとの時間でしたが、共有できたのが kumac のジャズ遍歴の中ではとても名誉なことだと思います。
ありがとうございました。

にほんブログ村
彼を初めて聴いたのは、多くの方が同じだろうと思いますが、キース・ジャレットのアメリカンカルテットの演奏ででした。
まず、FM から流れてきたキース・ジャレットの『ソロコンサート』で衝撃を受け、キースの音楽を聴くようになり、インパルスの『Fort Yawuh』を聴いたのが初めてだったような気がします。そこで、初めてチャーリー・ヘイデンという名前を知りました。ジャズの正当派のべーシルトとは全く違うベースライン、キースのアメリカンカルテットの音楽の中では、全く自然な音なのですが、客観的にジャズのメインストリームの音楽からみると、異端児であることは kumac にも理解できました。
その異端児という印象は、彼の代表作である『リベレーション・ミュージック』を聴いたことで決定的なものとなりました。そして、kumac の中で、最高のベーシストの一人となったのです。
ジャズは「抵抗の音楽」という姿勢を貫いたミュージシャンではないかと思います。最初は、左翼、つまり資本主義社会への警鐘を鳴らしているのではないかと思ったのですが、晩年にグラミー賞の「グラミー賞生涯功労賞」を受けるに至って、kumac はちょっと違和感を感じたのでした。「あっ、アメリカってチャーリー・ヘイデンを表彰するんだ。懐が深いな」と思ったのでした。しかし、それは、kumac の認識不足であり、彼はアメリカの中におけるいわゆる抵抗勢力ではなく、政治的なことよりも、もっと大きな精神を持ち、その根底にあったのは人道主義、人間性を守るという、人々を感動させる温かな心、徹底的な集団主義への抵抗ではなかったのかと今では思っています。
チャーリー・ミンガス、スコット・ラファロに匹敵するほどの個性の強い、奏でるベースラインで自己主張ができる数少ないベーシストではなかったかと思います。
生演奏を聴いたのは、アメリカンカルテットでの最初の来日公演における仙台での演奏、それとケニー・バロンとのブルーノート東京でのデュオ演奏の2回だけでしたが、彼と同じ場所と同じ時間をほんのちょっとの時間でしたが、共有できたのが kumac のジャズ遍歴の中ではとても名誉なことだと思います。
ありがとうございました。
にほんブログ村