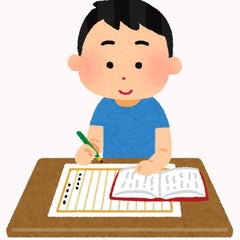日にちが過ぎるのは早くて、もう一か月が経ってしまいましたが、4月3日に子ども作文教室の講師6名で、「春の街歩き」を開催しました。
東急目黒線武蔵小山駅10時集合⇒星薬科大学⇒戸越銀座でランチ⇒洗足池公園・勝海舟記念館と墓地⇒東京科学大学⇒大岡山駅解散の行程でした。当日は止みそうで止まない霧雨が降り続く寒い一日でした。
星薬科大学
星薬科大学の創立者・星一は、明治6(1873)年、福島県に生まれた。20歳でアメリカへ渡り、コロンビア大学で経済学と統計学を修めた。帰国後、社会奉仕可能な事業として製薬を始め、研究を重ねて“イヒチオール”という湿布薬を販売するに至った。この薬の爆発的な人気と収益を基に、明治44(1911)年、星製薬株式会社を設立、社内に星薬科大学の前身である教育部を設置した。星薬科大学は、1911年の創学依頼、「世界に奉仕する人材育成の揺籃である」を建学の精神として制定された。
第一次大戦終結後、星は科学技術の最先進国ドイツの窮状を知り、明治維新後、多くの日本人が学んだドイツに恩返しができたらと、義援金を募るが思うに任せず、私費での援助を決断した。大正8(1919)年~14(1925)年までの7年間、事業が傾いた時も自宅を抵当に入れてまでも送金を続けた。その総額は現在の邦貨に換算して優に20億円を超える。一重に、日本がドイツから多くを学ばせてもらったことへの感謝と科学技術の危機を救いたいとの思いからのことである。星の援助により、後年、ノーベル賞を受賞する2人をはじめ、多数の研究者が活路を開かれ、今日のドイツ科学の礎を支えたといわれている。
当作文教室で教材として使用している『きまぐれロボット』の著者、星新一(本名:親一)は、星一の長男で、本名の親一は、一がモットーとした「親切第一」の略で、弟の名前の協一は「協力一致」の略である。新一は、父の死後、短期間星製薬の社長を務めたこともある。
講堂(メインホール)
本館内のドアを開けると、座席数1228席の講堂があります。この講堂は、星一が4年間学んだ留学先のコロンビア大学のローホールを模しています。建築を依頼したのは、1919年、旧帝国ホテル建設のスタッフの一員として来日したチェコ出身のアメリカ人建築家、アントニン・レーモンド氏でした。
メインホールには幾何学的なデザインが様々なところで見られますが、これは当時、彼の生まれ故郷で盛んに取り入れられていたチェコ・キュビズムの建築様式です。
メインホールの天井は、星がデザインされていて、天井の周りの7面の窓に校章と鹿茸、42種類の薬草をモチーフとしたステンドグラスが取り付けられています。
3階建ての建物には階段がなく、スロープが上下の移動手段となります。これは、一度に大勢の人が移動することを考えて歩行しやすく、安全性を考えての設計だそうです。このスロープの壁には、推古天皇の時代の薬草狩りと鹿茸狩りの様子を4枚の壁画として描いています。鹿茸狩りとは、成長する前の牡鹿の角を狩ることで、鹿茸は、この時代から生薬として使われていました。
100年の歴史を持つ講堂ですが、1923年9月の関東大震災、その後の太平洋戦争では、昭和20年5月23日の夜の空襲で、辺りは一夜にして灰燼に帰してしまいましたが、星薬科大学の講堂(メインホール)だけは残りました。終戦後は4年間GHQに接収されましたが、返還されてから何度となく補修を繰り返して、今でも学生や職員が創立者の思いを受け止め、愛着を持って大切に使い続けています。
本館は、日本建築学会の「近代日本の名建築」、品川区の「しながわ百景」にも指定されています。
薬用植物園
新しい医薬品を開発する資源としての植物を収集・栽培し、薬学的研究や啓蒙活動を行う施設で、一般的には薬草園と呼ばれています。大学構内にあるのが特徴で、3000㎡の広さがあり、薬用を中心とした有用植物約800種が栽培されています。園内は、おおまかに水生植物園、標本園、野草園、温室などに区分され温室内には熱帯産の薬用植物が集められていますが、当日はカカオが生っているのを見ることができました。野草園では牡丹が咲き、標本園では芍薬が元気よく芽を出していました。
歴史資料館
歴史資料館には、星薬科大学の歴史を展望するコーナーや、星一ゆかりの品々等が展示されています。星一の肖像と普段着用していた洋服、星一がモットーとしていた「親切第一」の額、友人だった野口英世の顕微鏡も保存されています。
英文は
“Why do many men never amount to anything? Because they don’t think”
「人は何故に成功せざるか、それは考えざるが故なり」
と記されている。
歴史資料館で星薬科大学を後にし、戸越銀座へ行き、街中華のお店でランチを頂きました。
食後、まだ霧雨は降り続いていましたが、洗足池公園を目指して歩き始めました。
勝海舟記念館
勝海舟記念館は、国登録有形文化財である旧清明文庫を保存・活用しながら増築し、勝海舟記念館を開館しました。明治時代後期、海舟は洗足池の畔に別荘「洗足軒」を構え、自身の埋葬の地に定めていました。
上の写真は、貴賓室として使用されていた当時の造りを復元した部屋で、老年期の海舟をモデルとした胸像が設置されています。
記念館から湖畔を少し歩くと、勝海舟夫婦墓所があります。海舟は明治32年1月19日に死去しました。五輪の形式は海舟が生前に図案化して指示したもので、「海舟」の文字だけを水輪に刻ませていました。
この後、最後の目的地、東京科学大学に向かいますが、相変わらず雨は降っています。
東京科学大学
東京科学大学は、2024年10月東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により新たに誕生した大学です。
博物館本館(百年記念館)
博物館の地階と2階に常設展示室があり、地階の特別展示室では、紡織(学科実験)工場で使用された繊維機械、東工大で開発された通信機器、東工大で利用された機器、スターリング・エンジンなど歴史的に価値のある大型機械類などが展示されていました。理系の方々の眼は輝いていましたが、私はただへー、フーン、すごいなと感心するだけでした。最後に、「資史料館とっておきメモ帳」という冊子が置いてあるのを見ていましたら、「夏目漱石と東工大 漱石の本学における講演はいかにして実現したか? そしてその後日談は?」「東工大が生んだデザイナー芹沢銈介のカレンダーの世界 伝統の型染めに命を吹き込み人々を魅了」など面白そうな、興味深い冊子があり、頂いてきました。
そして、大岡山駅で解散になりました。
東急目黒線に乗ったのも初めて、武蔵小山駅からの今回の街歩きは私にとって未知の世界でした。住宅街の細い道を通って行った星薬科大学の講堂はとても興味深く拝見してきました。100年を経ている講堂に一番感動しました。最後の東京科学大学の桜並木がきれいでした。
企画、下見もして準備して下さったK講師、N講師ありがとうございました。
(chtaki記)