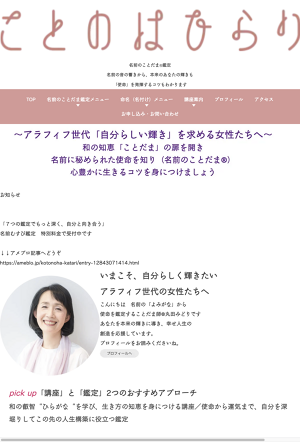5月5日は「こどもの日」
私が幼い頃はご近所のお家で
立派な鯉のぼりがあげられていました
あまりに立派で
うちの犬が怖がって散歩に出ないという
できごともありましたが、
その地域一帯の男の子のためにという
意味もあって、みんなとても喜んでいたものです
それで言うと私たちは
刷り込まれるようにといいますか
================
5月5日は男の子の節句
女の子は3月3日
これがあたりまえと捉えています
しかし実は…
================
「ことだま歳時記」は
単に行事や食べ物の話をするわけではなく
私たちが知っておきたい日本の風習、歴史
そして生活の知恵
代々語り継ぎたい大事な事柄についての
お話がメインです
ではテーマに話を戻しましょう
5月5日
それはもともと
女の子のための日でした
田植えをする若い女の子を
「早乙女(さおとめ)」と呼びます
若い女性が田植えをすると
成長が良いという理由があったようです
(女性―育てる役割も関連してか…)
5月5日は
「五月忌み(さつきいみ)」
早乙女たちが田植え前に身を清める日
と言っても同じ家に集まり楽しく過ごす
かわいいものですが
清めの日としてあてられていました
それが鎌倉時代になると武士が台頭し
(大河ドラマ鎌倉殿の13人でも描かれるように)
武士の時代がやってくると、
中国で行われていた菖蒲を燃やして香りで
邪気祓いをする風習が取り入れられ
菖蒲――勝負(尚武)とかけあわせ
男の子の節句へと変わっていったのです
歴史が語る物語
知ると知らないでは
人生のふくよかさが違います
じゃ、なぜ5月5日なの?というのは
講座でどうぞ(数字にヒントあり)
そうして古代と現代の子ども観についても
じっくりお話しますよ
特にこの「子ども観」については
たくさんの方に知って一緒に考えて
いただきたい、そんなお話です
「ことだま歳時記」
月一回(第三水曜日)に行っています
オンライン講座なので、全国どこからでも
それこそ海外からでも参加できます
(実勢メルボルンの方がおられます)
↓こちらからお問い合わせください
(その他問い合わせを選んでご記入ください)
1講座3300円です、現在は年間コースのみ行っています
あなたも日本の古来からの知恵を
ぜひ生活に取り入れてみてくださいね
文化と知恵を知る。明日からの生活が
ぐっと豊かになりますよ