<総人口>1億2667万人:有権者数は1億757万3千人で84.92%でした。
有権者数は1億757万3千人、そのうち18歳以上19歳未満が下記の人数です。
18歳になるのが122万9000人、19歳が123万3000人とあり、約246万2000人になることがわかった。これは、全人口の1.9%です。
前回は2.4%でした。これからも解るように20未満の人口の比率も減少してきているのです。
(人口統計資料集を見ると、2016年10月1日現在のデータしかありませんでした。)
人口推計(平成29年(2017年)4月確定値,平成29年9月概算値) (2017年9月20日公表)されていました。
≪ポイント≫
【平成29年9月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2667万人で,前年同月に比べ減少 ▲23万人 (▲0.18%)
【平成29年4月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2676万1千人で,前年同月に比べ減少 ▲21万5千人 (▲0.17%)
・15歳未満人口は 1569万9千人で,前年同月に比べ減少 ▲18万2千人 (▲1.15%)
・15~64歳人口は 7616万4千人で,前年同月に比べ減少 ▲63万2千人 (▲0.82%)
・65歳以上人口は 3489万8千人で,前年同月に比べ増加 60万人 ( 1.75%)
<日本人人口> 1億2481万4千人で,前年同月に比べ減少 ▲35万1千人 (▲0.28%)
統計表
- 統計表
 (政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表)
(政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表)
※ その他の推計結果
- 各月1日現在人口 「全国:年齢(5歳階級),男女別人口」
- 各年10月1日現在人口 「全国:年齢(各歳),男女別人口」 「都道府県:年齢(5歳階級),男女別人口」
- 国勢調査結果による補間補正人口 「全国人口:各月1日現在人口」 「都道府県人口:各年10月1日現在人口」
- 国勢調査による基準人口
- 長期時系列データ (大正9年~平成12年)
トップ > 選挙・政治資金 > 選挙 > なるほど!選挙 > 選挙権と被選挙権
なるほど!選挙
選挙権と被選挙権
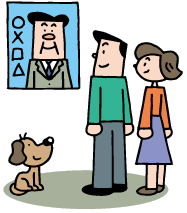
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
もくじ
1. 選挙権
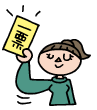 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
| 備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 | |
|---|---|---|
| 衆議院議員・参議院議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
|
| 知事・都道府県議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
|
| 市区町村長・市区町村議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)
メモ
- 選挙権年齢が引き下げられました
- 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
それでは、海外の選挙権年齢はどのようになっているのでしょうか。
現在海外では「18歳以上」が主流です。国立国会図書館の調査(平成26年)では世界の191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳以上となっております。
選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
2. 被選挙権
 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表を参照してください。)
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表を参照してください。)
| 備えていなければならない条件 | |
|---|---|
| 衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
| 参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
| 都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
| 都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
| 市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
| 市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
メモ
- 被選挙権の資格年齢
- 被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。

