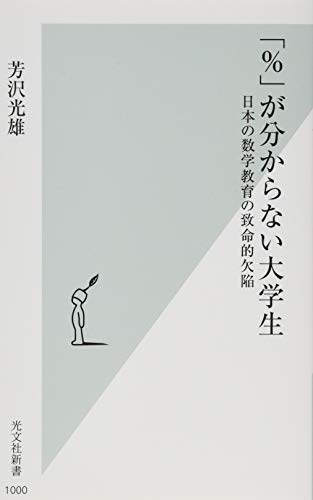従来から日本は資源を持たない国家であり、
人材を資源として国家運営を行っていくことが
国策の根本にあった。しかも、今後は人口減少社会に入っていく。
このような状況にあって、ますます教育の重要性が高まるのは必然であるのだが、
問題は、「%」の計算がわからない大学生が増えていると近年巷間で言われていることである。
例えば、2012年と1983年の全国学力テストの結果を比較してみると、
正答率が20%も低下しているのである。
原因は単に「やり方」を覚えるだけの詰め込み教育にあるのは明白である。
結果だけを無意味に暗記する教育では、少数の生徒だけは
努力が結果にむすびつく好循環に乗れるものの、そうでない生徒は努力しても
結果が出ず、意欲をそがれてしまい、最終的に学習自体を放棄してしまう。
本書によると、重視すべきは「やり方」ではなく「プロセス」だという。
たしかにテストで正答を重ねることは大切かもしれないが、そもそも数学においては
「理解」こそが問われるべきであろう。そして、重要なのは、「わからないこと」、「理解が遅いこと」も
それ自体は悪いことではない、ということだ。この点は教育現場でも認識を改めるべきであろう。
今後の日本の教育では、一人ひとりのペースに合わせて理解させ、その過程を評価する教育
である。そして、そのような教育こそが、21世紀後半の日本を支える人材を生み出すことが
できるのである。