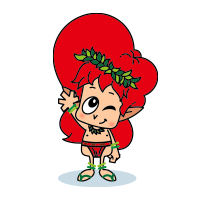(この記事は舞台「マスタークラス」の内容に触れています)
先日は大阪はサンケイホールブリーゼにて、舞台「マスタークラス」観劇でした。歌手マリア・カラスの、後年、音楽院で行った公開授業、マスタークラスに、彼女の音楽と人生とが組み込まれた作品です。
演技のもたらすぴんと張った空気、身体、それをもって鑑賞しました。
実在の著名な人物を演じる事の困難は、演じるとは同一化でも物真似でも降霊術でもないから。
妙な事に、彼女にまつわるいくつもの逸話、何より歌声、から、観る私はマリア・カラスという人もほんの少しは知っているという勘違いをもって観ています。
更に個人的にこの作品への解釈で厄介となっているのは、私が望海風斗さんの一ファンであり、かの人に心酔している部分がないと言えば嘘になる点です。
私はマリア・カラスに逢い、知ったように錯覚しますが。
私の観る舞台にいたのは望海風斗さんを初めとする演者の皆さんであり、ここはマスタークラスの聴講席ではない。
その演技の卓越さ、観る者の両の肩に舞い降りたでしょう密度、それらをつつき回したい訳ではない。
なのに同一視を助長してしまい、全てを肯定してしまうのに対する心の警鐘が鳴ったのが、終わって大分、それこそ翌日の鐘が鳴ったしばらく後の事でした。
とても怖い事でした。
生徒たち。
最初の生徒はその素直さですくすくと伸びて欲しい。
二人目の生徒は贈られた言葉のように、暖かに、今の自分のままであって欲しい。
三人目(あ、正確にはこちらが二人目か)は、いつか目が醒める事があってもなくても、その強さと相性のいい先生に出会えるといい。
マリアが受けた仕打ちの告白を前にして、鑑賞後でずたずたに引きちぎりたくなった(すみません)アリーの写真が、あらかじめちゃんと小間切れで写されていたのは、観ていたこちらの気持ちをやはり誘導されていたのを実感したのも併せた、複雑な苦さを覚えました。
望海さんの演じるアリーはマリアの記憶のアリーでしょうから彼女なりの美化が加えられていて、でもそれを差し引いても当人にも魅力があるのだろうな、と感じたり、オペラに対する愛情と無理解とで全くの正反対なのに「観客が求めるものは」と語る所など、何か互いの琴線に響く恋人同士だった事は察せられました。
でもやっぱりアリー許せん。
一時の授業を伴にした栄誉を誇らしくあった伴奏者の、結局は今の一時にしか添えないしましてや彼女の孤独には寄り添えない哀しみをもってマリアを見送る表情が忘れられません。
結局、私などと違い、授業に支配されていない視点を持っていたのは、マリアに「芸術を必要としていない存在」と言われ、「親方はいない」と言っていた、手伝いに度々現れた道具係の男だけかもしれません。支配されていないもの、神の視点を持つ存在。キリストは大工の息子ですから。