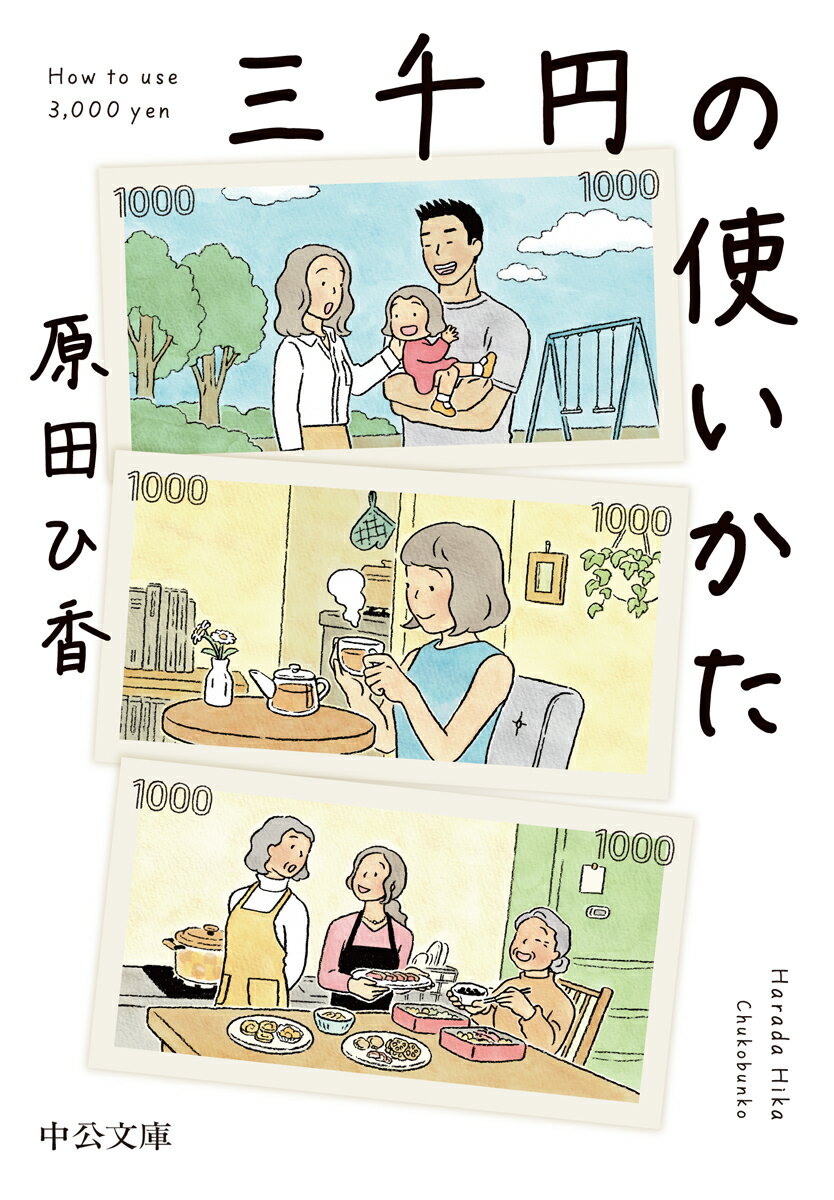読書☆青い壺
有吉佐和子 著
50年前の本で、一度絶版になるも、
2011年に異例の復刊をしたそうです。
最近人気なのだそうで、
確かに、書店に行くと、平積みされて
いたりします。
AIのあらすじ⬇️
- 無名の陶芸家が作り上げた、かけがえのない青磁の壺が誕生します。壺は、陶芸家の手を離れた後、日本橋のデパートで売られ、盗まれ、そして海を越えてスペインへ旅立ちます。壺は旅の途中で、定年後の虚無を抱える夫婦、財産争いをする家族、目の不自由な母と娘、スペインに帰郷する修道女など、様々な人々の人生を見つめます。
10年以上の時を経て、古色をまとった壺は作者のもとへ戻り、再会を果たします。
とても読みやすい文章と、13話からなる
短編集形式なので、読了までに日数は
掛かったけど(途中で他の本も読んでたので)
さらっと読めた感じです。
美しい青磁の壺が、人の手から手に転々と
していくお話で、でも青い壺のというよりは
青い壺を手にする人達の人生のお話です。
最後のお話がちょっと切なくショッキングです🫨
どのお話もだいたい、
50年前のザ・昭和の様々なファミリーが
描かれてますが、わちゃわちゃ、女性達が
語りあうシーンは、
まるで、渡る世間は鬼ばかり…を見て
いるよう。(笑)
社会も、家庭に於いても、
人間関係がどんどん希薄になっている
令和の今は、この空気感もなんだか
とても懐かしく思えてしまう昭和人です。
昭和の小説と言えば、ワタシ、
おばあちゃんち(実母が育った家)の
本棚に並んでいた源氏鶏太さんの本を
小中学生の頃、良く読んでいたのですが😅
同じような匂いのする本でした。
母が若い頃(昭和30〜40年代)に
源氏鶏太さんの小説がブームだったのかな?
昭和の
高度成長期、
サラリーマン、
OLさん…
がキーワードな小説です。
青い壺は昭和50年頃が舞台で、
この頃は私は子供だったので、
戦争(第二次世界大戦)はすっかり過去のもの
でしたが、
当時大人の人達には、まだ戦争の記憶が
濃く、人生に大きく影響していたのだなぁ、
としみじみ思うエピソードの数々。
そして、
13話の短編をまとめた1本の小説と
書きましたが、そう長編って訳でもない
本ですが、これを読んだだけでも
有吉佐和子さんが多方面にわたり
博識な事が分かり、さすが作家の方は
凄いなぁと思いました。
また、この本が50年の歳月を経て復刊し、
人気が出ているのは、今の若い人たちに、
昭和のレトロ感、
女性たちの上品な言葉遣いや、小物類、
エレガントな身のこなしというか仕草が
刺さってるからじゃないでしょうか?
かく言うワタシも、登場人物の優雅な様に
憧れを抱きました。
良い時代だったんですねぇ![]()
これから先、二度と来ることのない
古き良き時代。
今まで有吉佐和子さんの作品は、多分…
読んだ記憶が無いのですが、
その時代の空気に浸りたくなったら、
他の作品もぜひ読んでみたいです。
「三千円の使いかた」の原田ひ香さんが
こんな小説を書くのが私の夢です
と、帯に書いたのも、爆発的に人気が
出た理由の一つだとか。⤵️