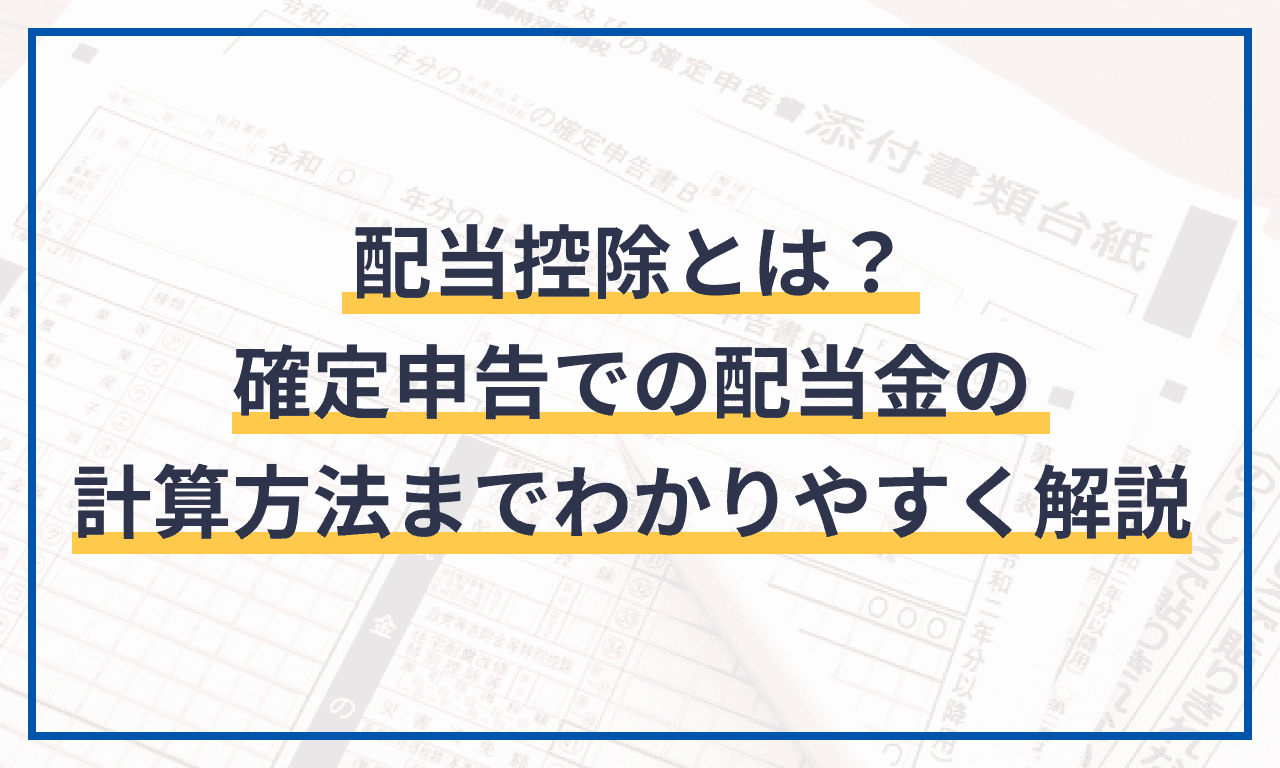みなさんおはようございます。
今朝はFP2級の科目別問題集CHAPTER4「タックスプランニング」について取り組みました。
取り組んでみて感じたポイントは「損益通算できる?できない?」と所得を計算するときに用いる「控除」の条件とその額でした。
以下に復習を兼ねてポイントをメモ。読みやすさへの配慮ゼロですみません。
<所得税の納税義務>
・居住者かつ非永住者以外(永住者と日本人)⇒すべての所得が対象
・居住者で非永住者(日本国籍がなく、住んでたのが過去10年のうち5年以下)⇒国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で、国内において支払われ、または国外から送金されたもの
・(日本国籍を有する)非居住者⇒国内源泉所得のみ
<総合課税>
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地、建物、株式以外、ゴルフ会員権、事業に用いる営業車、事業目的ではない金地金など)、一時所得、雑所得
太字は源泉分離課税とされているもの等を除く。
<分離課税>
退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式など)
退職所得は、何千万円もの退職金が総合課税にされると税金が45%とかになって可哀そうだから違う。
譲渡所得は投資っぽいものは分離課税、それ以外は総合課税。
<所得額の計算>
給与所得・・・収入金額‐給与所得控除額
退職所得・・・(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額⇒「40万円×勤続年数(勤続20年以下)」あるいは「800万円+70万円×(勤続年数ー20年)」
雑所得・・・総収入金額‐必要経費(公的年金等以外のものに係る場合)※公的年金等の場合は別途「×税率-控除額」で計算。
一時所得・・・総収入金額‐支出金額‐特別控除額(50万円)⇒他の所得と合算し総所得金額を算出する時には×1/2
一時払養老保険などは5年以内だと金融類似商品として源泉分離課税。それを超えると一時所得。
<損益通算>ふじさんじょう
不動産所得の損失⇒土地を取得するための借入金利子は×
事業所得の損失⇒〇
山林所得の損失⇒〇
譲渡所得の損失⇒生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、宝石など)の譲渡による損失×
土地建物(一定のものを除く)の譲渡から生じた損失×
株式等の譲渡損失(一定のものを除く)×
自家用車など生活に供する動産は非課税だし損益通算ダメ
上場株式の譲渡損失は申告分離課税の配当所得との通算可能。総合課税を選択(配当控除をしたい場合)すると通算できない。
相課税所得695万円以下の場合は配当控除が得らしい。
<控除>※最新内容要チェック
配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除
・基礎控除は納税者本人の合計所得金額が2400万円以下で48万円、その後下がっていって2500万円以上でなし。
・配偶者控除は900万円以下で38万円(70歳以上は48万円)、1000万円を超える場合はなし。
配偶者は合計所得48万円以下(給与のみの場合103万円以下)など条件あり。内縁関係×
・控除対象扶養親族・・・16歳以上と23-70未満(38万円)、19~23未満は特定扶養親族(63万)、70以上(同居58万、以外48万)合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円)
・所得金額調整控除(所得は夫婦で合算しない)
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
・医療費控除・・・支出した医療費-10万円(or総所得金額の5%)
自家用車ダメ。やむを得ない場合以外のタクシーはダメ。
・住宅ローン控除・・・6か月以内に居住。合計所得金額が2000万円以下。床面積40~50㎡の場合は1000万円以下。
基本は床面積50㎡以上、1/2以上が自己使用。返済期間は10年以上(繰り上げ返済注意)
年末の残高限度額3000万円、0.7%、13年
<確定申告>
同族会社の役員等で、その同族会社からの給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合には必要
<青色申告>繰り越し控除は3年間。10万円か55万円か65万円の控除。
<交際費>800万円以下の全額か飲食支出額×50%の多い方(資本金1億円以下)
飲食支出額×50%(資本金1~100億円)
<消費税(詳細要確認)>基準期間は個人の場合前々年。法人は前々事業年度。
個人の確定申告は課税期間の翌年1/1~3/31
簡易課税制度を選択した場合、廃業を除き2年は継続しなければいけない