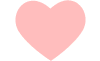明日は笹の節句、七夕です。
この「節句」と呼ばれる日は年に5回もあります。
3月3日は「桃の節句」、5月5日は「端午の節句」ということは良く知られていますが、その他にも1月、7月、9月と奇数月の季節の節目がこれにあたることはあまり知られていません。
その節目にあたる日のことを節句(節供)といいます。
江戸時代までは公的行事が行なわれ祝日として定められていました。
1月7日 人日(じんじつ) 七草の節句
3月3日 上巳(じょうし) 桃の節句
5月5日 端午(たんご) 菖蒲の節句
7月7日 七夕(しちせき) 笹の節句
9月9日 重陽(ちょうよう)菊の節句
さて、その七夕はもともと中国の乞巧奠(きっこうでん)の行事であり、機織りや裁縫、習字などの習いごとの上達を願い、祈る日でもあります。
この中国での行事が奈良時代に伝わり、元からあった日本の「棚機津女(たなばたつめ)」の伝説と合わさって生まれた言葉が「たなばた」です。
古来、豊作を祖霊に祈る祭として行われていた「たなばた」は「棚幡」「棚機」とも書かれ、お盆行事の一環です。
精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから7日の夕で「七夕」と書いて「たなばた」と発音するようになったともいわれています。
今でもお盆行事の一部でもあり、笹は精霊(祖先の霊)が宿る依代になります。
その笹に飾る願い事を書いた短冊はもともと大人たちが詩歌を色紙に書いたのが始まりで「万葉集」や「古今和歌集」などにも七夕の風習を詠んだ歌が多く残っています。
一般的に旧暦の7月7日の夜のことをいいますが、明治改暦以降、お盆が7月か8月に分かれるようになり、7月7日又は月遅れの8月7日に分かれて七夕祭りが行われています。
ちなみに全国で一番有名な宮城県仙台市の七夕祭りは8月7日です。
いつか行ってみたいものです。
あっ、この夢を今年の短冊に書いておこうо(ж>▽<)y ☆