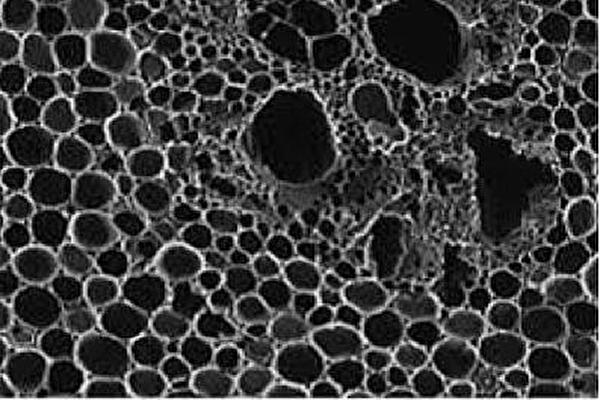おはようございます竹林整備の野澤です。【Vol 083】
本日も前回に引き続き福井県での林業実習PART10についてシェアさせて頂きます。
尿管結石の手術があり、実習を延期しました。
ですから、私は7期生でしたが9期生と合流し実習を受けます。
当然ながら、9期生の方とは初対面に近いので
上手くやっていけるか緊張感マックスで臨みました。
けれど、その心配をよそに温かく迎え入れてくれました♪
実習では覚えることが山のようにあります。
しかし、一貫して言えるのは
【危険を予期した行動をする】という点です。
早速、その点を忘れてしまい、
先生から非常に大きな声で叱責を受けました。
普段、私はガレージのDIYを一人でしています。
ですから、声を掛け合うということをしていません。
そのクセが出てしまい、
枝を切るときに【倒れます!】と周囲に声をかけなかったです。
こうしたことが、いずれ大きな事故につながります。
この実習では、技術はもちろんですが。
この危険を予期して行動することの大切さを、
叩き込まれました。
竹林整備は一人ではできません。
チームで行います。
そのときに、メンバーの危険を予期して
事前にその【対策をとっておく】ことは、
リーダーとなっていく私の責任です。
今回の実習では、そのことを徹底的に植え付けられました。
大きな事故を起こしてしまっては、
竹林整備を持続的に運営できませんよね。
本当に大切なことだと痛感しています。
画像のように、
人間の3倍以上の木を切り倒すときは、緊張で足が震えます。
私は見ているだけで足が震えました。