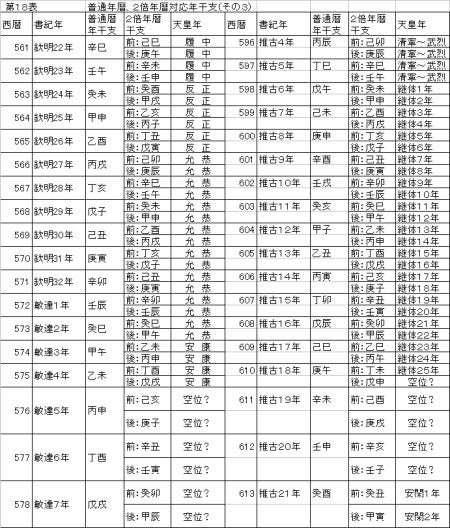45 再び『日本書紀』が語る季節
前回、私は、「誰の目にも季節がはっきりうかがえるのは冬季である。」とし、雪、霜、氷柱(ツララ)、霙(ミゾレ)
、厳寒といった現象に照準を当てて『日本書紀』記載の冬季記事をすべて拾って紹介した。
全部で8例見つかった。これらの記事には、真夏に関わらず、霰(アラレ)や雪が降ったり、家一軒を燃やして暖をとらないと凍え死にしそうだった、とする極めて不自然なものがある。
ところが、「二倍年暦」だと、ほぼことごとく無理なく妥当な記事であることを示した。
これは、『日本書紀』の編著者が、「二倍年暦」で記されていたに相違ない原記録をそのまま記したためである。
「極めて不自然だから記述した」という見解もあり得るが、深読みのし過ぎというものだろう。『日本書紀』の各記事には、異例や異常を伺わせる文言は一切ない。平安以前の漢詩、和歌、物語、随筆等々で真夏に雪などという異常現象を記載したものがあるだろうか。立秋、立冬、大寒、立春といった節気行事が生まれる背景に四季の存在があること、いうまでもあるまい。そもそも、気象衛星によって観測データが積み重ねられるようにならないと、異常気象だという判断さえ不可能だ。『日本書紀』の編著者は、原記録をそのまま書き写したに相違ない、と考えて一向に差し支えない。
『日本書紀』の編著者は、真夏(旧暦6月)に大和で雪が降ったり、凍え死にしそうになったりという記事を書くとき、極めて異常で不自然なことくらい即座に判断出来たに相違ない。にもかかわらず。珍事を示すコメントをなんら残さず、記事を自然に合うように修正を施した様子がない。
なぜか。原記録がそうなっていたからそのまま記した、と考えるのがもっとも自然である。気象記事をわざわざ異常気象記事に書き換える理由などないからだ。『日本書紀』の著者が造作や創作を施すつもりなら、いくらでも不自然でないようにに書き換えられるし、気象事項などカットすることもできる。この事実は、『日本書紀』の編著者は、原記録をそのまま単純に反映していることを示している。私にはそうとしか考えられない。
ところで、『日本書紀』記載の冬季記事8例中、日付干支が記載されているのは5例(推古36年、皇極2年、天武元年、天武11年、朱鳥元年の条)である。内、天武元年の条(壬申の乱の年)はすでに検証を行っているから、残りは4例となる。
私は、当初、この4例についても「二倍年暦」ごよみに当てはめてみようと考えていた。
ところが、天武元年の条の検証で明らかになったが、『日本書紀』の編著者は、天武挙兵の日付干支は原記録の6月の干支を起点にして、次々と日付干支を記している。単純に原記録の干支をそのまま記したわけだ。ここまではよい。ところが、これらの日付干支を普通年暦干支と解釈すると、奇妙なことになる。そもそも、原記録の6月は、普通年暦では10月後半(太陽暦では11月から12月にかけて)である。これに加えて、「二倍年暦」ごよみの日付干支は見かけ上二倍のスピードで動くから、『日本書紀』記載の月はどんどんずれていってしまう。その様子は、すでに天武元年の検証で示したとおりである。
のみならず、推古天皇の崩御年月日や聖徳太子の薨去年月日の記載で明らかになっているように、『日本書紀』の編著者は、原記録の日付干支と普通年暦の日付干支の不一致(原記録は「二倍年暦」、『日本書紀』の年紀は普通年暦だから不一致は当然なのだが)を日付干支を動かし、あるいは年干支まで動かしている。
以上、「壬申の乱」、「推古天皇の崩御年月日」、「聖徳太子の薨去年月日」の干支の動かし方から考えて、原記録の真の年干支や日付干支をたどることは非常に困難な作業となろう。
はっきりしているのは、この3例が3例とも月だけは変えていない。つまり、月だけは原記録を尊重していることになる。この3例はすべて非常に重要な記事で、朝廷内でよく知られていた事実だったに相違なく、原記録の月を動かすことははばかられたに相違ない。
したがって、『日本書紀』記載の日付干支から、原記録の日付干支を復元することは、『日本書紀』の編著者が日付干支をどのように処理したのか正確に把握しないと、非常に困難を極めること請け合いである。目下、問題にしている冬季記事の場合、月を動かすことは事柄の性格上考えられない。月はそのまま季節を表すからである。
月が尊重されていれば私としては十分。苦労して真の日付干支を追求しても実益がない。
少し気にはなるが、今回その追求はあきらめることにした。
もしも、やってみようという人がいれば、その結果をご教示いただければ幸いである。
前回、私は、「誰の目にも季節がはっきりうかがえるのは冬季である。」とし、雪、霜、氷柱(ツララ)、霙(ミゾレ)
、厳寒といった現象に照準を当てて『日本書紀』記載の冬季記事をすべて拾って紹介した。
全部で8例見つかった。これらの記事には、真夏に関わらず、霰(アラレ)や雪が降ったり、家一軒を燃やして暖をとらないと凍え死にしそうだった、とする極めて不自然なものがある。
ところが、「二倍年暦」だと、ほぼことごとく無理なく妥当な記事であることを示した。
これは、『日本書紀』の編著者が、「二倍年暦」で記されていたに相違ない原記録をそのまま記したためである。
「極めて不自然だから記述した」という見解もあり得るが、深読みのし過ぎというものだろう。『日本書紀』の各記事には、異例や異常を伺わせる文言は一切ない。平安以前の漢詩、和歌、物語、随筆等々で真夏に雪などという異常現象を記載したものがあるだろうか。立秋、立冬、大寒、立春といった節気行事が生まれる背景に四季の存在があること、いうまでもあるまい。そもそも、気象衛星によって観測データが積み重ねられるようにならないと、異常気象だという判断さえ不可能だ。『日本書紀』の編著者は、原記録をそのまま書き写したに相違ない、と考えて一向に差し支えない。
『日本書紀』の編著者は、真夏(旧暦6月)に大和で雪が降ったり、凍え死にしそうになったりという記事を書くとき、極めて異常で不自然なことくらい即座に判断出来たに相違ない。にもかかわらず。珍事を示すコメントをなんら残さず、記事を自然に合うように修正を施した様子がない。
なぜか。原記録がそうなっていたからそのまま記した、と考えるのがもっとも自然である。気象記事をわざわざ異常気象記事に書き換える理由などないからだ。『日本書紀』の著者が造作や創作を施すつもりなら、いくらでも不自然でないようにに書き換えられるし、気象事項などカットすることもできる。この事実は、『日本書紀』の編著者は、原記録をそのまま単純に反映していることを示している。私にはそうとしか考えられない。
ところで、『日本書紀』記載の冬季記事8例中、日付干支が記載されているのは5例(推古36年、皇極2年、天武元年、天武11年、朱鳥元年の条)である。内、天武元年の条(壬申の乱の年)はすでに検証を行っているから、残りは4例となる。
私は、当初、この4例についても「二倍年暦」ごよみに当てはめてみようと考えていた。
ところが、天武元年の条の検証で明らかになったが、『日本書紀』の編著者は、天武挙兵の日付干支は原記録の6月の干支を起点にして、次々と日付干支を記している。単純に原記録の干支をそのまま記したわけだ。ここまではよい。ところが、これらの日付干支を普通年暦干支と解釈すると、奇妙なことになる。そもそも、原記録の6月は、普通年暦では10月後半(太陽暦では11月から12月にかけて)である。これに加えて、「二倍年暦」ごよみの日付干支は見かけ上二倍のスピードで動くから、『日本書紀』記載の月はどんどんずれていってしまう。その様子は、すでに天武元年の検証で示したとおりである。
のみならず、推古天皇の崩御年月日や聖徳太子の薨去年月日の記載で明らかになっているように、『日本書紀』の編著者は、原記録の日付干支と普通年暦の日付干支の不一致(原記録は「二倍年暦」、『日本書紀』の年紀は普通年暦だから不一致は当然なのだが)を日付干支を動かし、あるいは年干支まで動かしている。
以上、「壬申の乱」、「推古天皇の崩御年月日」、「聖徳太子の薨去年月日」の干支の動かし方から考えて、原記録の真の年干支や日付干支をたどることは非常に困難な作業となろう。
はっきりしているのは、この3例が3例とも月だけは変えていない。つまり、月だけは原記録を尊重していることになる。この3例はすべて非常に重要な記事で、朝廷内でよく知られていた事実だったに相違なく、原記録の月を動かすことははばかられたに相違ない。
したがって、『日本書紀』記載の日付干支から、原記録の日付干支を復元することは、『日本書紀』の編著者が日付干支をどのように処理したのか正確に把握しないと、非常に困難を極めること請け合いである。目下、問題にしている冬季記事の場合、月を動かすことは事柄の性格上考えられない。月はそのまま季節を表すからである。
月が尊重されていれば私としては十分。苦労して真の日付干支を追求しても実益がない。
少し気にはなるが、今回その追求はあきらめることにした。
もしも、やってみようという人がいれば、その結果をご教示いただければ幸いである。
46 結論に至る経緯
以上で、やっと本論も終結の場面を迎えた。
振り返ってみると、本論は手探り状態でスタートした。「二倍年暦」ごよみという、実際に使用されたに相違ない、極めて具体的な形の暦の復元にまでたどりつく、とは想像もしていなかった。
ここまでたどりつくことが出来たのは、第一には、むろん、『古事記』の存在である。『古事記』は、判明している天皇の崩御年月日を、原記録そのまま忠実に書き残していた。
だが、本論を開始した当時は、『古事記』が記した各天皇の崩御年月日が、そのまま「二倍年暦」表記だったことに気づいていなかった。
そこで、『古事記』記載の崩御年を、普通暦の年紀といったん受け取り、それを半分にしたものを実年と推計した。結果的には『古事記』の記載を忠実に踏まえた形になっていたから、推計が実年を大きくずれることはなかった。
推計結果を基に、その推計実年が正しいか否かを、代表的な文献や金石文を用いて検証を進めた。こうした検証を進められたのも多くの先学の残した業績があったからだった。記紀の訓み方にしろ金石文の解読にしろ個々の専門家の業績を私は用いることができた。とりわけ、古田武彦氏の著作は私に大きな示唆を与えてくれた。
氏とは一面識もなく、その見解に同調できない私ではあるが、先入観にとらわれないで、真の事実、すなわち真理を探究しようという、その一点が命綱であり、私が共感できる点だった。
具体的にいうと、倭の五王問題を始め様々な古代史上の謎に対し、古田氏は度肝を抜く解釈を次々に施し、いわゆる古田氏のいう通説なるものを次々に痛撃している。
そのよりどころとなっているのは、九州王朝説であり、ときには多元王朝説である。謎はいくつもあって、本論で論じた謎だけでも次のようなものがあった。
ア:稲荷山鉄剣銘に現れる「シキノミヤ」は近 畿王朝に現れない謎。
イ:倭の五王は、強引な解釈を施さないと近畿 王朝に結びつかない謎。
ウ:継体紀に全くそれらしき事件がないのに 「日本の天皇、皇太子、皇子皆死去」と記さ れた奇怪な記事の謎。
エ:推古天皇は女帝なのに『隋書』俀國傳では 「男王」となっている謎。
オ:推古朝は隋王朝と重なっている部分がある にも関わらず、現実の推古紀には、大唐、唐 國、唐客、唐帝というふうに一貫して唐王朝 との交流記事になっている謎。
カ:記紀はほぼ同時代成立の史書であるにもか かわらず、推古天皇の崩御年月日が記紀で異 なっている謎
キ:法隆寺は全部焼失し、建物も仏像も再度造 られた、すなわち記紀編纂時と同時期に再建
されたと考えられるのに、推古紀と金石文た る「釈迦三尊像光背銘」とで、なぜ聖徳太子 の薨去年月日が異なるのか、という謎。
ク:「壬申の乱」は現在では七月という暑熱期の 筈なのに、なぜ家まで燃やして暖を取らない といけないほど厳寒だったのかという謎。
以上で、やっと本論も終結の場面を迎えた。
振り返ってみると、本論は手探り状態でスタートした。「二倍年暦」ごよみという、実際に使用されたに相違ない、極めて具体的な形の暦の復元にまでたどりつく、とは想像もしていなかった。
ここまでたどりつくことが出来たのは、第一には、むろん、『古事記』の存在である。『古事記』は、判明している天皇の崩御年月日を、原記録そのまま忠実に書き残していた。
だが、本論を開始した当時は、『古事記』が記した各天皇の崩御年月日が、そのまま「二倍年暦」表記だったことに気づいていなかった。
そこで、『古事記』記載の崩御年を、普通暦の年紀といったん受け取り、それを半分にしたものを実年と推計した。結果的には『古事記』の記載を忠実に踏まえた形になっていたから、推計が実年を大きくずれることはなかった。
推計結果を基に、その推計実年が正しいか否かを、代表的な文献や金石文を用いて検証を進めた。こうした検証を進められたのも多くの先学の残した業績があったからだった。記紀の訓み方にしろ金石文の解読にしろ個々の専門家の業績を私は用いることができた。とりわけ、古田武彦氏の著作は私に大きな示唆を与えてくれた。
氏とは一面識もなく、その見解に同調できない私ではあるが、先入観にとらわれないで、真の事実、すなわち真理を探究しようという、その一点が命綱であり、私が共感できる点だった。
具体的にいうと、倭の五王問題を始め様々な古代史上の謎に対し、古田氏は度肝を抜く解釈を次々に施し、いわゆる古田氏のいう通説なるものを次々に痛撃している。
そのよりどころとなっているのは、九州王朝説であり、ときには多元王朝説である。謎はいくつもあって、本論で論じた謎だけでも次のようなものがあった。
ア:稲荷山鉄剣銘に現れる「シキノミヤ」は近 畿王朝に現れない謎。
イ:倭の五王は、強引な解釈を施さないと近畿 王朝に結びつかない謎。
ウ:継体紀に全くそれらしき事件がないのに 「日本の天皇、皇太子、皇子皆死去」と記さ れた奇怪な記事の謎。
エ:推古天皇は女帝なのに『隋書』俀國傳では 「男王」となっている謎。
オ:推古朝は隋王朝と重なっている部分がある にも関わらず、現実の推古紀には、大唐、唐 國、唐客、唐帝というふうに一貫して唐王朝 との交流記事になっている謎。
カ:記紀はほぼ同時代成立の史書であるにもか かわらず、推古天皇の崩御年月日が記紀で異 なっている謎
キ:法隆寺は全部焼失し、建物も仏像も再度造 られた、すなわち記紀編纂時と同時期に再建
されたと考えられるのに、推古紀と金石文た る「釈迦三尊像光背銘」とで、なぜ聖徳太子 の薨去年月日が異なるのか、という謎。
ク:「壬申の乱」は現在では七月という暑熱期の 筈なのに、なぜ家まで燃やして暖を取らない といけないほど厳寒だったのかという謎。
もちろん、古代史上の謎は以上の諸点にとどまらない。細かいものを挙げれば数え切れないくらいある。そうした個々の謎は、専門家の間では知られていた。そして個別に、珍説、奇説をも含めてそれなりになんとか解釈を施し、説明の努力が重ねられてきた。いわば個別撃破の点的説明に終始してきた、といっていい。
そこへ登場したのが古田史学である。古田史学は九州王朝説なる仮説を用意し、その仮説を武器に数々の謎を説明しようと試みた。その核心はこうである。
古代史学者が説く学説ではつじつまが合わないのも甚だしい。それらの謎はすべて九州王朝のことだ、と解釈すればすっきりする、という主張にある。よしんば、九州王朝説で説明できない事項があっても、それは各地に王朝があったというもう一つの仮説、いわゆる多元王朝仮説を用意し、説明を試みた。
これに対し、古代史学界では両仮説とも否定ないし無視した状態になっている。
しかしながら、私はこの扱いは不当だと思う。否定ないし無視して済む問題ではない。それどころか、個々の謎にのみ着目し、個々別々の解釈(それもひどいこじつけが多い)を施して足れり、という従来の方法に逆戻りしてしまった感があるのである。
古田史学の画期的な方法は、古代史を巡る多数の謎を、個々別々ではなく一元的に捉えて解釈しようと試みた点にある。個々に捉えるやり方はマニアックになって全体が不明になりかねない。「木を見て森を見ず」ということになりかねない。
私は一元的に捉える、という古田史学の方法に衝撃を受けた。そして、それを肝に命じて研究してきたつもりである。こうした古田史学の存在がなければ、本論は登場しなかったかも知れない。この意味において私は古田氏に深い謝意を申し上げたい。


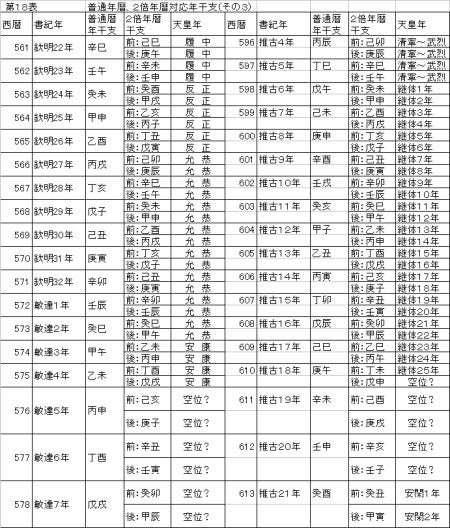



そこへ登場したのが古田史学である。古田史学は九州王朝説なる仮説を用意し、その仮説を武器に数々の謎を説明しようと試みた。その核心はこうである。
古代史学者が説く学説ではつじつまが合わないのも甚だしい。それらの謎はすべて九州王朝のことだ、と解釈すればすっきりする、という主張にある。よしんば、九州王朝説で説明できない事項があっても、それは各地に王朝があったというもう一つの仮説、いわゆる多元王朝仮説を用意し、説明を試みた。
これに対し、古代史学界では両仮説とも否定ないし無視した状態になっている。
しかしながら、私はこの扱いは不当だと思う。否定ないし無視して済む問題ではない。それどころか、個々の謎にのみ着目し、個々別々の解釈(それもひどいこじつけが多い)を施して足れり、という従来の方法に逆戻りしてしまった感があるのである。
古田史学の画期的な方法は、古代史を巡る多数の謎を、個々別々ではなく一元的に捉えて解釈しようと試みた点にある。個々に捉えるやり方はマニアックになって全体が不明になりかねない。「木を見て森を見ず」ということになりかねない。
私は一元的に捉える、という古田史学の方法に衝撃を受けた。そして、それを肝に命じて研究してきたつもりである。こうした古田史学の存在がなければ、本論は登場しなかったかも知れない。この意味において私は古田氏に深い謝意を申し上げたい。