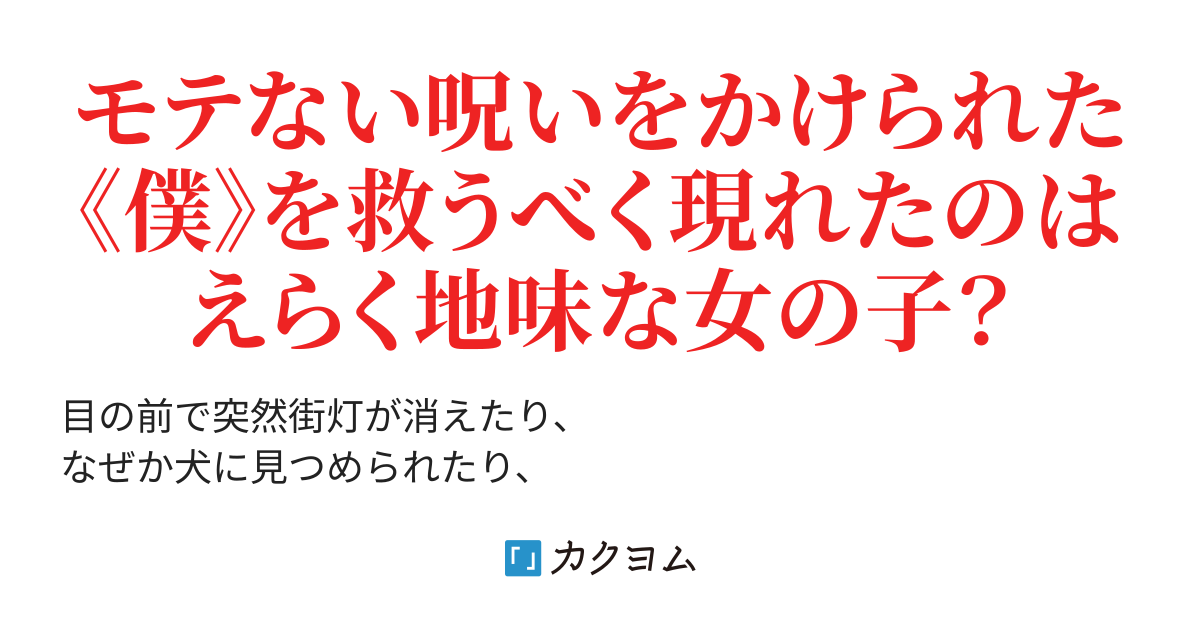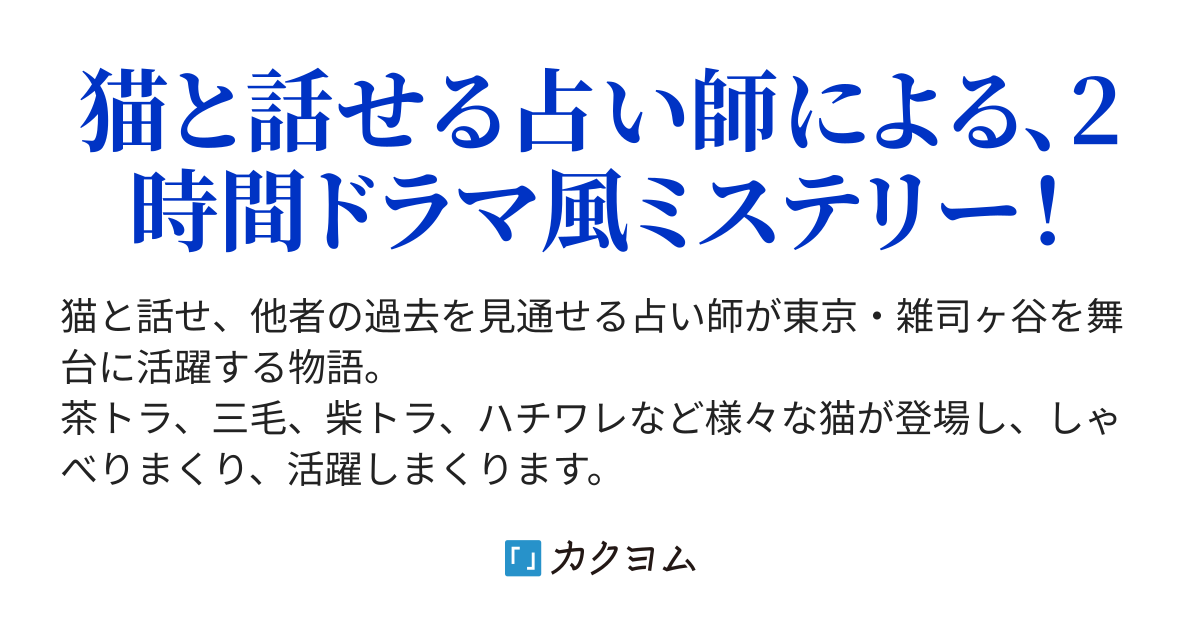「忘れたいと強く願うってのは、それだけ残ってるからなんだよ。忘れたいって思うくらい残ってるんだ。きっとそういう思いが意図せず出てしまうんだろう。あれを書いてるとき僕は嫌な夢を見た。いつも途中で終わる夢だ。僕はある場所へ向かって走ってる。まだ子供だった頃のことだ。頼りにできる大人もいなくて僕は混乱してた。混乱しながら走ってたんだ。そして、それを見た。今も印象に残ってるのは赤い色だけだ。それは液体には思えなかった。どろっとしてて端は内側へ折れ曲がるようになってた。顔は不思議と憶えてない。笑った顔だけが残ってる。それから夢は場面を変える。広い土堤下の原っぱだ。ニヤついた顔が幾つも並んでる。僕はまた走る。しかし、背中に強い痛みを感じたところで目を覚ます。嫌な夢だ。僕はなにもできなかった。ただ背中に蛇のような傷が残っただけだ。今はこれくらいしか言えない。嘘みたいに言葉が出てこないんだ。痞えてるんだよ。なにかが言葉を痞えさせてる。だから、僕は巧く小説が書けないんだろう」
ゆっくり立ちあがり、高槻さんは見下ろしてきた。その瞬間に明かりがふっと消えた。
「変電所だな。外も全部消えてる。もう閉店だ。やみそうにないし、今日は疲れたからね。――どうした? さすがに怖くなってきたんだろ?」
「もう平気です」
「本当に?」
「はい、平気です」
崩れるように座り、高槻さんは項垂れた。私はその顔を見つめていた。雷鳴も気にならなかった。吐き出される息の音以外は耳に入ってこなかった。
「僕は怖い」
「え?」
「怖いんだよ。だんだん怖くなってきた」
「なにがです?」
「わからない。ただ怖いんだ。自分がどうなるかわからない。こうしてちゃいけないって思ってるのに理性がうまく働かない。馬鹿な喧嘩をしたときと同じだ。突き動かされてる。自分でも理解できないものにね。なに言ってるかわかるかい?」
「いえ、あまり」
「だろうね。でも、それでいい。理解し合うのは危険だ。危ないのだけわかっていればいい」
煙草に手を伸ばし、高槻さんは首を振った。頬はわずかにゆるんでる。
「そう、『三四郎』の冒頭で広田先生が言ってたろ。『好きなものには自然と手が出る』って。『一念ほど恐ろしいものはない』って言ってたよな。その後は豚の話になるんだけど、あそこは本質をぼやかすための仕掛けだ。広田先生は直後にダ・ヴィンチの話をしてる。桃の木に砒素を注射して実にも毒が回るか実験したって話だ。漱石先生はそれを書きたかったんだよ。でも、それだけだと重くなりすぎるんで豚について入れ込んだんだ。――で、ダ・ヴィンチの話だ。ただ知りたいという一念でダ・ヴィンチは桃の木に砒素を打ち込んだ。でも、それを食べて死んだ者がいる。広田先生は『危ない。気をつけないと危ない』と言ってる。これは一念がそうして他者を死に導いたことを書いてるんだ。それに三四郎と美禰子の関係を予言したものでもある。人間は一念を抑えつけなければならない場合があるんだよ。気持ちに反することであってもそうしなきゃならないんだ。社会はそうやって成り立ってるんだからね」
「だけど、そうしてたらなにも変わりませんよね。『三四郎』がそうだったみたいになにも変わらないで終わってしまうんじゃないですか? 言ってたじゃないですか、三四郎や野々宮くんがもっと心をあらわしてたら結末は違ってたはずだって。あの二人は真剣に関わり合ってないって」
腕を伸ばし、私は強く握りしめた。目だけが向けられた。なにも言わず、表情も変えなかった。
「優秀な生徒だな。その通りだよ。それに反論の仕方もしっかりしてる。相手が言ったことを引いて対抗するのは優れたやり方だ。君は賢いよ。それに大胆で、はっきりものが言える。それは嫌ってほどわかった」
「真剣に関わってください。高槻さんはだんだん怖くなってきたって言ってたけど、私はずっと怖かったんです。自分の中にあるものが怖かったんです。でも、そうじゃないってわかったんです。怖がらなくてもいいってわかったんです。私、高槻さんが好きです。好きで、好きで、もうわけがわからないくらい好きなんです。たぶん初めて会ったときから好きだったんです。あのとき予感って言ってましたよね? 私はそれを感じたんです。こうなるんだろうって予感を」
濡れた頬には髪がはりついている。胸にも太腿にも汗は濃く浮き出ていた。蛇なんだ。私の中にも蛇はいる。そう感じた瞬間、それは硬い痼りを咥えて、すっと下へ降りていった。
「ありがとう。そう言ってもらえて嬉しいよ。でも、僕は君になにもしてあげられない」
「どうしてですか?」
「どうしてって。僕は三十一で、君はまだ十五なんだ。どうにもできるわけがない。まるで広田先生の夢みたいだな。この年で出会ったところでなにができる? ただ絵を観てるようなもんだ。それに僕たちがどうにかなったら犯罪だ。さっきも言ったろ? 気持ちがあっても抑えつけなきゃならない場合があるって」
「だけど、こうも言ってましたよね。まわりから間違いと思われることでも信じたら声高に叫べって。犯罪でもかまいません。この気持ちが間違ったものじゃないってわかってるんです。誰になにを言われてもいいです。だって、私は間違ってなんかいないんだもの」
「いや、すごいな。君はすごい。なにを言っても僕の言葉で返してくる。でも、それは表現に関することだ。罪を犯せって言ってるわけじゃない」
一度目をつむり、高槻さんは立ちあがった。私は縋るようについていった。
「人を好きになるのが罪になるんですか?」
「なる場合もあるんだろう。――もうこの話は終わりだ。駅まで送るよ。帰った方がいい」
「嫌です。帰りたくありません」
広い背中は目の前にあった。後ろから抱きつき、私は身体を押しつけた。
「危険だ。落合さん、危ないよ」
「危なくなんてないです。好きなんです。わけがわからないくらい好き」
「今は無理だ。すぐには君を受け容れられない」
「じゃあ、いつになったらいいんです?」
「君がもっと大人になって、それでも気持ちが変わらないなら、そのときにはいいんだろう。まあ、だとしても年の差は変わらないけどね」
腕を解き、私は正面に立った。口許は自然とゆるんでいった。
「どうした?」
「いえ。――あの、私、次の木曜で十六になります。大人にすこしだけ近づくってことです。最後の講義の日にもついてきます。それまでに考えといてください」
高槻さんはふっと窓の方を見た。その顎は鋭角で触れたら指が切れそうに思えた。だけど、次の瞬間に鈍くなった。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》