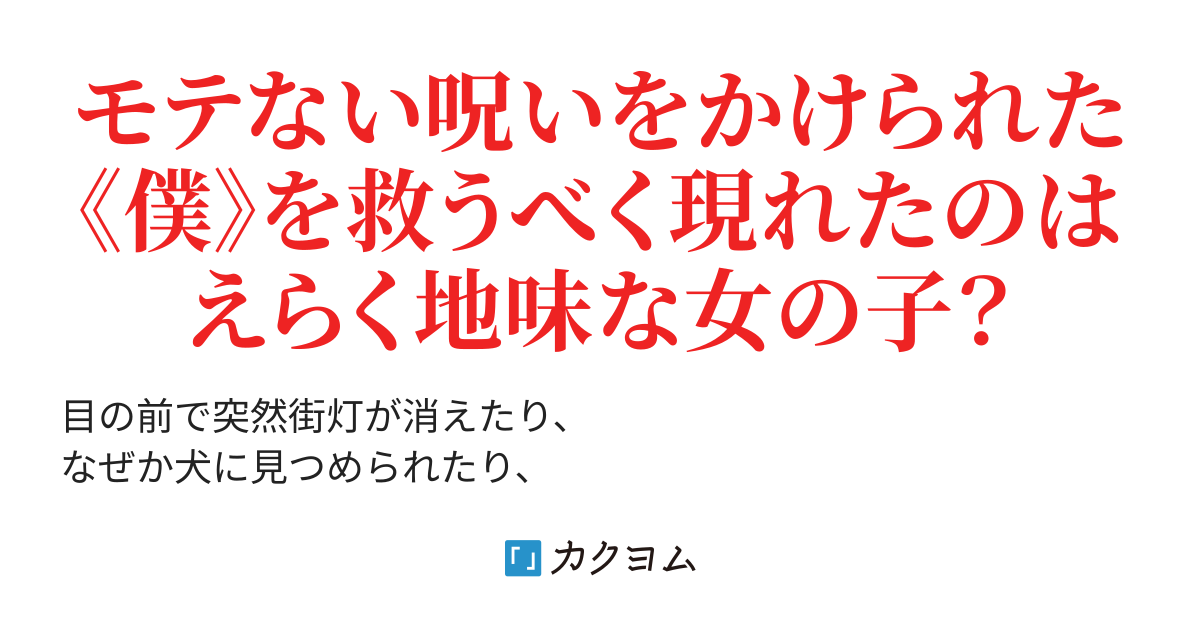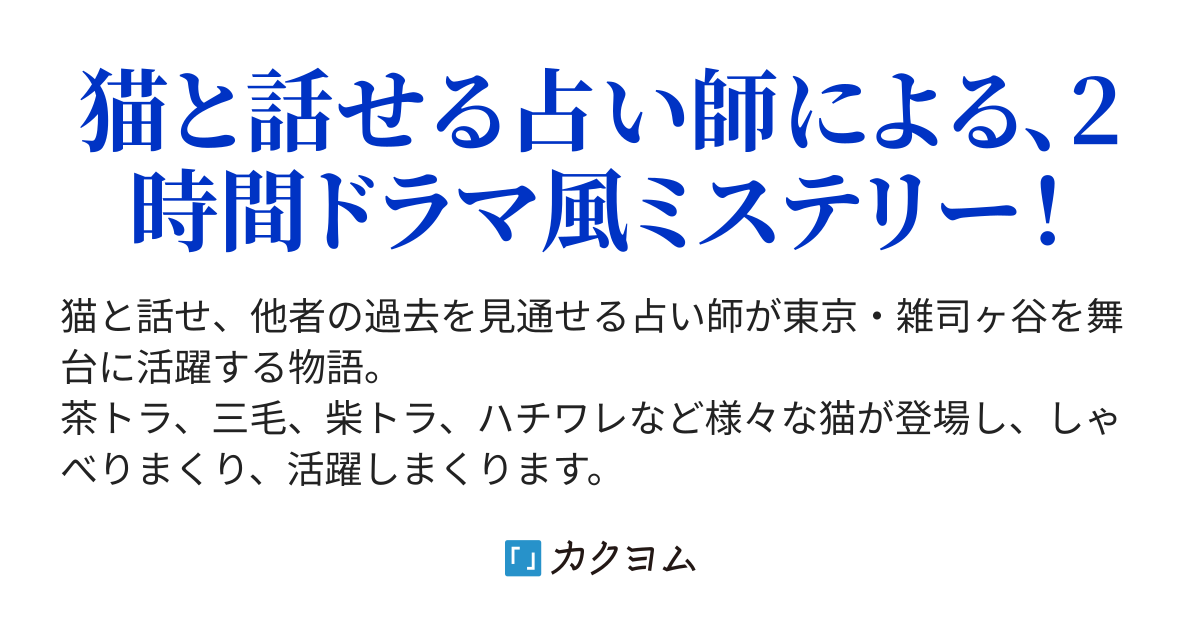柳田さんがいわゆる『文学宣言』をしたとき顧問はいいとも悪いとも言わず、ただうなずいていた。彼は四十過ぎの、小太りで、ほぼいつも曖昧な笑顔をしてる人だった。未玖は部活の初日にこう言ってきた。
「ね、新井田先生って、いかにもな感じよね。こう、オタクっぽいっていうか、マニアックっていうか」
「そう? 優しそうな先生じゃない。教え方だって上手いし、いい人だって思うけど」
「あんたは男を見る目がないの。あれは駄目。ほんと駄目な部類の人間よ。いい人には違いないんでしょうけど、ありゃモテないわ。四十過ぎて、いまだに独身なんでしょ。それにきっとこれからも独身よ。下手すりゃまだ童貞かもしれないしね」
ひとりで楽しそうに笑い、未玖は腕をつかんできた。
「ま、童貞じゃなかったとしても結婚はできそうにないわ。ね、賭ける? 私たちが卒業するまでにできるか。もちろん私はできない方にするけどね」
賭けるとは言わなかったけど、もしそうしていたら私が勝っていたわけだ。結婚の発表があったとき、部は騒然とした。とくに三年生たちの驚きようは見ていておかしくなるくらいだった。
「マジか! いや、嘘でしょ、先生。そんなはずがない」
「横森、お前はちょっと、――いや、だいぶ失礼すぎるぞ。俺だって結婚くらいできるんだ」
「結婚くらい?」
加藤さんは顎を反らしていた。彼女は背が高く、髪の長い、冷たくみえる目のかたちをした人だった。よく横森さんとしゃべってるので私と未玖はつきあってるものと思っていた。
「先生、その言い方だと結婚がだいぶハードルの低いものに聞こえちゃうけど、そうじゃなかったでしょ」
「あのな、加藤、お前もけっこう失礼だぞ。――まあ、いい。どう言おうとこれは事実だからな。俺は結婚するんだ。しかも、十歳も年下と。これはお前たちのプロットになかったことだろ?」
「証拠は? 先生、証拠はあるんですか?」
「証拠だって? ほんと失礼な奴らばかりだな。どこまで疑うつもりなんだよ」
「だけど、柳田の言う通りだ。先生、そこまで言うなら証拠を見せてよ。ほんとだったら写真くらい持ってるはずだもんな。見せてくれたら信用してやるからさ」
暗澹たる顔つきで新井田先生は首を振っていた。でも、埒があかないと思ったのだろう、スマホを教卓へ置いた。その瞬間に全員が集まった。
「マジか!」
横森さんは同じように叫んだ。
「信じられない。しかも、そこそこの美人だ」
「ほんと。そこそこは美人ね」
「っていうか、お前たちも文章を書く人間なんだから少しは言葉に敏感になれよ。このシーンは恩師が教え子たちに未来の妻を紹介してる件だぞ。『そこそこの美人』ってのはそぐわないと思わないのか?」
不穏当な修飾がついてるものの先生は笑顔だった。私たちは写真を見た後で離れた。西陽があたる教室の隅で未玖はこう言ってきた。
「驚きだわ。まさかってあるのね。――ま、あそこにいる人たちが全員眼鏡ってのも驚きだけど」
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》