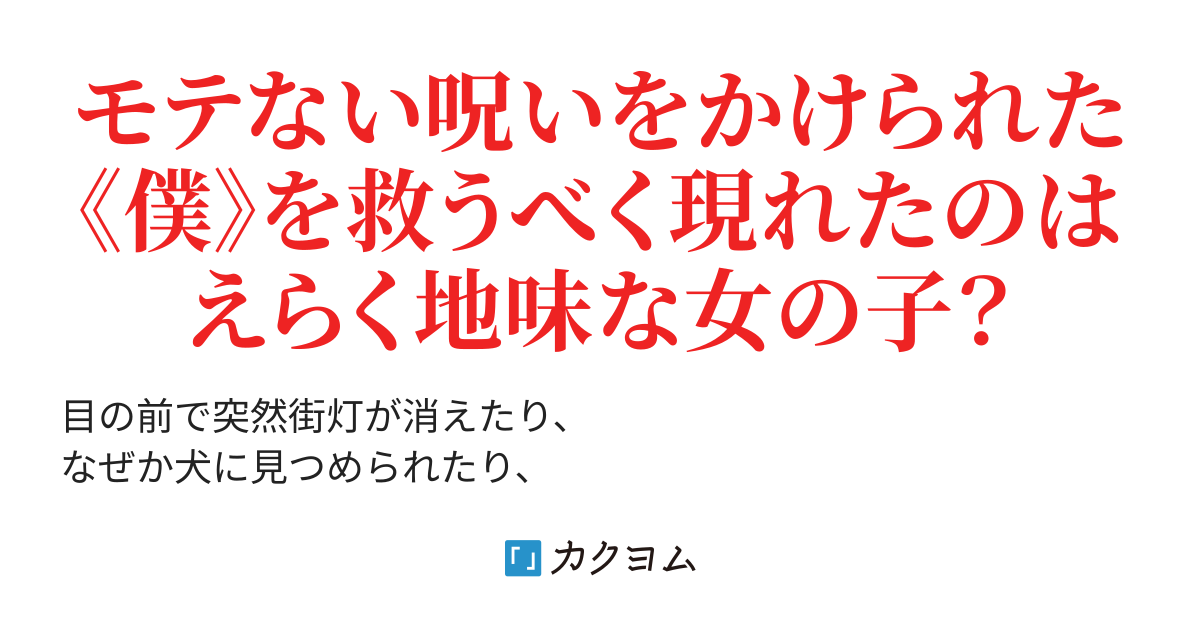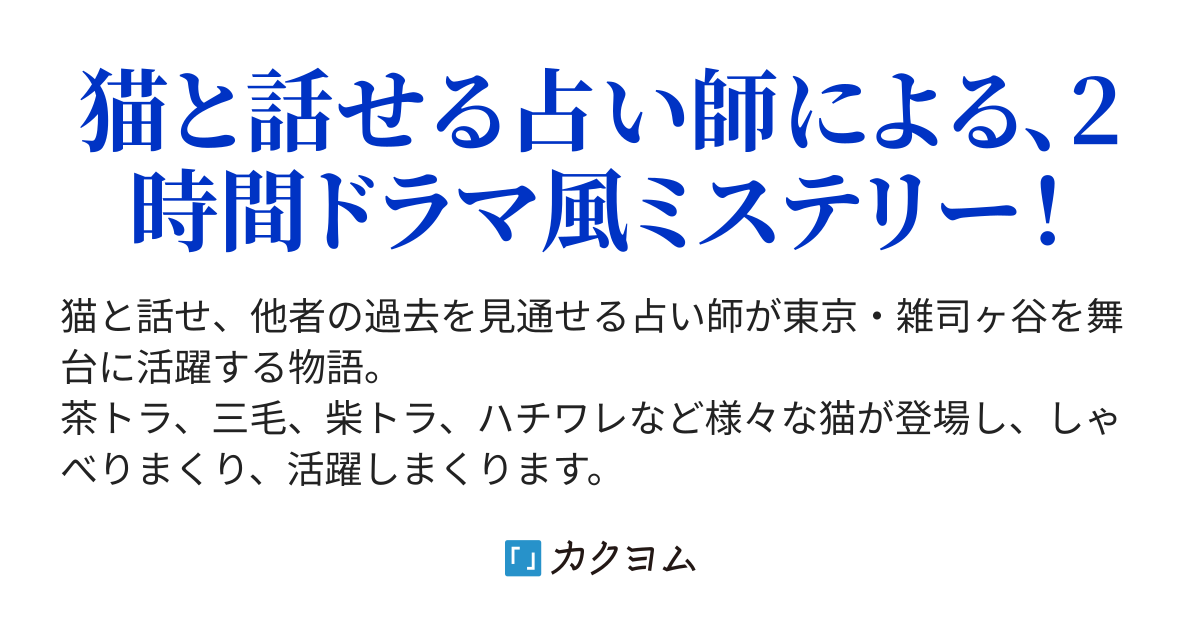それからも二人は話しつづけた。子供の頃のこと(青いネズミについてもだ)、それぞれの初恋がどんなものであり、そしてどうなったのか、などなど。ハーブティがなくなる頃には二人とも疲れきり、なにもしゃべれなくなった。
こういうのってどれくらい振りなんだろう? ミカは記憶をたどろうとした。でも、頭は動かない。ほんと馬鹿な一日。そう思えただけだ。だけど、なにかは乗り越えた。なにを越えたかはわからないけど、とにかく私たちはそれを越えたのだ。
「ありがとう、ミカちゃん」
「いえいえ、どういたしまして」
「私、ミカちゃんと姉妹でよかったわ。いつも迷惑かける姉だけど、これからも仲良くしてくれる?」
「いいわよ。――ま、こういうのが度々あるのは嫌だけどね」
ユキは立ち上がり、にっこり微笑んだ。こうして見るとやっぱり美人だ。瞼が腫れていても、化粧がぐしゃぐしゃになっても美人は美人なんだ。
「ね、お姉ちゃん」
「なぁに?」
「ひとつだけ訊いてもいい?」
そう言ってからミカはすこし迷った。でも、いま訊かなかったらずっと訊かないことになるだろう。それに、この瞬間ならどんな言葉が返ってきても受け容れられる気がする。そう思えた。
「憶えてる? 田崎くんのこと。私が大学生の時つきあってた田崎くん。憶えてるでしょ?」
ユキはゆっくりうなずいた。それから、指先を弄りはじめた。ミカは動く指を見た。顔を見るのはやめにした。見たくないものが含まれてるように思えたのだ。
「彼とお姉ちゃんの間になにかあった?」
指は止まり、また動いた。でも、それだけだった。なにか言おうとしてるのかもしれない。ただ、なにも聞こえない。しばらくミカは指先を見つめていた。静けさはずっとつづいてる。
「いいわ。やっぱりいい」
ミカはそう言った。
「おやすみなさい、お姉ちゃん。明日はキチノスケ様に謝るのよ。わかった?」
一人になるとミカは横になった。天井は遠くなったり近くなったりを繰り返してる。――疲れてるんだな。私は疲れてる。耳を澄ますと、それまで聞こえてなかった音もしてるのがわかった。風の音だろうか? それとも遠い道を走る車の音だろうか? それは大きな歯車がゆっくりゆっくり動いてる音のようだった。
ミカは目を閉じた。それと同時に音も途切れた。まるで本当に一人きりになってしまったみたいだ。壁の向こうにはなにもなく、暗い空間に私だけが漂ってる。無限に刻まれる時の中を漂いつづけ、誰とも交わることなく朽ちていく。――いや、私は疲れてる。眠らなくちゃいけない。そう、眠らなくちゃならないんだ。
―― 完 ――
お読みいただき
ありがとうございました。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》