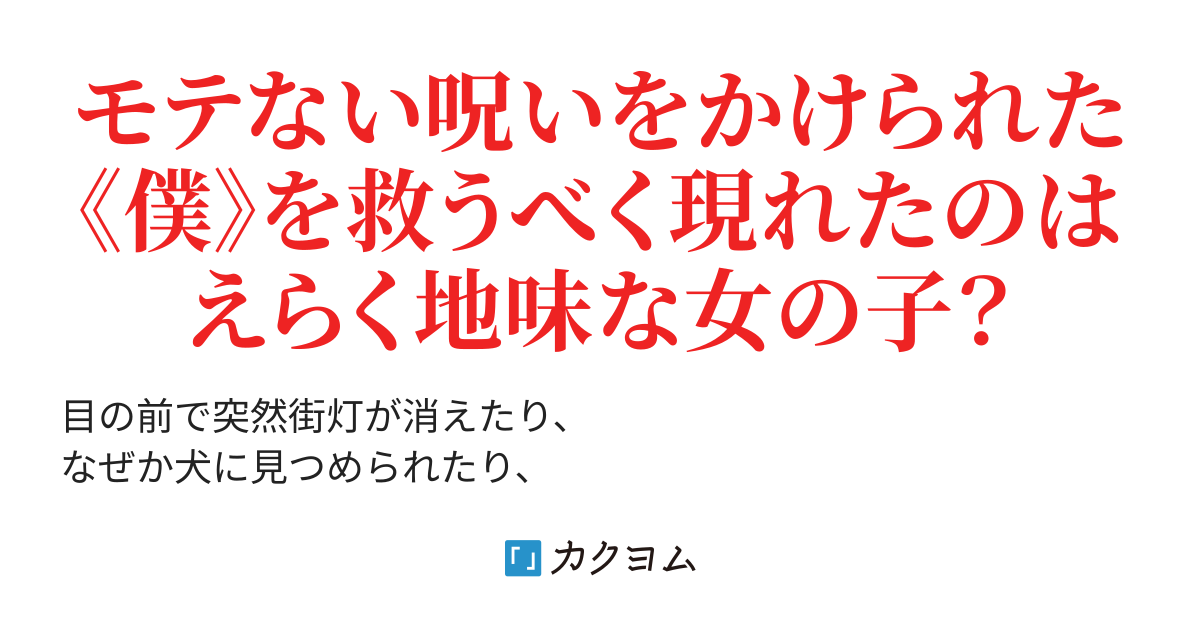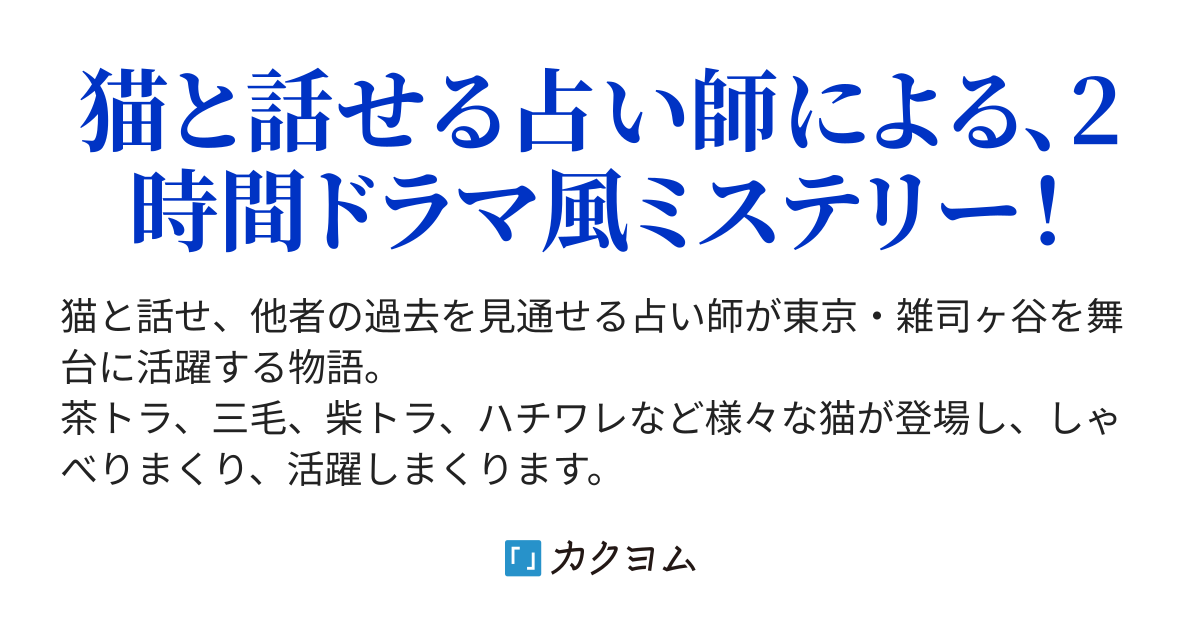休みの日に本を読んでると家の電話が鳴った。電話はリビングにあるものだから気づかないことはよくあった。ただ、その日――十一月頭の月曜日だった――にはしっかり聞こえてきた。ミカはドアを見た。父親と姉は仕事に行ってるし、すこし前に廊下をドスドス歩いていた母親が出かけたら家にいるのは自分だけになる。――しょうがない、出るしかないか。そう思った途端にベルは切れた。
何行か読み進めるとふたたび電話が鳴りはじめた。溜息をつきながら立ち上がり、ミカは部屋を出た。平日の日中にかかってくる電話なんてろくなものじゃないだろう。きっとマンションや健康器具の販売に違いない。リビングに入ると電話はけたたましく鳴っている。しかし、ドアを閉めた瞬間にまた切れた。
「まったく」
読みかけの本は置いてきた。つづきを読みたいけど、この調子だとまた鳴るかもしれない。ミカはソファに座り、テレビをつけた。日は冬のものになりかかり、欅も葉を散らしはじめてる。――もう冬になるんだな。あの木に新たな葉が繁る頃、私はここにいないんだ。
電話が鳴った。
「もしもし?」
「ああ、ミカか。母さんは? 携帯にかけたんだが出ないんだよ。出かけてるのか?」
「知らないわよ。どうせバッグに放り込んだままなんでしょ。で、どうしたの? なにかあったの?」
「いや、よくわからないんだがユキのことでちょっとな」
「お姉ちゃん? お姉ちゃんになにかあったの?」
「いや、ユキになにかあったんじゃない。ユキがしたんだ」
「はあ? どういうことよ。お姉ちゃんがなにしたっていうの?」
「とにかく母さんが戻ったら電話するよう言ってくれ。こっちもまだよくわからないんだよ、なにがなんだか」
母親が戻ってきたのは一時間ほど後のことだった。ぼうっとしたミカを見て驚いたようだったけど、話を聴くと血相を変えて折り返した。
「――はい? ――え? どうして? そんなこと、」
ミカは耳をそばだてていた。これまでにも何度か聞いた調子だ。そのいずれもが悪い報せだった。おじいちゃんの容態が急変したときもこうだったな。私は小学二年生だった。あのときは欅もこんなに大きくなかった。
「――ええ、ええ、わかりました。そうしてみます」
受話器を置くと母親は首を振った。顔は青ざめている。
「なにがあったの?」
「ユキが藤田さんに結婚できないって言ったんだって。どういうことなのかって先方から連絡があったっていうの」
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ 呪われた《僕》と霊などが《見える人》のコメディーホラー(?) ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》