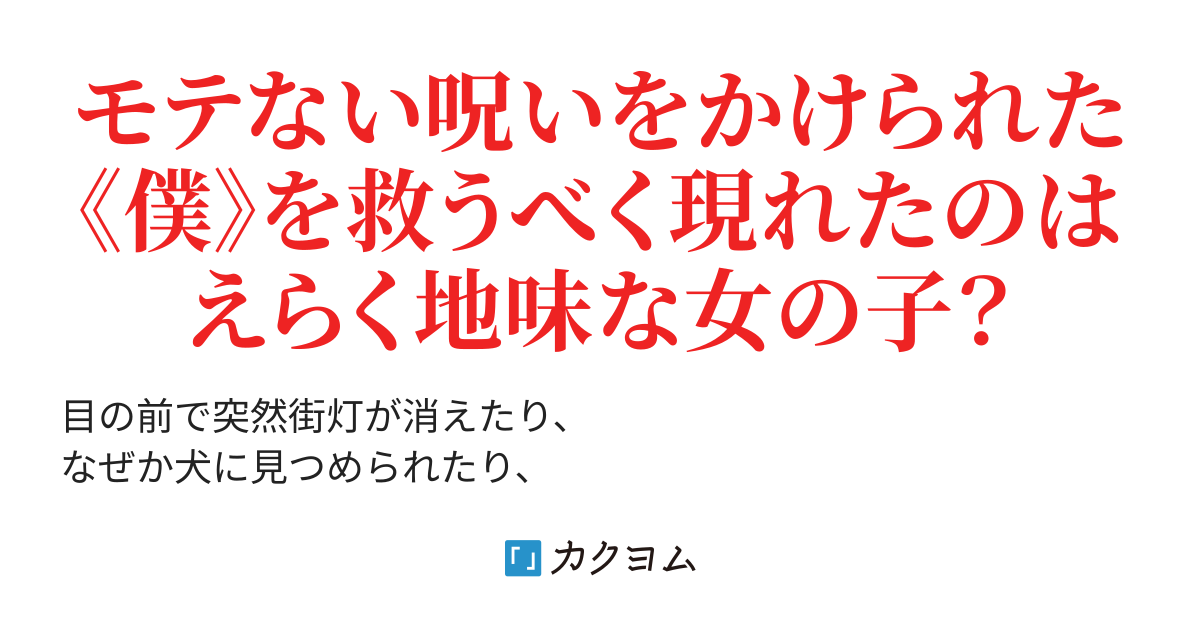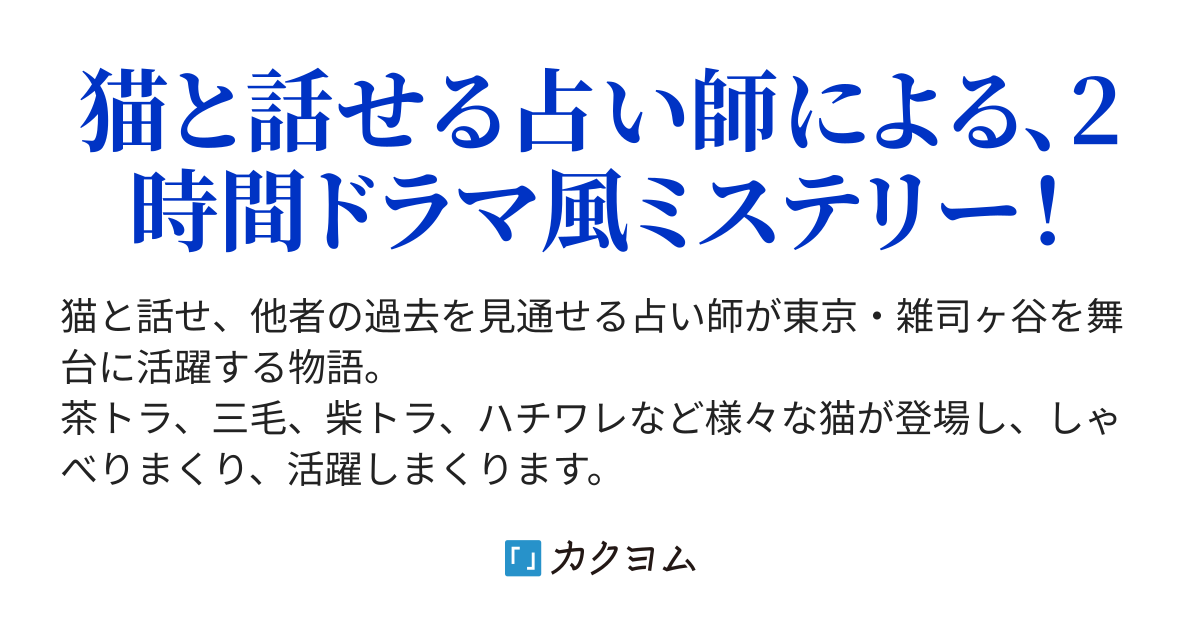「どうした?」
「ん、不思議に思えてな。ほんと、まったく不思議だ」
「なにが?」
「お前のことだよ。モテないはずないんだけどな。タッパもあるし、金だってそこそこ持ってるだろ? ギャンブルもしねえ、女遊びもしねえってんだから貯まる一方だもんな。それに顔だってまあまあだ。それなのになんでいつも振られちまうんだ?」
エレベーターがひらいた。乗りこみながらも小林は話しかけてくる。
「なあ、なんでなんだ?」
「そんなの知るかよ。こっちが教えてもらいたいくらいだ」
「ま、そうだろうけどよ。だけど、ほんと不思議だ。モテないはずがないんだよ。――ん? お前、呪われてんじゃねえか?」
僕は無視することに決めた。エレベーターは各階で停まり、徐々に空いていく。五、六人になったところで、「は?」と思った。じっと見られてる気がしたのだ。
「な?」
ジャケットが引っ張られた。最大限にひそめた声も聞こえてくる。
「あの子だってお前を見つめてるぜ。モテる男のつらいとこだな。熱い視線ってヤツだ」
睨みつけることで僕は黙らせた。それから不自然にみえないよう首を動かしてみた。
隅の方に白いブラウスを着た女の子が立っている。スカートは黒で靴も踵のない黒いもの。銀縁の眼鏡をかけていて、その奥にある瞳はこちらへブレることなく向けられている。
うつむき加減になってるから表情まではわからないけど、あらゆる特徴を消しこもうとしてるのはわかった。しかし、どういうつもりでそうしてるかは別にして消すことのできない特徴があった。えらく背が高いのだ。僕は一八三センチある。それでも視線は仰角になっていない。
僕はまた「は?」と思った。目が向かう先は顔じゃないようだった。左肩を見てるのだ。もしくは、そのすこし上に向けられていた。
「どうしたんだよ、そんな顔して」
「いや、なんでもない」
ドアが閉まる間際に振り向くと、その子は顔を上げていた。頬にかかった髪は払われ、すこしだけ表情が見える。ただ、視線はやはり肩へ向けられていた。
「な、あんな子いたか?」
「ん? 確かに見かけない子だったな。でも、むちゃくちゃ地味だったし、気づかなかっただけかもしれないぜ」
「あんなに背が高いのに?」
小林は目を左上へ向けた。この男には主だった女子社員のプロフィールが埋めこまれてるのだ。しかし、諦めたように首を振った。
「いや、やっぱりわからねえな。思い出せない。もしかしたら新しく入った派遣かもしれねえし。――ま、だけど、今ので自信がついたろ? お前はモテるんだよ。その要素は持ってる。だから、次の合コンにも出た方がいい。うん、こりゃ決まりだ。そうだろ?」
大声で喚きながら小林はトイレへ入っていった。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
↓↓ こちらでも読めますよ ↓↓
《雑司ヶ谷に住む猫たちの写真集》