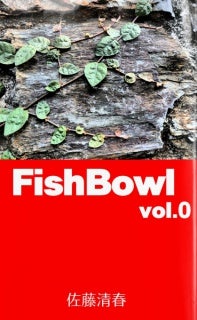母さんたちはほどなくしてFishBowlへ戻ってきた。
そして、武良郎はちょっと妙な歓迎を受けることになった。どこかに母さん以外の面影はないかと皆がかわるがわる穴のあくほど見ていたのだ。実際に父親候補たちと顔をあわせていたのは熊井女史だけだったけど、大人たちは彼らの顔を知っていた。重役っぽいところはないか、教授風の威厳はどこかに具わってないか、もしくは政治家的ないかにも嘘をつきそうな唇のかたちはしてないか――彼らはじっくり武良郎の顔を見つめていた。
「こうなると、誰がほんとうの父親か知りたいって部分もあるな」
井田隆徳はそう言いながら、柔らかい頬を指先で押していた。
「まあ、そうね」
真昼ちゃんもそれに同意した。
武良郎はほとんどいつも笑っていた。様々な顔があらわれては彼にとってあまり面白くもないであろう話をしていたわけだけど、もちろんそんなことに気づくはずもなかった。
ただし、それに気づく年齢になっても、いや、かなり成長して後も、その風潮はやまなかった。彼ほど生まれたときから将来どのような職業に就くかを期待(というか穿鑿というか)されていた者はいないだろう。ビジネスの世界に入るのか、教育者になるのか、それとも政治を志すのか――主にこの三つの職業に集約されていたにせよ、一挙手一投足に至るまでその行為が上に挙げたいずれかの職業に結びつく可能性を見られつづけていたのだ。
これを書いてる時点で、武良郎は二十九歳になった。
兄である僕が言うのもなんだけど、彼は頭も良く、スポーツも万能で、身長も一八五センチあって、顔立ちもいいという、まさに完璧な男に育った。栴檀学園へ入ってからは水泳部に所属して主将も務め、同時に生徒会長もやってのけるという万能振りを発揮させた。大学も僕が入ったのよりうんと良いところだった。たとえどの世界へ向かうにせよ(この頃に至るまで彼の進路は三つのうちのいずれかだろうと思われていた)、どこでもその才能を存分に奮えるだろうと期待されていた。
けっきょくのところ武良郎は俳優になったわけだけど、それはそれで納得のいく結果といえた。
まあ、彼はまだ充分に若いし、今後どのような運命が待ち構えてるかわからないから、父親と目されてる人物たちの仕事に転職する可能性はあるのかもしれない。しかし、彼が初めに選んだのは母親と同じ仕事だった。しかも、俳優の道に誘ったのは母親の新たなる恋人でもあった。そういったことを考えあわすと、家族というものが子供に及ぼす影響は深刻だといえる。まるで自由意志などないかのように自然と敷設された道を進むようにされてしまうのだ。
ところで、武良郎の父親捜し報道は彼が生まれる前に終わっていた。ある圧力から下火になったという側面も――熊井女史が言っていたように――あるのだけど、それがすべてではなかった。
大きな話題が水面下で囁かれていて、それをどう扱うかが芸能マスコミの連中の重大な関心事になっていたからだ。その話題というのは父さんの独立問題だった。母さんが自殺未遂をした直後に父さんの暴力事件があったのと同じように、またしても母さんのゴシップは父さんの話題にとってかわられることになったのだ。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》