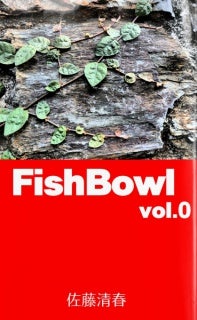母さんの方はというと、嘘のようにすんなり話が進んでいた。
なにより母さんが乗り気だったというのが、そうなった理由の最たるものだった。それまで住んでいた家にいることは母さんにとって苦痛になっていた。どの部屋にも、どの家具にも早乙女氏の思い出が潜んでいた。なにを見ても、なにかを思い出すことになった――食器ひとつにも亡き夫の面影がべっとりとついていたのだ。
このように書くとひどく薄情な人間に思われるかもしれないけれど、母さんは思い出に浸って生きるタイプの人間ではなかった。過去のことは、不満なこと以外は忘れられた(そのかわり不満なことは決して忘れなかった)。そして、早乙女氏との生活には不満が無かった。
唯一不満だったのは自分を残して先に死んでしまったことだった。しかし、それは後追い自殺を未遂で終わらせたことによって、ある程度は解消されていた。自分が死ねなかったのはまだしばらくは生きていろというのを示しているのだろうし、であるならば、くよくよせずに生き抜くのが必要なのだと母さんは考えた。
脩一さんもそれを望んでるはず――母さんはそのように考えられる人間だった。思い込みの強さと行動力だけは人一倍持っているのだ。そういう行動力のある母さんにとっては思い出の色濃く残る家に住み、忘れずにいつづけることの方が苦痛だった。
ただ、問題は自分の自殺が未遂で終わったのには温佳の存在が不可欠だったことを母さんがすっかり忘れているらしいことだった。母さんは自分の娘を(息子である僕に関してもそうだけど)うっかり忘れてしまう傾向があった。温佳が救急車を呼んだり、熊井女史に連絡したことで死なずに済んだのだけど、それは早乙女氏の意思にとってかわられていた。
それについては温佳も母親の性格に馴れっこになっていたので不満は少なかったけれど、自分にまったくなんの相談もなく引っ越しを決めたことには強い不満を感じていた。母さんにとって引っ越しのネックは温佳のその不満だった。
「だって、家に帰ったら段ボールだらけだったのよ。あの人は自分の荷物を全部段ボールにしまっていたわ。それで、あたし、いったいこれはどういうことなのかって訊いたの。そのときに、はじめて引っ越しの話を聞いたの。あまりにもひど過ぎると思わない?」
温佳は今もこのように言っている。
母さんの事務所もこの引っ越しをあまり好意的に捉えていなかったけれど、温佳が反対するより強い態度でひきとめようとはしなかった。
母さんのように始終問題を起こしている女優を抱えていたので、あるいはそういう事態にたいする耐性がついていたのかもしれない。父さんの方は普段の過激な発言とは裏腹に所属タレントとして優等生であったから、暴行事件以降の対処にはほとほと手を焼いていたのだろう。
それに、熊井女史へは真昼ちゃんが直々にこの試みの必要性を訴えてもいた。母さんの状況を改善すること、そして僕や温佳をちゃんとした環境で育てることの必要性をだ。熊井女史も全面的に賛成していたわけではないものの、真昼ちゃんの言う必要性は理解できた。
当然、世間は理解してくれないだろうけど、そのことがさほど重要でないことを熊井女史は知っていた。それに、これ以上なにが起ころうとも早乙女美紗子の名に傷がつくのを気にする必要はなかった――既に傷だらけであり、新たな傷が増えようと誰も気にしないだろうと考えたのだ。
そして、そこまでいけばかえってそれは女優・早乙女美紗子の強みとなった。
![]()
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》