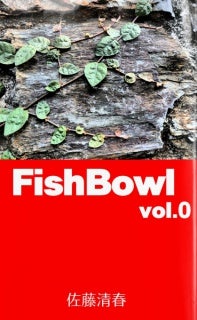喫茶店は混んでいた。僕はカウンターの空いていた席に座り、深煎りのコーヒーを頼んだ。それから、持ってきた本を開いた――『ワインズバーグ・オハイオ』だった。学生の頃に一度読んだだけの古ぼけた文庫本で、まだ持ってるとも思ってなかったものだ。適当にページを捲り、僕はコーヒーを飲みつつ、それを読んだ。ただ、思考はあらぬ方へと進んでいった。突然消える街灯、なぜか見つめてくる犬、篠崎カミラが伝えたかったこと。当然のことに鷺沢萌子のことも頭に浮かんだ。あの天使のような顔。寝顔だって愛くるしかった。僕は悶々と過ごした九日間に幾度もその寝顔を見つめたものだ。あんなことをしでかすとは思えない顔をして彼女は眠っていた。
![]()
僕は本を閉じた。なにかやむを得ない事情があって、結果的に騙すことになったんじゃないか? と考えてみた。たとえば父親がたちの悪い借金を拵え、ヤクザに拉致されてるとか。あるいは母親が不治の病なのかもしれない。緊急手術が必要だけど、それには七十五万もの金が必要だ。それをいったん借りただけというのもありえる。――いや、それじゃ『バーカ!!』の説明がつかない。鍋や食器まで持ちだした理由にもならない。僕はコーヒーを飲み、組みあわせた手に顎をのせた。泣きたい気分になっていた。確かに馬鹿ですよ、と思った。素性も知らない女を部屋に住まわせ、電子レンジまで持ち逃げされたんだから馬鹿には違いない。だけど、僕だっていろいろ訊いてはいたのだ。どこの出身かとか、親兄弟のこと、それまでどこでどのように暮らしていて、いまはどういう状況なのかなどをだ。鷺沢萌子はそれらに全部きちんとこたえた。朗々と淀みなくこたえたのだ。そして、「ちょっと困った状態なの」と言ってきた。
「ルームメイトがいるんだけど、その子が男関係で揉めちゃって、すごくナーバスになってるの。前に勤めてたお店の子なんだけどね、彼女、自殺未遂までしちゃったのよ。相手の男がたちの悪い奴で、私たちのマンションを見張ってるみたいなの。だから、その子も別の友達んとこに身を隠してるってわけ。私もそこに戻りたくないの。もし、ストーカー男に捕まって『彼女の居所を教えろ』みたいなことになったら大変でしょ? そういうわけで、私、帰るとこがないのよ」
コーヒーをちびちびと飲みながら、僕は鷺沢萌子が語ったことを洗いなおしてみた。その上で、瑕疵はない――と思った。ありそうな話だ。まあ、少々ドラマチック過ぎるとは思うけど、納得できる。そして、あのときの僕は完全に納得してしまったわけだ。
「じゃ、うちに来るか?」と僕は言った。ホテルのベッドで僕たちは話していた。二人とも裸で、さらさらした布団にくるまっていた。
「そんな、悪いわ。だって、私たちさっき会ったばかりじゃない」
鷺沢萌子はそのように言ってきた。
「悪いことなんてないよ。そうしてくれた方がうれしいんだ」
僕は天使のような顔を見つめた。彼女も同じように僕を見つめていた。僕たちはそれから唇をあわせた。
「ありがと」
唇を離す瞬間に、鷺沢萌子はそう囁いた。
いまとなってはその名前だってほんとうのものかわからない。出身が秋田だというのも、父親が水産加工の工場を経営してるというのも、大学生の妹がいるというのも、アパレルの店員をしていたというのも全部嘘なのだろう。だから、ストーカー男につきまとわれているルームメイトだって存在しないのだろうし、彼女には帰る場所もちゃんとあったのだ。鍋や皿や炊飯器は売り払い、僕のことを「バーカ!!」と思いながら札束を数えているのだ。
なんだか本格的に泣きたくなってきた。僕は天井を見つめながら首を弱く振った。部屋に戻り、片づけを再開しよう。心的な外傷にとらわれていては駄目だ。立ちなおるのだ。よし、小林がセッティングしつつある合コンに行こう。そこで新たな天使を見つけてやるんだ――そのように僕は考えた。その思いが強すぎたのだろう、カウンターから店員が教えてくれるまで声をかけられていることに気づかなかった。僕は振り向いた。それから首を思いっきり上げた。そこには篠崎カミラが立っていた。
「あっ、あっ、あの、」と彼女は言った(たぶんずっとそう言っていたのだろう)。
「篠崎さん?」
僕はそう言ってから辺りを見渡した。彼女は「そうです。私は篠崎カミラです」とでもいうように激しくうなずいていた。あとをつけられているんじゃないか? と僕は思った。この店で会社の人間と出会したことなんて一度もなかったのだ。
「あっ、あっ、あの、わ、私、び、び、びっくりしました。だ、だって、さ、佐々木さんが、い、いるって、い、いままで、き、き、気づかなかった、も、ものですから」
「ってことは、君は前からここにいたの?」
僕はそう訊いた。彼女はまたもや激しくうなずいた。
「そ、そ、そうなんです。も、もう、か、帰るとこなんです。きょ、今日は、せ、せ、先生と、いっ、い、一緒で、」
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》