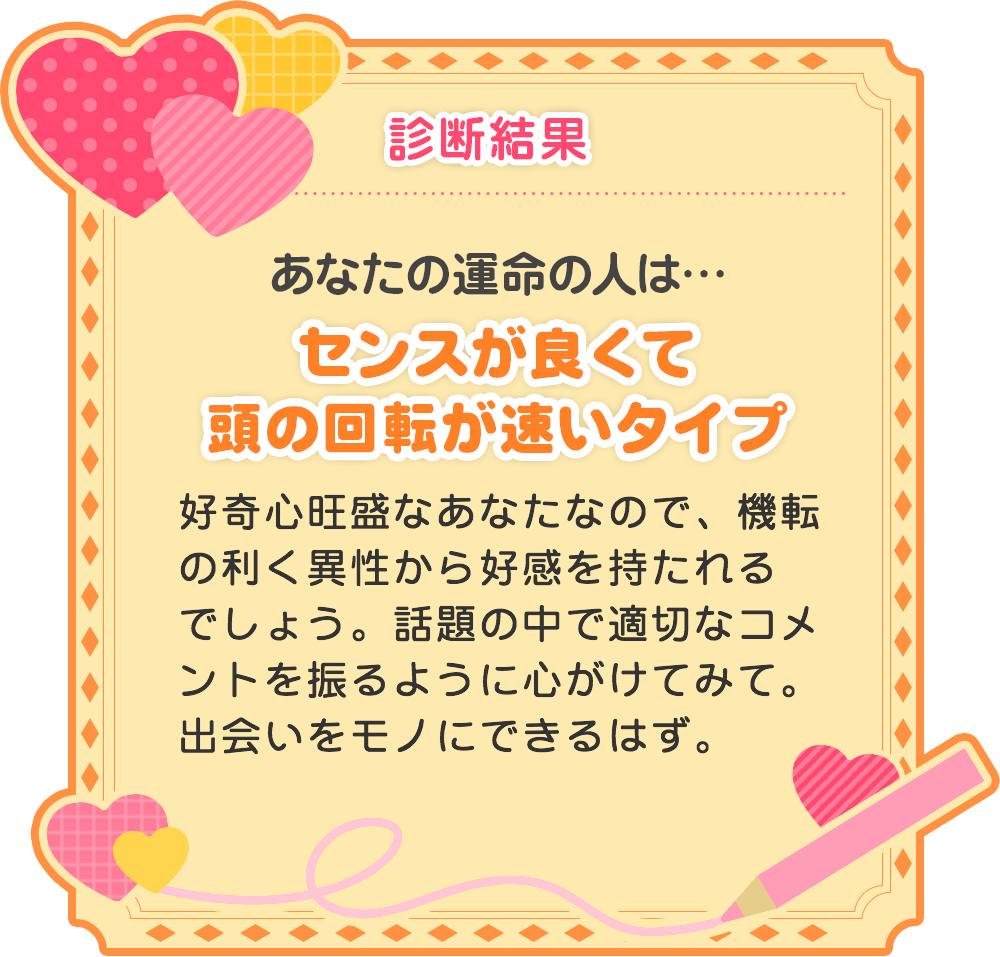放課後の始まる、午後4時前。
最後の時限が終わる、チャイムが鳴り響く。
バラバラにバイバイ。とか、じゃあね。とか。
中には、今日の部活の話をしている生徒もいる。
僕は、ホームルーム教室を後にして、 階段をゆっくり登った。
ひゅいっと風が抜ける。前髪を掠める。
屋根の無い渡り廊下を渡って、シルバーの重い戸を開いて入る。
風が、閉めようとした戸を、バン!と閉じて、その大きな音に、肩を震わせる。
ああもう、びっくりした。
まあ、それはともかくとして、そこから、しばらく進んでいった先に、その教室はあった。
風通しが無駄に良くて、夏はともかく、すっかり涼しくなった今では、むしろ寒いぐらい。
——化学教室——
そう書かれたプラカードが、上から見下ろしている。
逆に言えば、僕はそれを見上げる形になる。今更見上げないけど。
ガラガラ、と引き戸を開くと、後ろから風が吹き込む。
あっ、これはアレだ
。教室内が暖かいから、空気の密度の違いで、空気が移動するやつだ。
そんなことを考える以前に、僕に声が掛けられた。
「あ、加賀見君いらっしゃい。寒いからすぐに閉めてもらえる?」
「ああ、はい。」
戸を言われるままに閉じる。
まあ、閉じたくない理由は特に無いから、言われるままっていうのも語弊があるかな。
「…先生。他のみんなはまだですか?」
「そうね。あなたが最初じゃない?多分、もう少しすると…」
——ガラガラッ——
「失礼します!あ、加賀見君!早いね」
「そうかな。そうだね、多分」
この部活、理学部には、クラスメイトが数人所属している。
クラスだと、そんなに話さないけど、放課後の部活のこの時は、自分から話題を出せる。楽しい時間だった。
それと、本当は理学部じゃないらしいけど、また別に一人いた。
「住友君、今日遅いね」
「そうかな」
「そうだよ。いつも早いから…大体最初にいるでしょう?」
「…そうだね」
クラスメイトの女子、学級委員長でもある、木ノ瀬菜々穂と何気無く話していた。
すると先生が、話に入ってくる。
「確か、学校内で蛇見つけたとか言っていたみたいだけど」
「えっ、蛇?」
「そう。本人曰く、毒は無い種類らしいけど…」
「つまり、それって…」
いつもの彼なら、おそらく、蛇を——
「捕まえたら、ここに持ってくるでしょうね」
「…」
その時、引き戸が開く音が聞こえた。
「…おい住友。これどうしたらいい」
「そのまま持って、中へ」
「ふざけんなよ、まだ生きてるんだぞ?」
「あまり弱らせるな」
「何で俺が…」
そこには、背の高い男子と、それと並んでしまうと、小さく見えてしまうもう一人の男子が居た。とはいっても、僕はもっと小さいんだけど。
木ノ瀬さんは、小さい方の男子に聞いた。
「…住友君。捕まえたの?」
「…開く。」
「え?」
「コイツを開く。」
「…やっぱり?」
ああ、やっぱりだ。彼の頭には大体それしか無い。
生き物に興味がある、と言えば、まだ理解されるかもしれない。しかし、彼の場合は少し特殊だ。
彼は、生き物の身体の造り、及び骨格自体に興味がある。だから彼は、生き物を捕まえては、"開く"のだ。
つまり、それは"解剖"する、ということ——
「佐野、押さえろ、動かないように。あまり押し潰すなよ」
「それかなり高度な技術要らないか?というか噛まれるのは嫌だぞ、俺」
「チッ…なら仕方ない…」
先程から蛇と格闘している二人——捕まえ押さえているのは主に背が高い方なのだが——は、洗濯ネットらしき物に入った蛇を囲んで、何やら話している。
ちなみに、背が高い方が、隣のクラスの佐野定義。読み方はサノサダヨシだから注意。あと、理学部でもなんでもない。
背が低い方が、そう、彼が住友君。住友輝聡。こちらもなかなか難読でスミトモテルアキ、と読む。蛇足だけど、「輝聡」
っていう二文字は、どちらも「アキラ」と読めるので、「アキラアキラ」になるんじゃないかってことに気付いたことがある。
と、名前記憶スキルを頭の中で披露しながら、僕はボサッと突っ立っていた。
住友君は、持っていたカバンから、いつも持ち歩いている"白いケース"を取り出して、ケースのロックを外した。
中には、小振りのナイフやら、注射器やら。まるで医者の持ち物みたいだけど、その中から注射器を取り、また別に針を取り付ける。
洗濯ネットの中で蠢くそれに、慣れた手つきで針を刺した。
注射器の中身が空っぽになったかと思うと、しばらくして洗濯ネットの中は大人しくなった。
「最初からそれやれば良かっただろ。出し惜しみか」
「出来たら消費はしたくなかった。取り寄せるのが面倒だ」
僕は動かなくなった蛇を覗き込みながら、なんとなく話しかけた。
「…死んだ?」
「麻酔。」
「へえ…そうなんだ」
さて、そんなこんなで、今日も住友君の解
剖は始まる。
さっきの"白いケース"は、僕らは勝手に"解剖セット"とか呼んで、恐れ親しんでいる。ちなみに、勝手に触ると怒られる。
「骨が多いな、魚みたいだ」
「静かに。気が散る」
「あいあい、素人は口出すなーってか」
蛇をキレイに開きにしている様子を佐野君が物珍しそうに見ている。
「さて、皆さん。理学部の皆さん。集まった?集まったみたいね」
先生が、理学部の注目を集めた。
——尚、住友君は、全く反応していない。厳密には、彼は理学部に所属しているわけではないからだ。
「今回の活動内容は、ちゃんとあるので…そこ!実験器具で遊ばない!いつも言ってるでしょ?危ないから…え?生物部がフリーダム過ぎる?仕方無いでしょ幽霊部員だらけなんだから…」
「先生、話逸れてます」
先生は、あー、と一声、後に咳払いを添えて、話を続けた。
「今回は——」
さて、今日の理学部の活動は、下校時刻の到来
によって終了。みんなは帰り支度をしていた。もちろん、僕だって。
でも、生物部は、そうはいかない。本人が納得するまで、なかなか終わらない。
それだけに、彼の標本のクオリティは高いのだけど。
僕は、彼のすることには少し共感できた。僕も生物の授業は好きだし、どうなっているのか知りたい、という探求心は、とてもよくわかる。
僕だって、知りたい、近付きたい、みたいな、好きなものはあるんだ。
「みんな帰るけど…住友君は?まだ帰らないの?」
木ノ瀬さんが手に教室の鍵を持って聞いた。
「まだ掛かりそうだから放っておいてくれ」
「…わかった。じゃあ、鍵置いておくね」
木ノ瀬さんは、住友君の使っている机の端に鍵を置いた。
カシャリ、と寂しそうな音がした。
そして、木ノ瀬さんは教室を出て行った。
ああ、木ノ瀬さんは同じクラスに仲の良い友達がいたっけ、一緒に帰るのかな…あの美人な子と——
「…」
ふと気が付いた。
僕はなんだ
かんだ、残ってしまっていたのだ。
それも、あの住友君も。
佐野君は、生徒会の集まりがあるからと、早々に立ち去っていた。
暖房の切られた化学教室に、二人残ってしまったわけである。
「…住友君。見てても、良い?」
「…」
「あ、僕さ、医学系とか目指してて、選択も生物だし…その、そういうの、ちょっと興味あってさ、だから…」
自分でも何を言っているのかわからない。
でもこれだけは確実だ。僕は住友君の作った標本のファンだ。
ずっと、作る工程を見てみたかった。でも、なかなかじっくり見る時間も無かった。
しばらくしても、返事が無かったので、「あっ、邪魔だよね、ごめんね」と言って立ち去ろうとした時だった。
「…別に構わない。でも、もう終わる」
答えて、くれた…!
「ああ、そうなんだ。ちょっと残念だな」
僕は、ゆっくり微笑んだ、と思う。
接点はあるけど、しっかり話したことのない彼に、少しだけ、認めてもらえた気がした
から。