こんばんは。
日刊サイゾー からの転載です。
本文は長いので抜粋します。本文はこちら
誰がアニメを変えたのか? 世代論で切るオタク文化の10年、そして50年
はたしてアニメはどこから来てどこへ行くのか。名称には「10年」を掲げながら、じつは日本アニメの深層がどこにあり、そこからの50年を経て、現在にいかに影響を及ぼしているかを問うシンポジウムが、去る12月6日に明治大学駿河台キャンパスで催された。
オタクが愛好するアニメ的なものとは、アニメ、マンガ、ゲーム、はてはライトノベルまで幅広い。森川氏はこのシンポジウムにいかなる名称を付与すべきか慎重な論議があったことを述べていたが、実際の内容はほぼアニメについて、だった。
■すべてのアニメは「厨二病」的である!?
基調講演のメインフレームは、アニメが徐々にオタクのものになっていくその根源を探るもの。冒頭、森川氏は1996~97年の『エヴァ』ブームから始まる「セカイ系」の台頭を引き合いに出し、まず、アニメ自体が「厨二病」的であり、厨二病的資質の人、あるいはリアルに中学二年生以下の若者に向けたメディアであることを喝破する。
そこで問題になるのが、各年代における「中二(14歳以下)人口」である。
■「少子化」がアニメの訴求対象をシフトさせた
次の波がアニメだった。74年の『宇宙戦艦ヤマト』に始まるアニメブームは多くの若者を巻き込む。サブカル誌「OUT」が特集を組み、のちにアニメ専門誌へと変貌していくほどのパワーがあった。森川氏はこの衝撃を「STUDIO VOICEがエヴァ特集号を発行した時に似ている」と、昔を知らない人にもわかりやすく表現したが、つまり当時はまだアニメはオタクのものではなく、高感度でカッコイイ若者文化になりうる可能性があったのだ。
■2010年、アニメは半減する!?
まず話題に上ったのはアニメのデジタル化だった。90年代から00年代にかけてアニメがデジタル制作へと移行。撮影や特殊効果の分野ではそれまでの技術が使えなくなり、店をたたむか否かを迫られた作り手も少なくなかったという。その後、色調がギラつきすぎていて画面になじまないなどの課題を克服して現在に至るが、制作コストは悩みどころらしい。
本文で何が言いたいかというと…
一体アニメと言うのはこれからどこに行くのか?という事。
根本的にはアニメというものが子供の物から大人のモノになり深夜枠に移動していったのが原因です。
表現が比較的緩い時間帯だとは思いますが…
多分今が分水嶺なんだと思います。
技術が進化しても本質が変わらなければ面白い物ができるはずもなく、ましてや売上に繋がらない。
面白い作品は何時までも話題になりますし、今年の作品でももう忘れ去られるものもありますね。
結局萌えというものだけに頼り切っても駄目ですし、作品内容だけに偏っても駄目、原作ばかりに頼ると資産が食い尽くされて次が作れなくなる。
来年は色々淘汰されてくるんでしょうね。
- 化物語 第四巻 / なでこスネイク【完全生産限定版】 [Blu-ray]/神谷浩史,花澤香菜

- ¥7,350
- Amazon.co.jp
- けいおん! 6 (初回限定生産) [Blu-ray]/豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美
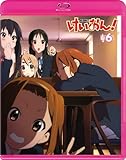
- ¥7,980
- Amazon.co.jp