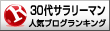◇◆◇
先日からの大雨、ほとほと嫌になった、なんて方もおられるかもしれない。
いや、それどころじゃない。避難しなければならなくなったり、河川の氾濫で家が浸水してしまったという方もおられる。お見舞いの言葉しかない。
一方で、これからさらに忙しくなる土木技術者の方々もおられるだろう。災害復旧のための調査や測量、設計、災害査定など、やらなければならないことがこれから山となって現れる。
SNSでも、どこどこが崩れたとか、水が溢れたとか、さまざまな情報が出ている。一方で、このような記事もある。
この記事にもあることだが、山は崩れるものだ。
土が集合体となって均衡を保っているから静かに鎮座しているわけで、土の粒子の間に水が入り込んでしまったら、均衡は崩れる。バランスが崩れる。水が入り込むことで、それまで動いてなかった土の粒子が動きやすくなってしまう。水が動けば土も動いてしまう。
そして、避難するかしないかの判断材料として、とてもわかりやすい。以下の4つのうち、いずれかに当てはまる方々は、要注意ということである。
1,家の裏に法面(崖)を持っている方
2,自宅の上に他者の土地の法面(崖)が有る方
3,周囲に以前崩壊して法面保護工事がしている山がある方
4,法面保護工事から数百m程度離れている方
◇◆◇
ここで、思わずうなづいてしまった内容がある。
「法面保護などの対策工事を行なった箇所は、かつて崩れたか崩れる可能性が大きいため対策をした」
ということである。
対策というのは、必要があるからやるわけだ。必要のないところに対策を施す必要はない。対策が必要ということは、必要である理由や背景が存在する。法面対策を実施したということは、崩れるかもしれないから対策が必要となったから、対策工事をしている。
ここで忘れてはならないのは、
「対策をしたから大丈夫なのではなく、対策をした箇所の周りが崩れるかもしれない」
ことだ。
山全体に対策をすればいいのかもしれないが、あまりにもお金がかかりすぎる。時間もかかる。現実的ではない。
そこで、弱いと思われる箇所を抽出して優先順位をつけ、対策をやる。対策をした箇所はいいがらその隣りや周りが無対策となっていたら、そこが大雨などによってやられてしまう可能性がある。
だから、対策工事をしたところも、気をつけないといけない。
◇◆◇
崩れないようにするのが、土木技術者の仕事である。とはいえ、自然相手の仕事であり、完全に抑え込むことはできない。想定したより遥かに大きな力がかかり、崩れてしまうことがある。予想以上の豪雨により、やられてしまうことがある。
どこまで想定するのか、根拠をしっかりつけて明らかにするのは難しい。どこかで落とし所をつけないといけない。
お金は無限にあるわけではないから。
そして、どんなに強靭な対策をしても、それでもやられてしまうことがある。
山は崩れるものなのだ。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◇◆◇
こちら、クリックをしてくれると
飛び上がって喜びます(*≧∀≦*)
◇◆◇
直接のお問い合わせは、
下記アドレスへお願いします。
tadashiprosta@gmail.com
※こちらもリクエスト・フォロー大歓迎です。
Facebook:https://www.facebook.com/htadash
Twitter:https://twitter.com/togura33