一般質問その③です。
この質問は増え続ける社会保障費について、
少しでも何かできればという想いです。
社会保障費、医療費についてはセンシティブな領域ではありますが、
(先日某ブログが炎上していましたし)
避けては通れないと思っています。
また、「エビデンスにもとづく政策(Evidence-Based Policy)」
をどこかの分野からでも導入していってはどうかという話です。
枚方市の国民健康保険会計の中での
医療費で一番費用が掛かっているのはがん治療です。
がんは検診を受けることで早期発見早期治療ができます。
しかし、検診の受診率が低い・・・(国の目標にはほど遠い)
そこで、コチラ
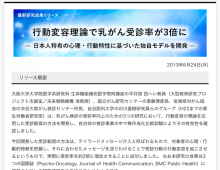
↑
参照元はこちらです。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/06/20130624_1
他市の自治体で健診の受診率が3倍になった事例を紹介しつつ、
同じような手法を導入してはどうかと提案いたしました。
【質問】
健康寿命の延伸を実現させるために様々な取組みが進められておりますが、一方で、高齢化、医療の進歩などを背景に医療費は高騰を続けています。
最近では、高額な治療薬が保険適用となり、特にがん治療における医療費は高額となる場合もあると聞いていますが、国民健康保険の医療費分析においては、がんにかかる医療費はどのような状況ですか。
【答弁】
本市国民健康保険の平成26年の医療費分析では、調剤・歯科を除く医科の診療費の総額は約224億8,500万円です。その診療費のうち「がん」は約35億9,800万円で、高血圧などの「循環器系の疾患」は約35億9,500万円と共に全体の16%を占めています。
また、がん治療にかかる入院、外来のレセプト1件当たりの医療費平均は、
約12万円で、循環器系の疾患の約3万円と比べて高額となっています。
【質問】
国民健康保険の中での、がんにかかる医療費についてお聞きをいたしましたが、全体で200億円超えという費用も膨大ですが、そのうち、がん治療が、約36億円と診療費の多くを占めているということです。
がん治療は、医療費への影響だけではなく、長期の療養や副反応の強い治療によりQOLの低下を招くことから、健康寿命の延伸という観点からも、早期発見・早期治療が重要であると考えます。
そこで、がんの早期発見には検診が有効だと思います。国もがん対策基本計画をたて、目標値を定めているかと思います。市のがん検診受診率の現状および目標値についてお伺いします。
【答弁】
平成27年度のがん検診の受診率は胃がん6.2%、肺がんは19.6%、大腸がんは22.4%、乳がんは30.2%、子宮頸がんは34.2%となっております。
がん検診受診率の目標値については、国と同じ値を設定し、胃がん・肺がん・大腸がん検診は40%、乳がん・子宮頸がん検診が50%としております。対象者は、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診については、40歳から69歳、子宮頸がんは20歳から69歳として算出しています。
【質問】
現状では目標に到達していないようですが、受診勧奨案内の通知文書の工夫などをすることで、受診率が向上している地域もあると聞いています。例えば、関東の自治体においては、大学・医療機関との共同実施により、行動変容の理論を応用した受診勧奨の方法を開発し、自治体の検診事業の中で実際に受診率を約3倍に増加させることに成功。対象者の心理・行動特性を考慮しない従来通りのメッセージ(コントロール群)に比べて、対象者の心理・行動的特徴を把握し、それに合わせたメッセージを送りわける方が、(テイラードメッセージ介入では)受診率が統計的に有意に高く、約3倍になったという結果が得られております。
(受診率:コントロール群5.8%に対してテイラード介入群19.9%)。
このような取り組みをし、受診率を向上させている自治体もありますが、枚方市の受診率の向上にむけての取組を教えてください。
【答弁】
がん検診の受診率向上にむけての取り組みとしましては、がん検診推進事業として一定の年齢の人に無料クーポン券を送付している他、広報やホームページなどでがん検診の周知を行っております。新しい取組としては、事業者との包括連携協定に基づき生命保険会社の外交員が、がん検診の受診方法等を個別にお知らせするなど、連携しながら周知啓発に努めているところです。
【質問】
目に触れる機会を増やすことも大事であると思いますが、先ほどのように、どのようなメッセージを送るかも非常に大事です。先ほどの関東の自治体の事例ですが、ランダム化比較試験(RCT)によりその有効性を確認しております。
「ランダム化比較試験」は英語で(Randomized Controlled Trial)でRCTといわれております。これは、もともと自然科学でよく用いられてきた分析手法です。例えば新薬の効果を測定する場合、新薬を投与する処置群と、プラシーボを投与する対照群に、被験者をランダムに振り分け、両グルームのアウトカム指標を比較することで新薬の効果を測定する方法がRCTです。被験者をランダムにグループ分けすれば、それ以外の要因を排除し、正確な因果関係を推定できます。
RCTには適した施策と適さない施策があるとされ、RCTの必要性が高く、実行可能性も高い施策としては、税・保険料等の滞納予防や医療・健康、教育プログラム、就労支援などが挙げられております。
このようにRCTを導入し、無作為抽出により、対象の母集団を2つに分け、受診率向上に効果的な受診勧奨案内をそれぞれ送付し、どちらの方がより受診する人が多かったのかについて検証するなど、受診率の向上に向けた取り組みの導入について、市の見解を伺います。
【答弁】
受診率向上は大きな課題と認識しており、引き続き効果的な方策を検討してまいります。
【意見要望】
ぜひともご検討いただきたいと思います。
このRCT(ランダム化比較試験)は政策目的を達成するために効果的な施策を科学的根拠に基づいて意思決定する「エビデンスにもとづく政策(Evidence-Based Policy)」の中で活用されている手法です。エビデンスに基づく政策は、欧米の先進国で急速に導入が進んでおり、さらに開発援助を通じ途上国にも展開されております。しかしながら、日本ではいくつかの政策分野をのぞき実践例はごくわずかです。医療機関や大学などとも連携し、こういった手法も全国の自治体に先駆けて取り入れつつ、効果的に受診勧奨をすることにより医療費の抑制につなげていただきたいと要望をしておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枚方市議会議員
木村亮太(きむらりょうた)公式サイト
http://kimura-ryota.net/
ご連絡はこちらにお寄せください。
hirakata@kimura-ryota.net
ツイッターアカウント
→@kimura_ryota
未来に責任
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この質問は増え続ける社会保障費について、
少しでも何かできればという想いです。
社会保障費、医療費についてはセンシティブな領域ではありますが、
(先日某ブログが炎上していましたし)
避けては通れないと思っています。
また、「エビデンスにもとづく政策(Evidence-Based Policy)」
をどこかの分野からでも導入していってはどうかという話です。
枚方市の国民健康保険会計の中での
医療費で一番費用が掛かっているのはがん治療です。
がんは検診を受けることで早期発見早期治療ができます。
しかし、検診の受診率が低い・・・(国の目標にはほど遠い)
そこで、コチラ
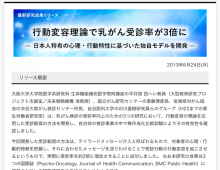
↑
参照元はこちらです。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/06/20130624_1
他市の自治体で健診の受診率が3倍になった事例を紹介しつつ、
同じような手法を導入してはどうかと提案いたしました。
【質問】
健康寿命の延伸を実現させるために様々な取組みが進められておりますが、一方で、高齢化、医療の進歩などを背景に医療費は高騰を続けています。
最近では、高額な治療薬が保険適用となり、特にがん治療における医療費は高額となる場合もあると聞いていますが、国民健康保険の医療費分析においては、がんにかかる医療費はどのような状況ですか。
【答弁】
本市国民健康保険の平成26年の医療費分析では、調剤・歯科を除く医科の診療費の総額は約224億8,500万円です。その診療費のうち「がん」は約35億9,800万円で、高血圧などの「循環器系の疾患」は約35億9,500万円と共に全体の16%を占めています。
また、がん治療にかかる入院、外来のレセプト1件当たりの医療費平均は、
約12万円で、循環器系の疾患の約3万円と比べて高額となっています。
【質問】
国民健康保険の中での、がんにかかる医療費についてお聞きをいたしましたが、全体で200億円超えという費用も膨大ですが、そのうち、がん治療が、約36億円と診療費の多くを占めているということです。
がん治療は、医療費への影響だけではなく、長期の療養や副反応の強い治療によりQOLの低下を招くことから、健康寿命の延伸という観点からも、早期発見・早期治療が重要であると考えます。
そこで、がんの早期発見には検診が有効だと思います。国もがん対策基本計画をたて、目標値を定めているかと思います。市のがん検診受診率の現状および目標値についてお伺いします。
【答弁】
平成27年度のがん検診の受診率は胃がん6.2%、肺がんは19.6%、大腸がんは22.4%、乳がんは30.2%、子宮頸がんは34.2%となっております。
がん検診受診率の目標値については、国と同じ値を設定し、胃がん・肺がん・大腸がん検診は40%、乳がん・子宮頸がん検診が50%としております。対象者は、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診については、40歳から69歳、子宮頸がんは20歳から69歳として算出しています。
【質問】
現状では目標に到達していないようですが、受診勧奨案内の通知文書の工夫などをすることで、受診率が向上している地域もあると聞いています。例えば、関東の自治体においては、大学・医療機関との共同実施により、行動変容の理論を応用した受診勧奨の方法を開発し、自治体の検診事業の中で実際に受診率を約3倍に増加させることに成功。対象者の心理・行動特性を考慮しない従来通りのメッセージ(コントロール群)に比べて、対象者の心理・行動的特徴を把握し、それに合わせたメッセージを送りわける方が、(テイラードメッセージ介入では)受診率が統計的に有意に高く、約3倍になったという結果が得られております。
(受診率:コントロール群5.8%に対してテイラード介入群19.9%)。
このような取り組みをし、受診率を向上させている自治体もありますが、枚方市の受診率の向上にむけての取組を教えてください。
【答弁】
がん検診の受診率向上にむけての取り組みとしましては、がん検診推進事業として一定の年齢の人に無料クーポン券を送付している他、広報やホームページなどでがん検診の周知を行っております。新しい取組としては、事業者との包括連携協定に基づき生命保険会社の外交員が、がん検診の受診方法等を個別にお知らせするなど、連携しながら周知啓発に努めているところです。
【質問】
目に触れる機会を増やすことも大事であると思いますが、先ほどのように、どのようなメッセージを送るかも非常に大事です。先ほどの関東の自治体の事例ですが、ランダム化比較試験(RCT)によりその有効性を確認しております。
「ランダム化比較試験」は英語で(Randomized Controlled Trial)でRCTといわれております。これは、もともと自然科学でよく用いられてきた分析手法です。例えば新薬の効果を測定する場合、新薬を投与する処置群と、プラシーボを投与する対照群に、被験者をランダムに振り分け、両グルームのアウトカム指標を比較することで新薬の効果を測定する方法がRCTです。被験者をランダムにグループ分けすれば、それ以外の要因を排除し、正確な因果関係を推定できます。
RCTには適した施策と適さない施策があるとされ、RCTの必要性が高く、実行可能性も高い施策としては、税・保険料等の滞納予防や医療・健康、教育プログラム、就労支援などが挙げられております。
このようにRCTを導入し、無作為抽出により、対象の母集団を2つに分け、受診率向上に効果的な受診勧奨案内をそれぞれ送付し、どちらの方がより受診する人が多かったのかについて検証するなど、受診率の向上に向けた取り組みの導入について、市の見解を伺います。
【答弁】
受診率向上は大きな課題と認識しており、引き続き効果的な方策を検討してまいります。
【意見要望】
ぜひともご検討いただきたいと思います。
このRCT(ランダム化比較試験)は政策目的を達成するために効果的な施策を科学的根拠に基づいて意思決定する「エビデンスにもとづく政策(Evidence-Based Policy)」の中で活用されている手法です。エビデンスに基づく政策は、欧米の先進国で急速に導入が進んでおり、さらに開発援助を通じ途上国にも展開されております。しかしながら、日本ではいくつかの政策分野をのぞき実践例はごくわずかです。医療機関や大学などとも連携し、こういった手法も全国の自治体に先駆けて取り入れつつ、効果的に受診勧奨をすることにより医療費の抑制につなげていただきたいと要望をしておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枚方市議会議員
木村亮太(きむらりょうた)公式サイト
http://kimura-ryota.net/
ご連絡はこちらにお寄せください。
hirakata@kimura-ryota.net
ツイッターアカウント
→@kimura_ryota
未来に責任
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━