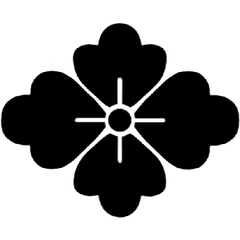No.274 2025年4月面足尊・惶根尊の扇祇神社トレッキング資料
宮原誠一の神社見聞牒(274)
令和7年(2025年)04月19日
2025年(R7)4月20日 10時
集合場所 坂本八幡宮駐車場
福岡県太宰府市坂本3丁目14
西鉄電車利用者は都府楼前駅で迎えに行きます
1.浄妙尼社 福岡県太宰府市朱雀6丁目15−7
2.王城神社 福岡県太宰府市通古賀五丁目8-40
3.春日神社 福岡県春日市春日一丁目110
4.古賀の扇祇神社 福岡県筑紫野市古賀738
5.萩原の扇祇神社 福岡県筑紫野市萩原708
6.大歳神社 .. 福岡県筑紫野市山口1924
予.上古賀若八幡宮 福岡県筑紫野市上古賀4丁目3-7
(昼食)ジョイフル原田店 筑紫野市原田7丁目1−1
面足(オモダル多細胞)、綾惶根(アヤカシコネ遺伝子)は生命の根源の男女神、イザナギ・イザナミ、
または、カムロギ・カムロミに相当します。祭神としては倭国の御祖神(ミオヤノカミ)になります。
■浄妙尼社 福岡県太宰府市朱雀6丁目15−7
○榎社 (旧榎寺浄妙院)太宰府市朱雀6丁目18−1
◎No.53 菅公受難の旅路と福岡県田主丸町の小川天満神社 2018年3月19日
○菅公受難の旅路と大分県九重町の菅原天満宮
菅原道真公が右大臣に就任して3年、昌泰4年(901)正月25日破局は突然におとずれた。道真公は大宰権帥に左遷され、詔が公布されます。道真公は宇多上皇の救いの努力もむなしく大宰府に流される身となり、2月1日には早くも都を立たねばならなくなった。妻と女子は都に留まることを許されたが、長男の高視は土佐に流され、ほかの三人の男子も地方に追われ、一家離散の悲運となった。
九州下向の一行は、警固の役人二人と隈麿と紅姫の幼児二人と門人を含め七名で、見送る人もなく、配流の罪人としての長旅となります。道真公は京都を発してから、絶えず藤原時平の差し向けた刺客に狙われることになります。刺客を避けるためか、大宰府館への旅路は苦難の旅路であった。
博多の若宮(今泉若宮社)に上陸→天拝山→基山→脊振板谷峠→早良壬生家→谷村(六本松)→築上町網敷→大分邯鄲→九重町安全堂→北野町江口→松崎→南館(榎社)
○大分県九重町の安全堂に到着
玖珠郡葦谷村(あしやむら)、現在の大分県九重町菅原の白雲山安全堂に着かれる。「菅原」は菅原道真公の名にあやかった名称で現在「菅原天満宮」があります。天満宮の西に、観応が開基した真宗白雲山浄明寺(当時は天台宗)があり、観応は道真公と親しい山城國愛宕山の学友でした。ご一行が着かれた日は春というのに雪が軒下まで積っていたという。延喜2年の早春であった。ここに長期の滞在をされます。
葦谷村では、地元の女性二人との間にそれぞれ子を成されたが、二人とも育たなかったという。その女性の一人、浄妙尼(浄明尼)は菅公没まで身の周りの世話をされたという。ここ安全堂にて、菅公は手鏡を前に、自分の姿を映し、自画像を描かれたという。地元では、榧(かや)の一枝を採り、自像を彫刻されたと伝承が残る。
菅公没後、葦谷村名は菅原村に改められた。寛永10年(1633)、安全堂は天台宗より浄土真宗に改宗し、寺号を淨明寺と改めた時、自像の彫刻像をご神体に神社一宇が創立されたという。この神社が現在の「菅原天満宮」となった。安全堂を浄明寺に改めたのは菅公のお側人「浄妙尼」にあやかってのことではといわれる。
菅原天満宮案内書末尾には「太宰府天満宮のご祭典は、この天満宮の使者が出府しないと開くことができかった、という由緒ある天満宮である」とあります。
菅原天満宮 大分県玖珠郡九重町大字菅原(字本村)2300
浄明寺 大分県玖珠郡九重町大字菅原336
菅原天満宮より浄明寺を望む
■王城神社 (No.170 171)
「春日」が春日神社(春日市春日一丁目110)に由来する前の古代から「奴国の丘」と那珂川の間に開化天皇の春日率川宮(かすがのいざかわのみや 春日之伊邪河宮)がありました。現在は天児屋根命(あめのこやねみこと)の四柱を祀る春日神社となっています。 私は、春日率川宮があったこの地一帯が本来の「春日」の地ではないか、と思っています。
春日一丁目の春日神社は古昔より一貫して現在の地にあったのではありません。 その前は、四王寺山(王城山 おおきやま)に祀られていましたが、白村江の戦いに対処する山城再築のため、現在地(春日市)に中大兄皇子が天児屋根命を祀る神社として遷したという。さらに、相殿であった事代主命を祀る王城神社も共に現在の太宰府市通古賀五丁目8-40に遷されました。
王城神社
福岡県太宰府市通古賀五丁目8-40(字扇屋敷1203)
神紋は檜扇紋(女)、鯉、波乗りウサキ、鶴の彫刻が祭神の決め手です。
※通古賀の王城神社の祭祀線
通古賀の王城神社の祭祀線は、大分県国東の杵築市の奈多八幡宮につながります。
奈多八幡宮の祭神は大幡主と市杵島姫です。市杵島姫は奈多八幡宮の海岸沖の市杵島に祀られています。
■春日神社 福岡県春日市春日一丁目110
氏子さんは白水(しろうず)さんが筆頭。祭神は本殿の天女(天照)の彫刻が決めてです
本殿右側の若宮社は奈良の春日・若宮社と同じで、祭神は天押雲根命
天押雲根命(女・天照) 率川神社、率川(いさかわ)=日佐川(ひさかわ)
春日大社には別殿(本殿と同格とされる)の若宮神社に天押雲根命が祀られています
※談山神社 奈良県桜井市多武峰(とうのみね)319
祭神 藤原鎌足 合祀:鏡王女(妻) 藤原不比等(次男) 長子の定恵が創建
末社 天照大神、大山咋神、宇迦之御魂神
■古賀の扇祇神社 福岡県筑紫野市古賀(字)舟木738
祭神 綾惶根命、合祀・大山祇神
祭神・大山祇神(山神社 大字古賀字山の口・大字古賀字白ヶ原)は明治44年10月合祀
神紋は三つ扇紋、向拝に鶴の彫刻、境内社・秋葉神社 (No.166)
■萩原の扇祇神社 福岡県筑紫野市萩原(字)垣ノ内708
祭神 綾惶根命、合祀(埴安命、火之迦具土神)
祭神の埴安命(大神社 大字萩原字京手)、
火之迦具土神(日尾神社 大字萩原字吉浦)は
明治44年合祀
神紋は三つ扇紋、向拝に亀の彫刻、本殿の地紙紋(扇)に富士山、桃の彫刻、許黄玉の石塔
宇佐八幡宮(山口県防府市大字鈴屋840)の神紋は地紙紋です、三巴紋ではありません
※萩原の扇祇神社祭祀線(亀)
扇祇神社から参拝遥拝する神社
筑紫神社(大幡主)、筑前町小隈の元大神宮(大幡主)、
朝倉宮野の宮野神社(大幡主)
同上の別所熊野神社(大幡主)、
日田大原八幡(大幡主、天照女神)
筑紫神社と大原八幡は完全に本殿を通ります
※古賀の扇祇神社の祭祀線(鶴)
拝殿は上古賀の若八幡宮、内山の竈門神社下宮を、
本殿は竈門神社上宮を向いています。
祭祀線から見ると、
萩原の扇祇神社の主祭神は天照女神、
古賀の扇祇神社の主祭神は大幡主
の傾向が強いです。
いずれにしても、二社の扇祇神社は天照女神(綾惶根尊)
・大幡主(面足尊)を祀る神社となります。
※やよい語
カムロミ 目に見えない世界
カムロキ 目に見える世界
オモダル 生命の男根の神、多細胞
アヤカシコネ 生命の女陰の神、遺伝子
■大歳神社 福岡県筑紫野市山口1924
祭神 大歳神
. 大鷦鷯尊(仁徳天皇) 素盞嗚尊 大山祗神
. 火結尊 奥津彦 奥津姫 埴安命 事代主命 倉稲魂神
本殿左は八幡神社、
本殿右は貴船神社、貴船社は扇祇神社です
貴船神社の祭神
高淤加美神、高龗神(たかおかみ)=大幡主
闇淤加美神、闇龗神(くらおかみ)=天照女神
荒神社(こうじんしゃ)祭神
火結尊 奥津彦 奥津姫 (No.169)
■上古賀若八幡宮 筑紫野市上古賀4丁目3-7
祭神 仁徳天皇
※一般的に若宮八幡宮は、
若宮社(天照女神)+八幡社(大幡主)
若宮社は福岡市中央区今泉に若宮神社(天照女神)があり、桃が印象的です。
菅原道真公は今泉の若宮神社付近に上陸され、水たまりに自分の姿を映し、嘆いたといわれます。
後に、ここに水鏡天満宮(容見天神)が建てられ、天神(アクロス福岡付近)に移されています。
※若宮を「わかみや」と呼んではいけません。表意は蛇宮(じゃぐう)です。蛇の宮です。
すると、祭神は天照女神となります。龍宮を「たつみや」と呼びますか?
※王城・扇祇(おうき) → 意富岐(おおき) → くなと → 塞の神・幸の神 → 大幡主・天照女神
※柏(かし・かや) → 栢(かし・かや) → 榧(かや) → 伽耶(かや)・意富伽耶 → 大伽耶
※四王寺山から下ろされた王城神社
四王寺山に祀る王城神社の祭神は天照女神(春日大神)と武甕槌命(住吉大神)であり、四王寺山から下ろされた時、武甕槌命は春日神社に、天照女神は通古賀の扇屋敷に遷され王城神社となっています。
春日神社は、神護景雲2年(768年)、太宰大弐の藤原田麿は、筑紫春日の地に藤原家の祖神である武甕槌命が祀られていることを知り、故郷である奈良の春日大社から、天児屋根命、経津主命、姫大神を迎え、神社を再構築(改変)したという。一方、通古賀の王城神社の祭神は天照女神から事代主に変えられています。
本来の王城神社(扇祇神社)は、武甕槌命(面足尊)と天照女神(惶根命)を祀ります。
春日様(春日大神)とは「天照女神」をいいます。
もしかしたら、初期の春日神社(天照大神社)は春日様(春日大神)の天照女神を祀り、王城神社(扇祇神社)は、武甕槌命(住吉大神)を祀っていたのかもしれません。
藤原氏は春日神社を現在の春日四神に再構築しましたが、東にある天押雲根命(天照女神)を祀る若宮神社は藤原氏の神社ではありません。
王城神社の祭神は事代主に変えられています。
坂本八幡宮駐車場 福岡県太宰府市坂本3丁目14
浄妙尼社 福岡県太宰府市朱雀6丁目15−7
王城神社 福岡県太宰府市通古賀5丁目8-40
春日神社 福岡県春日市春日1丁目110
古賀の扇祇神社 福岡県筑紫野市古賀738
古賀公民館(駐車場) 福岡県筑紫野市古賀675
萩原の扇祇神社 福岡県筑紫野市萩原708
大歳神社 福岡県筑紫野市山口1924
上古賀若八幡宮 筑紫野市上古賀4丁目3-7
■大神神社 奈良県桜井市三輪1422
主祭神:大物主大神(倭大物主櫛甕玉命)
配祀神:大己貴神 少彦名神
大物主神は大己貴神の和魂である蛇神であると考えられ、水神または雷神としての性格を合わせ持ち、稲作豊穣、疫病除け、醸造などの神として特段篤い信仰を集めている。Wiki
※中世の大神神社の神宮寺・大御輪寺
大神神社の神宮寺は大神寺(おおみわでら) として奈良時代に成立。大神寺は鎌倉時代、大規模な改修がなされ、寺名も大御輪寺(だいごりんじ) に改称。
明治政府の神仏分離令により、神宮寺は廃寺となり、本尊の十一面観音は桜井市の聖林寺に移されました。大直禰子神社がある所は、かつての大御輪寺の神宮寺跡とされる。
大御輪寺には若宮本地堂と大宮本地堂の二堂があったとされる
若宮本地堂の本尊は十一面観音 → 天照女神
大宮本地堂の本尊は薬師如来 → 大幡主(行方知れず)
阿蘇神社の神護寺の薬師如来も行方不明です。
※倭大物主櫛甕玉命は大山咋神ですか?私は天照女神と思うのですが。
さらに、大己貴神は天照女神、少彦名神は大幡主と思うのです。
大歳神社は「おおとし神社」と読ませています。年の暮れに「大年神様」を迎えるという意味で使用されています。それでは、神格が漠然とします。
大歳神は、大の「さいの神」であり、「さいの神」は塞(さい)の神で、正八幡神大幡主を指します。又、幸(さい)の神もあります。
幸神社(さいのかみのやしろ)は高良下宮(久留米市御井町387)にあります。向拝に三笠松紋が打ってあります。祭神はいろいろな説がありますが、天照女神です。
筑前町の大己貴神社の社頭には、「幸神」と刻んだ大きな石碑があります。祭神からすると「さいの神」であり、天照女神とも大幡主ともとれます。
大己貴神社 福岡県朝倉郡筑前町弥永697−3
※神宮寺本尊を薬師如来から庚申尊天へと変えるならば本尊の存続を許そう
庚申(こうじん)→幸神(こうじん)→「さい」の神です。「庚申尊天」「幸神尊天」の石碑をよく見かけます。「庚申尊天」は大幡主、「幸神尊天」は天照女神を指すのでしょう。
今宮も「いまみや」とよんでいます。意味がピンときません。
方位の神様に「金神」(こんじん) がおられます。さらに、月毎に変わる巡金神(めぐりこんじん)も、その年の十二支によって変わる大金神・姫金神もあります。
今宮→金神→こんじん→金龍→きんりゅう(金立)→大幡主 です。
金神は忌避の方位神とマイナスのイメージがありますが、本当の意味は違います。
今宮は金凝彦、金裂神、金毘羅様へと続きます。
■護良親王の事績が判明した加太春日神社(1)
https://www.kishu-bunka.org/ochiai1/kadakasuga1.html
平成26年11月12日 落合莞爾
平成26年6月、海南市大野中の春日神社で執行された大野十番頭祭で、護良親王の末裔として祭主を勤めた私は、かねがね和歌山市加太の春日神社も、正体は奈良春日大社の末社ではなく、和邇春日氏(大春日氏)の神社ではないかと見当をつけていた。
藤原北家による諸豪族の家名と姓の簒奪と源平藤橘四姓の欺瞞性に、以前から漠然と気付いていた私は右の説にわが意を得たが、さらに『紀伊続風土記』名草郡大野荘中村条に興味を惹かれた。
大塔宮護良親王の滞在場所を「中村菩提寺」としているが、これは大野荘幡川村禅林寺末の同荘山田村菩提寺のことで、大野荘春日神社の奥ノ院(年越明神の奥ノ院)であった。大塔宮はここでしばらく滞在したわけである。・・・ 大野荘春日神社の社伝のごとき異説はなく、大塔宮が頼りにされた大野十番頭の中の井口壱岐守がわが実家と同姓なのに興味を抱いたのである。
大塔宮護良親王の事績は、『太平記』に基づく今日の教科書歴史とは全く異なるものである。 春日氏は本来、海人系の古代氏族で、祖神を祀っていた奈良の春日野の地を天平年間に藤原不比等に召上げられたのは、渡来人のために氏神も姓氏もなかった不比等が中臣の姓を奪ってこれを称し、鹿島の神を奪って奈良春日野へ移して中臣の祖神とし、春日大社と称したのである。
南北朝対立の背後事情に関する調査を進めた結果、私は今日の「海人史観」を建てることができたのである。全国の海辺にある春日神社は、すべて大春日氏(和邇氏)の観点から洗い直す必要があると睨んだが、その最初が< /strong>加太春日神社であった。
『紀伊続風土記』海部郡加太荘加太浦条の春日神社
本社 祀神 天照太神・春日明神・住吉明神
末社 二社 稲荷社 八王子社
村中馬場町に在り、粟島社の摂社にして一村の産土神なり。村民相伝う。この地創造の時、当社を勧請すという。按ずるに、其の初め天照大神一座を祀り奉り、後に住吉・春日両社を合わせ祀りしなり。
当社は、延喜式の式内社ではないが、『紀伊国神名帳』には「正一位春日大神」と記されている。
鎌倉時代末期の文保元(1317)年に、地頭の日野光福が住吉社(の建物など)を寄進したことは確かで、その日野氏が藤原姓の祖神の奈良春日社をも祀ったので、社名が春日神社となったというのである。地頭の日野氏が古来の天照大神社に奈良春日三神を合祀したと判断。
(注)詳しくはWEB アクセスにてお願いします