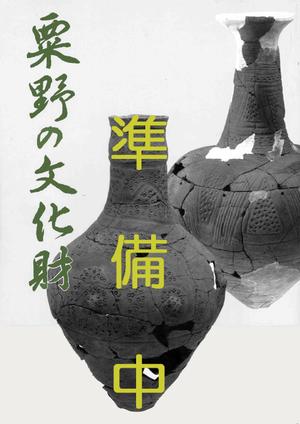昨日は、月に一度の 『鹿沼の麻を知る会』
麻農家 7代目 大森由久先生に定期的に
お話をお聞きしております
麻は古来からの日本人の生活に溶け込んで来た
大切な植物
本を読んだり、
麻をご存知の方のお話会に参加するのも
大切ですが。。
やはり、現地に赴いて、今の日本の麻を一番に支えている方から、
実際のお話をお聞きするのが、なによりも重要なことだと思い、
企画しておりまする
今回のテーマは、『弥生時代』
日本人と麻の歴史は長く
ずっと日本人の生活をサポートしてくれています。
大森先生のご自宅からほど近い場所に
鹿沼市指定文化財『戸木内遺跡』
昭和59年(1984年)に発見されました。
死者を一時的に埋葬し、白骨化したものを掘り起こして
丁寧に洗い、改めて美しい壷に納めて埋葬する 『再葬墓(さいそうぼ)』
と呼ばれ、一緒に勾玉や管玉(くだたま)が発見され
そして、大阪市鬼虎川遺跡からは『麻紐』も発見されています。
戸木内遺跡では、骨は発見されませんでしたが、
死者を丁寧に弔う文化が
弥生時代から続いているって、本当に素晴しいですよね
鹿沼の地には、海を渡り川を遡上して入植してきた海洋族と
山を越えて入植してきた山民族の2ルートがあり
弥生文化を伝えた山民族は、朝鮮半島から北九州を中心に栄え
稲作を主とする農耕生活を始め、伊勢湾周辺まで波及し
山道を辿り、天竜川を遡り伊那谷から浅間山麓を超えて
群馬を経て栃木、そして永野に伝わってきたのです。
争いがない縄文時代の豊かな文化は、自然神を祀り
平和な時代ではありましたが、まだ稲作が始まっていないので
食料難が短い間に何回も続いた、厳しい時代だったそうです
その証拠に、九州で発掘された骨に飢餓の時に傷が刻まれたと想像される
年輪があり、全人生が短かった(30年程)であろう中、
なんと15本(1年に1本)もの筋が発見されたとのこと。
慎ましく暮らしながらも、周りと分け合い譲り合い丁寧な営みの縄文時代でしたが、生活をするには厳しい時代だったのですね。
海外からの様々な民族が、それぞれの新しい技術、
稲作や五穀、タタラ製鉄、製紙等が日本に持ち込まれ
特に稲作が始まったことにより、人口も増えて豊かな安定した生活が
始まり、大きな社会が生まれる。
ということは、
『利権』や『派閥』がうまれ、弓矢による
『戦いの歴史』が始まった時代でもありました。
豊かさとは、戦いの始まりでもあり
そして、人口が増えたことにより疫病が発生し
それを治めるために、生活の中に寺院が作られ始めた。
タタラ製鉄は、吉備地方(岡山、広島、香川、兵庫など)にまたがり
ここは、筑紫、出雲、毛野などと並ぶヤマト王権を支える有力な地域だった。
『天目一個神(あまのまひとつのかみ)』は、製鉄・鍛冶の神様とされ
古事記での岩戸隠れの段で、鍛冶をしていた『天津麻羅』と同一視されており、
『目一個(まひとつ)』とは、『一つ目(片目)』の意味で
鍛冶師が鐵の色合いで、その温度を確認するときに片目をつぶっていたことや
炎によって片目を失明することから、名付けられたと言われるている
今回も大勢の方にお集り頂きました。
弥生時代は、様々な海外からの民族が
それぞれの卓越した文化を携えて
日本を目指して集まり、地域の生活向上とともに
戦いの歴史が始まり、
そして、『国譲り』、、
とは、日本が負けたことを意味します。
くぅ、、
縄文時代に使われた 『青銅器』
青銅器を扱っていた『忌部族』ですが、やはり
『銅』は、『鐵』には勝てなかったのですね。。
現在、『族』『氏』と呼ばれている歴史上の人々は、海外からの民族のことで
一番古いとされる、京都にある 『下鴨神社』『上賀茂神社』は
『賀茂氏』が作った神社とのこと
盛りだくさんの麻と日本の歴史を
惜しみなく伝えて下さる 大森先生
大集合写真

お写真を撮るときだけ、ほんの僅かの時間のみ
マスクを外させて頂きました
いやー、、本当に愛情たっぷりの大森先生
あれれ?
なんか、巨人に見えてますが・・?笑
てか、後ろにも巨人が・・・爆笑
ガリバーか?
飛び出す絵本状態の 大森先生でした

月に一度、栃木県鹿沼市で大森先生から
日本の麻の歴史を教えて頂いております。
ご興味のある方、御一緒しませんか?
お問合せ、お申込みは
keityblue01@gmail.com
大森先生、千津さん、ご一緒させて頂きました
皆さま
ありがとうございました。
また来月、お逢いしましょ〜!