 こちら葛飾区亀有公園前派出所 199 (ジャンプコミックス)の感想
こちら葛飾区亀有公園前派出所 199 (ジャンプコミックス)の感想弘前城動く。曳家。モービルハウス・日本だと家と認められない。盆コレ。東京飛行場。ダッゼムカー。ニュルブルクリンク。人間カーリング。月の砂漠。御宿海岸。月面車。金町。取水塔。柴又帝釈天。水元公園、区内最大。
読了日:8月15日 著者:秋本治
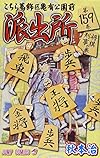 こちら葛飾区亀有公園前派出所 159 (ジャンプコミックス)の感想
こちら葛飾区亀有公園前派出所 159 (ジャンプコミックス)の感想ブルーマウンテン・ジャマイカ政府の法律、高地800~1200メートル。コーヒーベルト。アイリッシュ・コーヒー。
読了日:8月15日 著者:秋本治
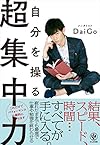 自分を操る超集中力の感想
自分を操る超集中力の感想パーキンソンの法則。プライミング効果(膝と肘)。水色のペン立て。事故認識力・鏡。アイディアは天井の高さに比例する。低GI食品。セカンドミール効果。コーヒーとヨーグルト。セルフ・ハンディキャップング。HIIT。バリュアブルスリーパー。hue(LED)。パワーナップ。ウルトラディアンリズム。パーミング(手の窪み、目を閉じる)。ローズマリー。ペパーミント。シナモン。ポモドーロ・テクニック。アクティブ・レスト。アイビー・リー・リスト。モラル・ライセンシング。週の2日間を余白に。
読了日:8月14日 著者:メンタリストDaiGo
 マンガでわかる人間関係の心理学 (池田書店のマンガでわかるシリーズ)の感想
マンガでわかる人間関係の心理学 (池田書店のマンガでわかるシリーズ)の感想マンガでわかるとはなっているが、マンガはほとんどなく、イントロダクションとしての役割に過ぎない。本の内容は、心理学の用語説明や人間関係における一般的な人の反応、行動、心理等、実際的でコンパクトにまとまっており、入門書として良いと思う。最近、マンガでわかる~というのが増えているが、自分の知らない分野の学習によく使えると思う。
読了日:8月13日 著者:渋谷昌三
 マネー力 (PHPビジネス新書)の感想
マネー力 (PHPビジネス新書)の感想これまでの本と言ってることは同じ。新しさがない。他の新しい本で勉強しようと思う。
読了日:8月13日 著者:大前研一
 民主主義の本質と価値 他一篇 (岩波文庫)の感想
民主主義の本質と価値 他一篇 (岩波文庫)の感想ちょっと時間を空けて読むことになったので、繋がりが忘れかけていたが、著者の主張は非常にクリアで整合的。結局民主主義や社会民主主義、資本主義等、その国にあったやり方を自信を持って追求していくしかないのではと思う。
読了日:8月12日 著者:ハンス・ケルゼン
 人はどうして疲れるのか (ちくま新書)の感想
人はどうして疲れるのか (ちくま新書)の感想自分の睡眠時間の長さやそれにも関わらず、入眠剤がないと眠れないという矛盾、また人よりも疲れやすい身体を何とかしたいので読んでみることに。疲れの一般的なメカニズムはわかったが、これを実際にどのように解決していくのかはまた別の問題なので、何とかして行きたい。人間関係のストレスが疲労に大きな影響を与えていると思うので、これを上手く乗り越えられるようにしたい。
読了日:8月12日 著者:渡辺俊男
 二つの祖国〈上〉 (新潮文庫)の感想
二つの祖国〈上〉 (新潮文庫)の感想久しぶりの山崎豊子さん。今度は第二次世界大戦に巻き込まれた日系人二世を主人公に描く。山崎さんの本を読むと、毎回自分の勉強不足が露呈するので、頑張って勉強していきたい。
読了日:8月11日 著者:山崎豊子
 スノーボール (上) ウォーレン・バフェット伝の感想
スノーボール (上) ウォーレン・バフェット伝の感想今年の世界時価総額ランキングで7位にランクされているバークシャー・ハサウェイ。その会社を率いる投資の神様・オマハの賢人ウォーレン・バフェットの伝記。かなりの吝嗇家であり、すごく頭が良く、奇人っぷりはその投資スタイルに表れているのではないかと思う。とても長くて、なかなか読み終わらなかったが、下巻も読み進めて行きたい。
読了日:8月11日 著者:アリスシュローダー
 「教養」とは何か (講談社現代新書)の感想
「教養」とは何か (講談社現代新書)の感想吉茂の生涯で注目すべきことは若いときに寺子屋に行くよう勧められながらもそれを断り、算術の勉強も断って農業ひとすじに働いた点である。生半可な学問は鼻を高くさせるだけで、百害あって一利なしとされている(45頁)。教養の始まりは「いかに生きるか」という問いを立てたことにあった(54頁)。「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうとしている状況」を「教養」があるというのである(56頁)。私たちは「世間」の中に原始的な生の規範を閉じ込め、そこでのみ無理の
読了日:8月10日 著者:阿部謹也
 コミュニケーション力 (岩波新書)の感想
コミュニケーション力 (岩波新書)の感想コミュニケーション力とは、意味を的確につかみ、感情を理解し合う力のことである(4頁)。クリエイティブな関係性。文脈力。3色ボールペンメモ。マッピングコミュニケーション。
読了日:8月9日 著者:齋藤孝
 授業づくりエンタテインメント! ―メディアの手法を活かした15の冒険の感想
授業づくりエンタテインメント! ―メディアの手法を活かした15の冒険の感想MC-1.楽しい雰囲気を作れる。2.観察力が旺盛で、多くの人が気づかないことに焦点を当てられる。3.歯に衣着せぬ発言が許されやすく、建前でなく本音で話せる。4.他の出演者に「つっこみ」を入れて、話を引き出せる。静かなる革命。フローレンス-病児保育専用、施設型ではなくスタッフを派遣する形のシステム。「働き方革命」。ゲーミフィケーション。西千葉子ども起業塾。
読了日:8月9日 著者:藤川大祐
 ローカル線で地域を元気にする方法: いすみ鉄道公募社長の昭和流ビジネス論の感想
ローカル線で地域を元気にする方法: いすみ鉄道公募社長の昭和流ビジネス論の感想乗らなくてもよいですよ。枕木オーナー。よそ者の仁義。公募社長募集の原則。エアオン。マニアックな世界の人たちというのは精神的な価値を理解できる人たちであって、物質的なことでは満足できない(物質的なことを卒業した)アンテナの鋭い人たちであるということです(129頁)。とくに有名な観光地でもなく、万人受けするような呼び物もないのがいすみ鉄道沿線です。だから、いすみ鉄道などのローカル線の旅にいらしていただく皆様方は、精神性の高い皆様だと思います(140頁)。
読了日:8月9日 著者:鳥塚亮
 物語ラテン・アメリカの歴史―未来の大陸 (中公新書)の感想
物語ラテン・アメリカの歴史―未来の大陸 (中公新書)の感想以前ブラジルの事は少し勉強したが、如何せん周辺知識がないので、頭に入って来ないし、整理できるレベルでもない。スペイン語やポルトガル語、南米ローカル語をそのまま日本語の発音にした言葉等、記憶が大変である。夏休みに全然本を読めていないので、なんとか打開したい。
読了日:8月8日 著者:増田義郎
 アメリカのユダヤ人 (岩波新書)の感想
アメリカのユダヤ人 (岩波新書)の感想ユダヤ人問題について。ルポルタージュ。アメリカのユダヤ人であるが、ソ連から渡ったユダヤ人の視点からも書く。ユダヤ人のロビー活動の強さや選挙での影響力についても紹介。PLO等ユダヤ人組織など。
読了日:8月6日 著者:土井敏邦
 地域再生の経済学―豊かさを問い直す (中公新書)の感想
地域再生の経済学―豊かさを問い直す (中公新書)の感想非常になるほどがいっぱいの本。地方に財源を渡さない中央集権的な何処かの政府もあるが、地方に財源と権力を委譲し、地方がコミュニティーとして自立ある財政、そして発展を遂げていけるような仕組み作りを自ら出来るようにしないと国そのものがダメになってしまう。中央集権は均一ある国土の発展をするのには良かったが、役割が終わったらやはり変えるべき。今の日本に未来はあるのかと本当に不安になってしまう。
読了日:8月5日 著者:神野直彦
 エビと日本人 (岩波新書)の感想
エビと日本人 (岩波新書)の感想少し古い本なので、現在の輸入量・消費量は正確には分からないが、世界一のエビ輸入消費国である日本のエビ関連事業の実態を書く。エビ生産に関してインドネシアや台湾の生産家の実態、環境破壊、第三世界と先進国の格差について紹介されており、それらに胸を痛める。現在は大量消費国となった中国の動向が気になるので、また新たに調べてみたい。
読了日:8月4日 著者:村井吉敬
 ニュースで学べない日本経済の感想
ニュースで学べない日本経済の感想大前さんの本を古本屋以外で読んだことがなかったので、今回のような新しい本は時代にマッチしていて新鮮だった。どうしてこんなに時代を先読みし、分析して、現状の解決法を思い付くのだろうと思う。やはり勉強不足を感じるので、頑張ろうと思った。
読了日:8月3日 著者:大前研一
 圧倒的な勝ち組になる効率のいい考え方と仕事の仕方の感想
圧倒的な勝ち組になる効率のいい考え方と仕事の仕方の感想天明さんのファンなので、読むのが楽しみだったこの本。タイトルに似合わず、内容はまともで非常に戦略的。圧倒的な結果を出すため、フレキシブルかつ合理的に考え行動する事を説く。しかし、別に非人間的、無感情的な生き方を勧めている訳ではなく、割り切りや優先順位等、至極常識的。読んで参考になったし、天明さんの生き方に共感する。問題はタイトルと一般人が持つ天明さんへのイメージ。華麗な経歴と高飛車な発言で敬遠する人がいる中、このタイトルでは本を手に取る人自体少ないのではないか。もっと彼女の内面が知れたら本も売れると思う。
読了日:8月3日 著者:天明麻衣子
 憲法と平和を問いなおす (ちくま新書)の感想
憲法と平和を問いなおす (ちくま新書)の感想主に立憲主義についての本。これまで民主主義や自由主義、政治学等の本を読んできたが、先にこの本を読めばよかった。分かりやすく解説が丁寧である。本書にもあった憲法9条問題。憲法は原理を示すのであって、準則を示すのではない。日本国憲法は日本国のあり方を定めたもので、外国には適用されないし、当然に集団的自衛権の行使も認められない。著者である長谷部教授は国会召集時、集団的自衛権の行使容認は憲法違反であると述べていた。しかし、だからと言って憲法改正する事も的を射ていない。この国にあった方法は如何なる物なのかと思う。
読了日:8月3日 著者:長谷部恭男
 若者のための政治マニュアル (講談社現代新書)の感想
若者のための政治マニュアル (講談社現代新書)の感想今の問題を政治学の面から見るとこのように解釈されるのかと色々納得する点が多い。勉強不足なのでこれからも継続的に行って行きたい。
読了日:8月3日 著者:山口二郎
 科学的とはどういう意味か (幻冬舎新書)の感想
科学的とはどういう意味か (幻冬舎新書)の感想小説を読む人と、ノンフィクションを読む人はほとんど重なっていない、というのが僕の印象だ。そして、小説を読む人数の方が(僕の作品の読者では)圧倒的に多い(106頁)。科学というのは「方法」である。そして、その方法とは、「他社によって再現できる」ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他社に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる(107頁)。非常に面白い一冊であった。
読了日:8月2日 著者:森博嗣
 知っていそうで知らない台湾―日本を嫌わない隣人たち (平凡社新書)の感想
知っていそうで知らない台湾―日本を嫌わない隣人たち (平凡社新書)の感想台湾についての入門書的存在。台湾の歴史や政治、政権、中国・日本との関係、外交等包括的に紹介している。台湾に親日家が多い理由がいくつか挙げられており、日本人として嬉しいが、日本の台湾に対する態度は冷たく残念に思う。また、台湾地震の際、日本の救助隊が被災者を救えず、「努力不足で救えず申し訳ない」と述べた事が描写されており、それが日本に対する尊敬の念を生んだのではとされている。問題なのは無軸で大国の意向ですぐに変わる日本の外交。国のためを思い行動する政治家が今の日本にどれだけいるのか、最近の選挙を見ていて思う。
読了日:8月2日 著者:杉江弘充
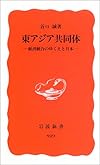 東アジア共同体―経済統合のゆくえと日本 (岩波新書)の感想
東アジア共同体―経済統合のゆくえと日本 (岩波新書)の感想米国財務省によって潰された東アジア共同体について書く。新宮沢構想など、日本には東アジア共同体を創る考え自体はあったものの、太平洋戦争の贖罪意識が強く、また、長期的視野に欠けているため、リーダーシップを発揮出来なかった。そもそも、日本はアジア1、東洋唯一の先進国という意識が強く、福沢諭吉が唱えた「脱亜入欧」の考え方が続いてきたため、アジアに対して積極的に行動して来なかった。時代の変化に伴い、日本に求められる意識改革と役割を述べ、また、環境・食糧問題によって、東アジア共同体構想の積極的意味付けを行っている。
読了日:8月2日 著者:谷口誠
 ルポ 貧困大国アメリカ (岩波新書)の感想
ルポ 貧困大国アメリカ (岩波新書)の感想世界一進んだ国と言えども、その実態は必ずしも良いとは言えない。アメリカの繁栄は下層民、貧困者達の犠牲の上に成り立っている。また、よく問題になる医療・保険制度は破綻している。命を扱う分野に競争を取り入れるのは何かがおかしい。大学、高校卒業後、仕事がなく奨学金返済のため入隊する若者は多い。冒頭の貧困が肥満に結び付くというのも衝撃的。健康に気を使わない食事を学校が出すことで病気が増え、医療費削減のため運動をやらせ、水分・栄養補給のためコーラを飲ませ、スナック菓子を食べさせる。一体何をやっているのだろうか。
読了日:8月1日 著者:堤未果
読書メーター