近年の戦略研究において、中国は今や主役の座を占めています。台頭する中国は、アメリカの地位を脅かす大国にまで成長しました。冷戦後、ソ連が崩壊して、アメリカは国際システムにおける唯一の大国になりました。近代国家が誕生して以後、初めて単極システムが誕生したのです。しかしながら、単極体制は長くは続きませんでした。新興大国として中国が力をつけるにしたがい、世界は冷戦期のように、再び二極システムになりました。このような国際構造の変革期においては、戦争を招きかねない危機が起こりやすいので、それを乗り越える賢い戦略が求められます。それではアメリカや日本は、どのように中国と向き合えばよいのでしょうか。
こうした大戦略の問題に取り組むにあたり、参考にするべく重要な研究書が次々と出版されました。それらの代表的なものが、トランプ2.0政権の国防次官エルブリッジ・コルビー氏による『拒否戦略』(イェール大学出版局、2021年)、アーロン・フリードバーグ氏(プリンストン大学)による『中国を取り違えてしまったこと』(ポリティ出版、2022年)、ハル・ブランズ氏(ジョンズ・ホプキンス大学)とマイケル・ベックリー氏(タフツ大学)による『デンジャー・ゾーン』(W. W. ノートン、2022年)です。フリードバーグ氏の著作以外は日本語訳もありますので、そのリンクを張っておきます。ただし、ここでの議論は英語の原書に基づいています。
中国の地域覇権を阻止する「拒否戦略」
コルビー著『拒否戦略』は、中国がアジアで地域覇権を確立することはアメリカの死活的な国益に反するので、反中国連合を組み、それを防ぐことを提唱しています。これはジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)やスティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)らリアリストが提唱する中国への封じ込め政策の提言とほぼ同じです。
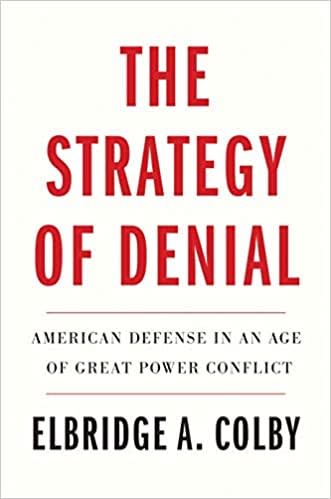
・中国に対する封じ込め戦略
ミアシャイマー氏は、中国を封じ込める戦略の有用性を以下のように指摘しています。
「台頭する中国を扱う最適な戦略は封じ込めだ。これは北京が軍事力を使ってアジアで領土を征服したり、より普遍的には影響力を拡大したりするのを防ぐことにアメリカが集中することを要請する。この目的に向かって、アメリカの政策立案者は、出来る限り多くの中国の隣国に対抗連合を形成するよう求めることになるだろう…封じ込めは本質的に防御戦略である。なぜならば、それは中国と戦争を始めることを要請していないからだ。実際、封じ込めは台頭する中国との戦争に代替するものなのである」(Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton, 2014、384-385頁)。
ウォルト氏もこう主張しています。
「アメリカはアジアで大規模な軍事プレゼンスを維持し、現在のアジアにある同盟国と引き続き安全保障面での相互関係を継続しなければならない…中国が大発展して東アジアで覇権的な位置を狙い始めた際に、アジアでのプレゼンスはアメリカが中国を封じ込めるための『足場』になる…アメリカが…他の国によって(アジアを)支配されるのを防げばよいのだ」(『米国世界戦略の核心』奥山真司訳、五月書房、2008年、350頁)。
このように封じ込めは、中国が覇権を打ち立てるのを拒否する戦略なのです。これは中国のアジアでの領土征服の既成事実化を防ぐものであり、中国の内政に介入して、共産党政権の転覆や民主化を目指すものではありません。コルビー氏の見立てによれば、中国が台湾を併合すれば、次にフィリピンを支配下に入れるのが容易になり、日本を孤立させることもできます。そうなると中国は一気に西太平洋に勢力を拡大してアメリカの安全保障を脅かすことになるので、その踏み台となる台湾侵攻を阻止すべきということです。そのためにはアメリカと日本、オーストラリアといった国家が協力して、中国に台湾侵攻は高くつくことを思い知らせることで、戦争を起こさせない拒否的抑止の戦略が最適であるとコルビー氏は主張しています。
対中エンゲージメント戦略の失敗
フリードバーグ著『中国を取り違えてしまったこと』は、冷戦後のアメリカの歴代政権が、中国は民主化するだろうと期待してエンゲージメント政策をとってきたことが、いかに間違っていたかを論証するものです。彼もリアリストと同様、アメリカは中国を優遇することにより、その期待に反して、自らの国益を脅かす巨大なライバルにしてしまったと結論づけています。
彼の言葉を借りれば、「中国は、自由で協力的なパートナーになる代わりに、ますます豊かで強力な競争相手となり、国内では抑圧的になり、海外では攻撃的になってきた…アメリカの歴代政権は、中国と商業的、外交的、科学的、教育的、文化的なつながりを深める『エンゲージメント』の促進を追求した…北京がアメリカの支配する冷戦後の国際システムに入ることを歓迎することで、アメリカの政策立案者は、中国の指導者が既存の秩序を維持することに利益を見出すよう促せると望んだ…最終的に、北京は、国際的現状維持の満足する支持者になるどころか、今やあからさまな現状打破目的を追求している…エンゲージメントは失敗した。なぜならば、そのアーキテクチャーや擁護者が中国を取り違えたからだ」(Getting China Wrong、1-3頁)。
ミアシャイマー氏による批判も、以下のように手厳しいものになっています。すなわち、「対中エンゲージメント政策は、近代史上、最悪の戦略的失敗だったかもしれない。超大国が自らと肩を並べるライバルの台頭を、これほど積極的に推進した先例はない。いまや、大がかりな対抗策をとろうにも手遅れだ」ということです。
要するに、アメリカが実行してきた対中エンゲージメント政策は、中国を強大な現状打破国に成長させることを助けてしまった大失敗だったのです。この間違いを訂正して、今後、中国を正しく扱うには、台頭する中国に対抗する政策をとるべきであり、ロシアを中国から引き離し、同国の現状打破行動にはコストを課す姿勢で臨むことだと、彼は次のように主張しています。
「エンゲージメントを擁護する古いワシントンのコンセンサスは最終的に崩壊したのであり、『中国を封じ込めることへの…要請が増大』している…したがって、アメリカと同盟国の戦略家が直面する喫緊の任務は、地域の軍事バランスにテコ入れをして、抑止を強化し、たとえ危機になっても、中国の指導者が武力行使による利得のために立ち上がると合理的に結論づけられる可能性を減らすのだ」(Getting China Wrong、147、187頁)。
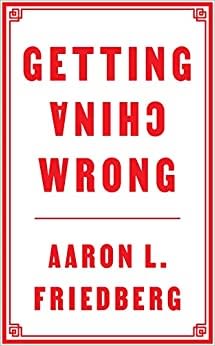
コルビー氏とフリードバーグ氏の分析の大きな違いは、米中対立の源泉について、前者がもっぱら中国の地域覇権への動きに見るのに対して、後者は、それに加えて中国共産党の「レーニン主義的イデオロギー」を加味していることでしょう(Getting China Wrong、174頁)。
「危険地帯」戦略
ブランズ氏とベックリー氏『デンジャー・ゾーン』は、上記の2冊とは、やや異なる中国観を提示しています。すなわち、中国のパワーは今がピークであり、今後は人口動態の変化などにより衰退していく。衰退する大国は「予防戦争」の動機を高めるので、この10年くらいが「危険」であり、アメリカと同盟国は、巧みな戦略で中国が台湾に対して戦争を始めることを阻止するべきだということです。その目的のために、アメリカと日本といった民主主義国は結束して、中国の台湾侵攻を阻止するべきだと彼らは主張しています。
・対中戦略の中の台湾有事
日本の安全保障にとって台湾有事は大きな問題です。その際、日本が直面する深刻な課題は、中国が日本の台湾有事への介入を阻止するべく、核恫喝を行うことです。この難問について、ブランズ氏とベックリー氏は明確な対抗策を大胆に述べています。後述するように、アメリカが核兵器で中国の軍事アセットを攻撃するオプションを持つことで、中国の核使用や恫喝を懲罰的に抑止するのです。
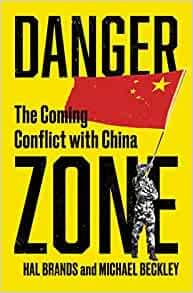
また、彼らは、世界の民主主義勢力の結束が長期的に続けば、中国は最終的に瓦解して屈すると期待しています。同時に、中短期的には、アジア方面で中国、ヨーロッパ方面でロシアを二重に封じ込めることも提言しています。こうした結論は、ブランズ氏の対ソ封じ込め戦略の成功を分析した研究成果とベックリー氏のアメリカのパワーの特異性を明らかにしたユニークな考察のハイブリッドと言えるでしょう。ブランズ氏は『大戦略の何が良いのか』(コーネル大学出版局、2014年)で、トルーマン政権が始めた封じ込め戦略とレーガン政権の対ソ戦略を高く評価していました。ベックリー氏は『無敵』(コーネル大学出版局、2018年)において、アメリカのパワーは他国に対して独自の優位性を持っているので、それは今後も継続すると分析していました。
これらの研究書が示唆するように、アメリカが対中封じ込め戦略に移行していることは確実であり、中国の台湾侵攻を阻止することが、近い将来の最大の戦略的課題であるのは間違いありません。台湾をめぐる紛争では、中国は数日の内に既成事実を作ろうとするでしょう。したがって、アメリカは抑止を劇的に強化して、台湾征服を成功させる能力への北京の自信を掘り崩す必要があるのです。ミッシェル・フロノイ氏(新アメリカ安全保障センター)とマイケル・ブラウン氏(スタンフォード大学)が指摘するように「台湾防衛のための時間は切れ始めている」とすれば、早急な対策が必要です。
拒否戦略の利点と欠点
中国に対する最適な戦略については、このようにさまざまな提言がなされていますが、私は、コルビー氏の「拒否戦略」が最も現実的であるように思いました。彼が提唱する戦略の骨子は、以下になります。
「アメリカは世界中のあらゆる潜在的紛争に対処できないし、同時には確実に無理である。アメリカはアジアとりわけ中国の覇権阻止と台湾の防衛に集中すべきで、ロシアからの脅威へは、欧州が自らの防衛を強化できるようにすべきであり、ここで中心的役割を果たすのはドイツになる」。
・コストの問題
拒否的な抑止戦略の問題は、コストがかさむことです。第1に、中国が国外への侵攻に走ることを防ぐには、戦争で勝利するには犠牲が大きくて割に合わないと明確に納得させるだけの大規模な通常戦力を、アメリカや日本といった同盟国は展開しなければなりません。コルビー氏は、そのために日本はGDP比で3%の防衛費を支出して軍備を強化する必要があると主張していました。我が国の戦力不足は深刻です。ある自衛隊幹部は「南西諸島で有事があれば(現有戦力では)数日も持たない」と明かしています。
・イデオロギーと戦略
第2に、中国に対する封じ込め戦略に民主主義イデオロギーを持ち込むのは、中東の主要国であるサウジアラビアやチョークポイントであるマラッカ海峡を臨むシンガポールといった重要な国家を遠ざけてしまうので賢明ではありません。ブランズ氏は「アメリカが大規模な民主主義国の連合の先頭に立って戦う戦争は、おそらく中国が勝てないものだ」と指摘しますが、中国に対抗するには、民主国に限らず多くの味方を集めるべきでしょう。
・戦略の優先順位
第3に、単極時代は終わったので、アメリカの限られた戦略資源を優先的に中国封じ込めに投入する必要があります。この点について、ある研究者は「いわゆるアジアへの軸足移動の失敗の根本原因は、アメリカのパワーがグローバルで普遍的だとするワシントンの継続的な信念である。アメリカの意思決定者がアメリカの戦略的優先順位を本当に求めるのなら、国家の利益と義務の明確な階層が必要である」と批判的にコメントしています。
ロシアと中国の二重封じ込めは、アメリカのパワーを過大評価しています。アメリカにはロシアと中国と同時に闘う二正面作戦の能力はありません。アメリカ軍の弾薬不足は、このことを裏づけています。マーク・カンシアン氏(戦略国際問題研究所)は、「アメリカは何種類もの弾薬や兵器システムをウクライナに数多く提供してきた。ほとんどのケースでは、アメリカの貯蔵と生産能力からすれば、ウクライナに供与された量は相対的に少ない。しかし、いくつかの兵器の在庫は戦争計画や訓練に必要な最小限レベルに達している」と警鐘を鳴らしています。
このような補給能力の弱体化が続けば、米軍の継戦能力は著しく損なわれる結果、アメリカは、ロシアよりはるかに強大な中国を封じ込めることが困難になるでしょう。ロシアの脅威にはヨーロッパ諸国だけで十分に対処できます。ロシアの軍事予算は、アメリカを除くNATOのちょうど5分の1であり、NATO全体の6%にすぎません。ロシア恐怖症とリベラル覇権主義の妄想は捨てられるべきです。
対中戦略における拡大抑止の問題
大戦略の構築において依然として重くのしかかる課題は、中国による日本や台湾への核兵器による威嚇でしょう。「ワシントンがニューヨークを危険にさらしてまでして、東京や台北を守るのか」という拡大抑止(核の傘)の古典的な問いには、明確な答えがありません。
・拡大核抑止の楽観論と悲観論
コルビー氏は、この問題に楽観的です。彼は、台湾をめぐる米中間の決意の競争は中国が有利とは限らない。なぜならば、中国はアメリカや同盟国からの反撃により、自国を破壊に導きたいとは決して思わないからだと判断しています(The Strategy of Denial、93頁)。しかしながら、中国とアメリカでは台湾に賭けるものが非対称なので、その威嚇は「チープ・トーク」になりがちです。中国にとって、台湾の支配は「核心的利益」にかかわります。他方、アメリカにとって台湾は、本土から何千キロも離れた政治主体の帰属問題です。台湾をめぐる利益のバランスは、中国にとって有利であり、アメリカにとって不利です。こうした利益の不均衡は、アメリカの台湾防衛にかかわる中国への抑止の威嚇を弱めかねません。
ブランズ氏とベックリー氏は、一歩踏み込んで、中国への低威力の核による対兵力戦略をとるべきだと以下のように主張しています。
「アメリカが台湾をめぐる戦争を核兵器を使わない状態に保ちたいのは明らかであるが、限定的な核オプション、すなわち、港湾、空軍基地、艦隊や他の軍事標的に対して低威力の核兵器を使う能力を持つことが必要である。これらは中国の核の脅しに対してアメリカが信頼性を持って対応することを可能にし、ひいては抑止することになるであろう」(Danger Zone、185頁)。
問題は、はたしてアメリカが、こうした懲罰的抑止のコミットメントを持つかどうか、ということです。保守派のダグ・バンドウ氏(ケイトー研究所)は、このことに否定的です。彼は「台湾は確かに価値のある友人だ。だが、核戦争に値するのか…アメリカ人がこの島の運命をめぐって戦う理由はない…台北のためにロサンゼルスを(中国からの核攻撃の)危険にさらす理由はない…この島には、アメリカの防衛に対する本質的価値はないのだ」と主張しています。同じロジックは、尖閣諸島をめぐる日中紛争にも当てはまるかもしれません。
米中関係に関する我が国での先駆的研究である、梅本哲也『米中戦略関係』(千倉書房、2018年)では、アメリカが中国の地域覇権を受容する場合の日本の「周辺」化が懸念されています。確かに、トランプ2.0の次期国防戦略は、アメリカ・ファースト主義による本土防衛が中国の封じ込めより優先されていると報じられています。そうなると日本が同盟国アメリカに「見捨てられる危険」は高まらざるを得ませんので、これは日本の安全保障にとって深刻なことでしょう。
いずれにせよ、各国に安全を提供できる中央政府が不在のアナーキー世界は、主権国家に生き残るための自助努力を強いるのですから、梅本哲也氏(静岡県立大学)が指摘する「我が国が戦略的に活用可能な軍事力」(同書、326頁)とは何であり、それをどう追求するかが、われわれには問われるでしょう。その際、核兵器という軍事力は、避けて通れないように思われます。
アメリカが中国からの核報復のリスクを冒しても日本を守るかは、その国益などに大きく左右されます。核の傘の信頼性の問題です。「核革命」の楽観論が正しければ、中国が核戦争へのエスカレーションを確実に制御できると判断しなければ、アメリカの日本に対する拡大抑止は効くことになります。しかし、悲観論の方が正しければ、アメリカが差し出している「核の傘」は破れやすいので、それほど信頼できないという結論になるでしょう。
・核共有という選択肢の是非
「核の傘」が脆いとしたら、それを補強する1つの方法は、アメリカと日本が核兵器を共有することです。そうすれば、中国の侵攻を思いとどまらせる、より高い効果に期待できそうです。なぜなら、核共有において核爆弾を運搬する任務は米軍ではなく自衛隊になるので、その分だけ核使用のハードルが下がるからです。この問題の専門家であるマサチューセッツ工科大学(MIT)のリチャード・サミュエルズ氏とエリック・ヘジンボーサム氏は、核共有を日本の安全保障強化のための現実的な選択肢であると主張しています。しかしながら、この核共有も「万能薬」ではなく、根強い懐疑論や反対論があります。
岩間陽子氏(政策研究大学院大学)は、「たとえ核共有しても…日本の国益のために使いたいと思っても、米国がそう簡単に認めることはあり得ない」と主張しています。要するに、アメリカは日本の国益のための核使用を許さないのです。その一方で、彼女はこうも言っています。「必要になれば米国の核の傘が機能し、日本が必要とした時に米国が助けてくれる信頼関係こそが、日米同盟の持つ抑止力である」。つまり、アメリカは自らの犠牲を厭わず、日本を助けるだろうということです。
核共有の場合は、アメリカは日本の国益のためにコストを払いたがらない一方で、核の傘の場合は、日本の国益のためにアメリカ人は膨大な命を捧げる覚悟を持つということでしょうか。なぜアメリカは拡大抑止になると、急に犠牲を厭わなくなるのか、私には不思議に思えます。そんなことは本当にあり得るのでしょうか。
必要とされる核政治研究
日本とアメリカの国益は同一ではありません。アメリカは日本を守ろうとすれば、かなりのリスクを負うと同時に、コストを払うことにもなります。この戦略的ジレンマを解消するために、前出のウォルト氏は拡大抑止の停止と日本の核武装を示唆しています。「アメリカが核の保障を止めることは、いくつかの国家に自分自身の核武装を促すかもしれないが、日本やドイツの核保有は、純粋にアメリカの視点からすれば、明らかに恐ろしい結果になるということではない」ということです。
私が見逃していなければ、この主張に対する日本の専門家などからの反論は見たことがありません(あるならば、ご教示ください)。他方、アメリカでは核武装がそれを阻止する他国からの「予防攻撃」を招きやすい条件(核拡散への悲観主義)を明らかにする、有力な研究が既に発表されています。この条件が東アジアで満たされている場合、ウォルト氏の予測は外れることになるかもしれません。
要するに、二極世界における中国の挑戦と台湾有事が日本人に突き付けているものは、より信頼性のある核抑止を含む安全保障戦略を構想することでしょう。その際、参考になるであろう核政治研究は、アメリカの政治学者を中心に、韓国の若手研究者も参入して、どんどん増えるとともに前進しています。にもかかわらず、わが国の戦略/安全保障研究では、それらの成果が十分に取り込まれていないようです(軍縮研究を除くと、日本の関連学会誌での「核政治」の特集は数件しかありません)。国家の安全保障にとって研究と政策が両輪であるとするならば、少なくとも片輪がガタガタしているのです。これをキチンと補修することが、激動の世界において、日本の独立や主権を守る堅実な安全保障政策を構築するための第一歩ではないでしょうか。
*近年の主要な核政治研究の代表的著作とその要約は、ロバート・ジャーヴィス、野口和彦、奥山真司、髙橋秀行、八木直人訳『核兵器が変えた軍事戦略と国際政治—核革命の理論と国家戦略—』芙蓉書房出版、2024年の「訳者あとがき」で、私が行っています。関心のある方は、ぜひ、ご一読ください。