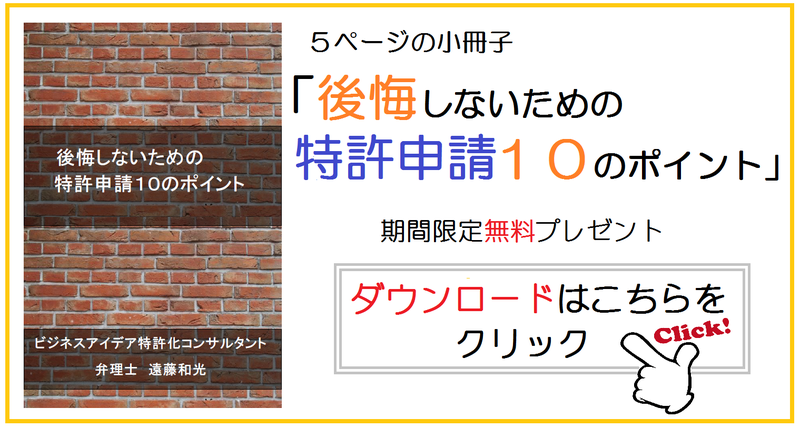出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、
かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が他人の登録商標の
指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである場合は、
商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。
商品については、生産部門、販売部門、原材料、品質等において
共通性を有する商品をグルーピングし、
役務については、提供手段、目的若しくは提供場所等において
共通性を有する役務をグルーピングし、
同じグループに属する商品群又は役務群には、
同じ「類似群コード」を付しています(類似商品・役務審査基準)。
審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、
原則としてお互いに類似するものと推定されます。
一方、区分は、商品や役務が属する業種のことで、
商標法施行規則で定められたものです。
商品は第1類から第34類、
役務は第35類から第45類に分類されています。
すなわち、商品又は役務が類似しているかどうかは、区分とは関係なく、
原則として類似群コードが同一か否かで判断されるということです。
例えば、区分が同じ場合、互いに類似するものもあれば、非類似のものもあります。
【同類間の類否】
第16類:書籍(26A01) 類似 新聞(26A01)
第16類:書籍(26A01) 非類似 鉛筆(25B01)
区分が異なる場合、互いに類似するものもあれば、非類似のものもあります。
【他類間の類否】
第14類:宝石箱(20A01) 類似 第20類:家具(20A01)
第14類:宝石箱(20A01) 非類似 第16類:鉛筆(25B01)
商標を使用する商品又は役務に付されている類似群コードが何かは、
特許情報プラットフォームで商標の中の「商品・役務名検索」を選び、
商品・役務名の欄に商品又は役務の名前を入力して「検索」をクリックすると、
商品・役務名ととともに類似群コードが表示されますので、それで分かります。
類似群コードは、商品及び役務の分類表の「類似商品・役務審査基準」で確認できます。
最新の「類似商品・役務審査基準」は以下の特許庁のサイトで公表されています。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2019版対応〕
※追伸
◆アイデアで起業を考えている方、
アイデアを形にしたい方、
発明力を付けたい方、
「ビジネス特許徹底ガイド」
をお勧めします。今なら無料です!
ダウンロードはこちら
↓↓↓↓

◆主婦やサラリーマンなどの個人発明家、
ベンチャー企業や中小企業の経営者に
「後悔しないための特許申請10のポイント」
をお勧めします。今なら無料です!
ダウンロードはこちら
↓↓↓↓
◆メッセージ付き友達申請をお待ちしております。
facebook個人ページ
https://www.facebook.com/kazumits