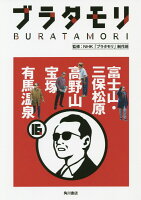お早うございます
私がこの場で時々ブラタモリについて取り上げていますのは、この番組で鍵になっている地形・地質と人間との関わりについて、着目する意義がなかなか広く認識されない世の中(日本だけの?)の現状にあって、地形・地質やそれと人間との関わりについての学問分野に育てられた身として、その学問の意義を少しでも広く知らしめることによって何か恩返しができないかとの想いを抱いているのが動機であります。ただ、これまで拙ブログにお付き合い頂き、ブラタモリ関係の記事をお読み下さっている方はお気付きかと思いますが、番組で関係するものが写ったものの深く扱っていない話を掘り下げたり、時にあれが欲しかったといったことをボヤいてもいます。
そうなる理由として、番組制作者側からの単純化圧力のことを昨日取り上げました。
この記事でも引用しましたが、そもそも地形・地質と人間との関わりに着目する意義がなかなか広く認識されないながらも実は日常と繋がりがあることを知る機会として番組が人気であることが指摘されていたり、
単純化された情報だけに振り回されることの危険性を指摘する記事もあります。
前者については、書籍刊行の案内(これについては最後にふれます)も兼ねている訳ですが、その著者であり、ブラタモリの高尾山の回
で案内人(小仏層群の解説)をされた山崎晴雄先生(首都大学東京(昨春に東京都立大学と改称)名誉教授)が、受験における地学の軽視や近年の都市部を中心とした開発によって地層を認識する機会が激減し、人々の好奇心において飢えている面があることを指摘しています。
一方、後者については、地形・地質の分野から離れた話題にもふれていますが、深い理解にために複雑な情報にふれる必要があるとの指摘は当然出てくるものです。その中で、地形・地質の分野では、一般向けの情報発信が整備されおらず、いきなり敷居の高い学術論文を読まねば最新の知見に辿り着けない現状を問題視しています。
分野が何であれ、学術論文のみの状態から一般向けに嚙み砕かれたものとして情報発信されるまでには時間がかかりますが、上記の両者を合わせると、世間の地球科学軽視の現状から情報の需要が不自然に少なくて絶対的に人員が揃うだけの予算が確保できず、一般向けの情報発信の仕組みの整備が追いつかない状態にあるのでしょう。
これは残念ながら今に始まったことではないですが、確かにまとまって噛み砕かれた情報発信は少ないかも知れません。ある地域のということでは、以下のように題材ごとに関連論文を要約して整理されたものはあります。
山崎先生が中心となって書かれた以下の書籍は、地方ごとに整理してブラタモリと専門書の間に位置付けられる文庫本ということでしょうか。