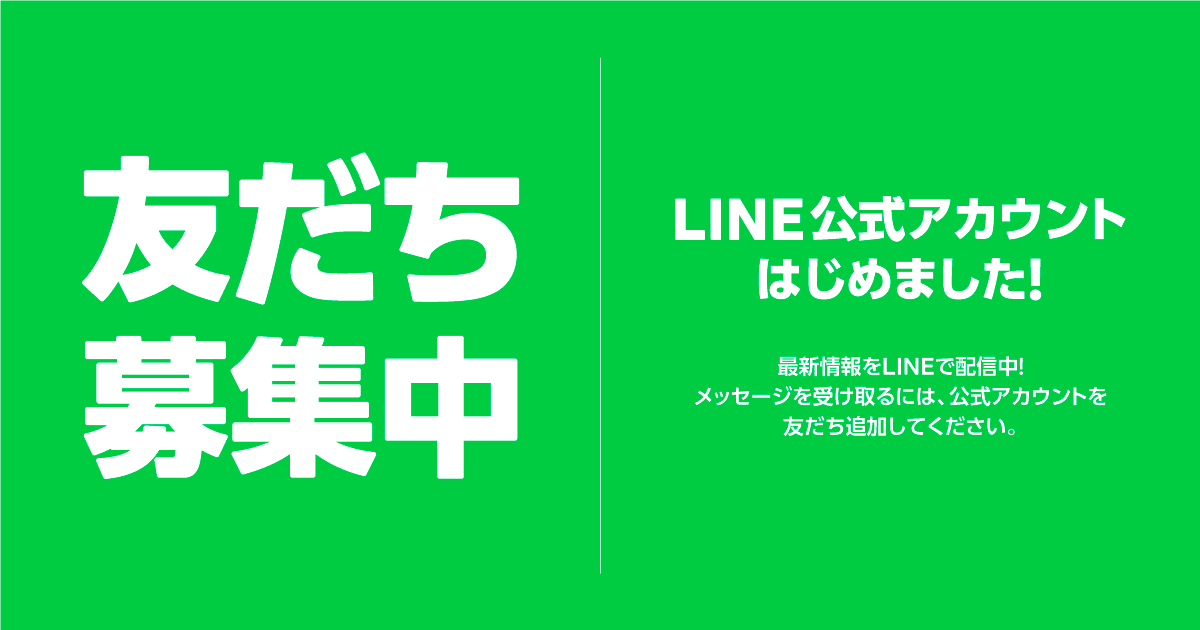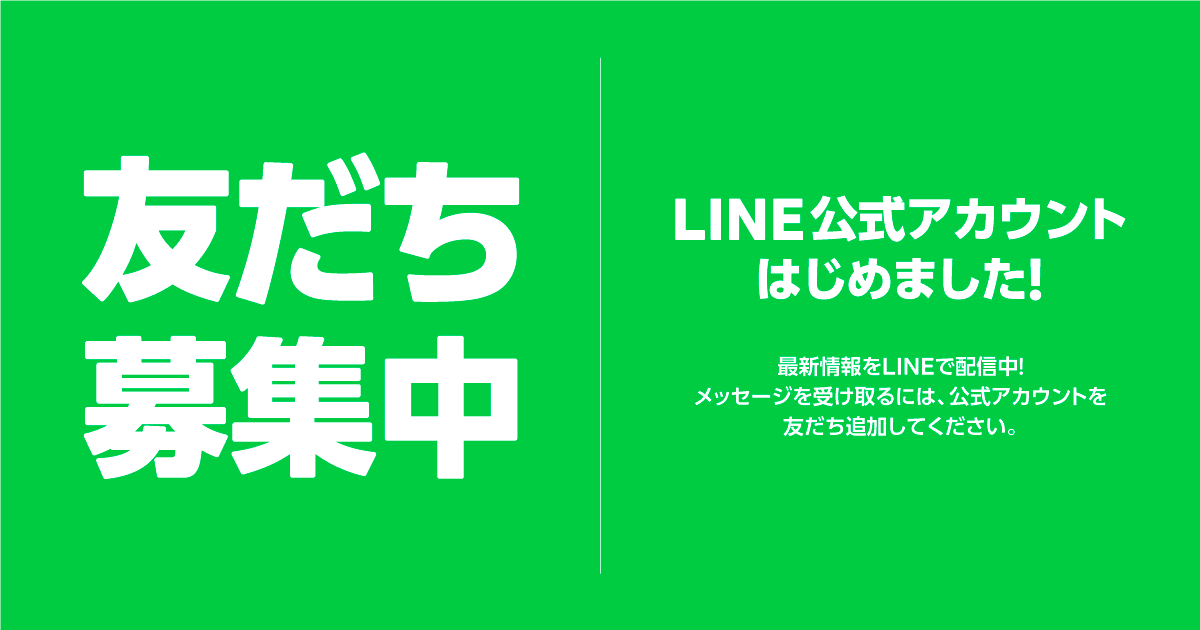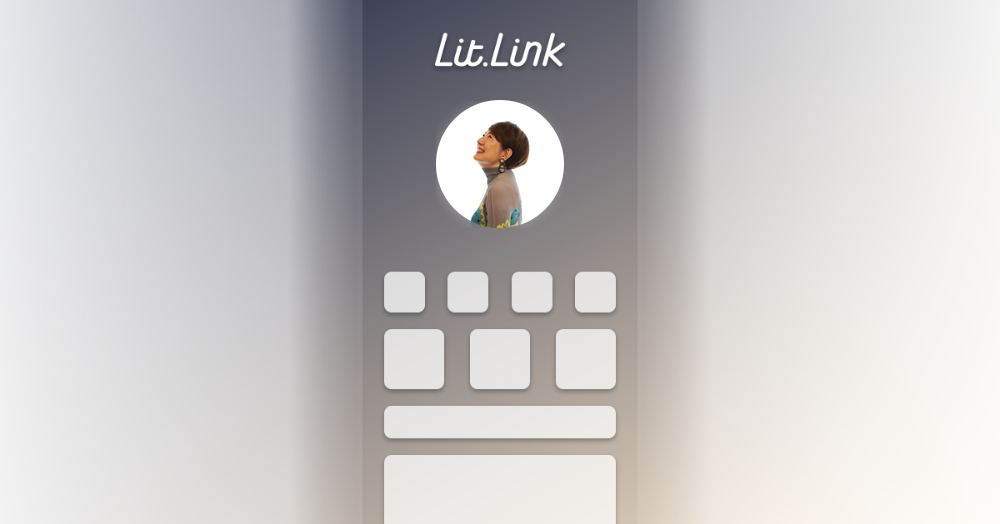【体験談】身体の声を聴くとは「感じる」ことだった。
キエコちゃんが言語化してくれるおかげで更に理解が深くなる。いつもありがとう❤️😊🙏
________________________
#Repost @kiecono with @use.repost
・・・
・
一年半前、2021年の夏。
子宮筋腫→過多月経→貧血
様子を見に
病院に通い始めた私は
「身体の声が聞きたい」
そう望んだ。
その頃の投稿を見ると
そのことがたくさん書いてある。
「身体のリーダーとコンタクト取りたい」
とか書いてある。
しかし実際は
「身体の声を聞く」
どうやって⁉️だった。
身体のリーダーが
日本語を話して
伝えてくれるわけじゃなかった😆
↑
どこかでサイキック(特殊能力)的に
「メッセージ」が
やってくるんじゃないかと
思いたかった私がいたのは否めない😆
────
特殊能力なんてなくても
身体の声は聴けるのだ。
今はわかる。
身体の声を聴くというのは
「感じる」ということなのだ✨
知識では
「感情=体感」ということは
ヴィパッサナー瞑想に
行った時から知っていた。
しかし
私にはその体感はなかったから
自分に活かせていなかった。
「知識」は必要だ。
しかし、自分のものとして
「知恵」にするには体験が必要だ。
そして
それを人に伝えることで
「叡智」になる。
────
笠村裕子さんの
「感情を感じるメソッド」の
助けを借りて
「感情」を「体感」として
感じることを意識し始めて
いろいろなものがつながってきた。
この地球で
肉体を持って生きる以上
「身体」からは逃れられない。
というか、身体が光明なのだ。
今まだまだ私は
発展途上段階だから
その視点でしか書けないけれど。
不感症出身の私だから
ネガティブ出身の私だから
出発点から書くことができる。
ーーーー ●感じるのがあんまりだから 閉ざして不感症になる
●辛いこともないけど
嬉しいこともない
●自分が感じていないということにさえ
気づいていない(麻痺)
●ネガティブの中にいるのが
あたりまえすぎて不快に気づかない
●辛いことしかない
(ネガティヴ思考:エゴキンマン)
●思考と感情の区別がつかない
●ホッとすることを覚える
●なんでも思考で
ポジティブに転換する技を覚える
(エセポジティブ=ネガティヴへの抵抗)
●どこかの分野がうまく行っていない
(お金・健康・人間関係)
●思考はポジティブでも
モヤモヤが残っていることに気づく
●思考と感情の区別がつく
感情=体感に気づく
●ネガティヴを感じるコトを許可する
●あるがままの感情を感じられる、
自分の感覚が信頼できるようになってくる。
(自信がついてくる) 抵抗がなくなる
望みが自然に出る →今、私ココ
●ポジティブとネガティヴが統合される
(抜けた、という状態)
ゼロポイント
エネルギーが満ちる
●エネルギー使いになる
トルネードを起こす
穏やかに生きる
お好み次第
ーーーー
私のわかる感覚と予測を
ざっと書いてみた。
人には段階があり
その段階の視点では見えない世界があり
次の段階に行ったときに
初めて前の段階の自分が見える。
その段階では通じない言葉があり
その段階に必要な言葉があり
その段階では必要なコトが
次の段階では邪魔になったりする。
段階と書くと 上がることが良いように思えるが
上がらない選択だってありだ。
というかそもそも最初から上の方にいて
コツコツ上がってくる必要のない人もいる。
そして
上がるにしてもなんにしても
今その瞬間
その段階を全うするしかない。
────
感じることに関しても。
感じることがわかって初めて
感じてなかったコトがわかったし
感じるようになってしまったら
感じなかった頃には戻れない。
だから
その時点その時点で
その人が体験している
「旬」でしか伝えられない
「感覚」「エネルギー」があるのだ❣️
人は慣れるし
忘れてしまうから。
だから。
今の私に伝えられるコトを
なるべく書き留めていこう😊
#感情を感じるメソッド
👇🏽【初めての方へ】"感情を感じる"とは?
🗣ご質問は公式LINEにて受付中!
公式LINEご登録はこちら
【公式LINEにてご質問受付中】
公式LINEにて直接ご質問いただくと、無料でワンポイントアドバイスをお送りします。
また、公式LINEでのみQ&Aのすべてを日々シェアしています📝
🗣お仕事のご依頼や企画のご相談はこちらから
事務局公式LINEはこちら
〰️〰️〰️
〰️Stay Negative〰️
ネガティブと共存しよう。
15年の実験を経てたどり着いた【KASAMURA METHOD: 感情を感じるメソッド】
●ネガティブな感情を感じきるだけで人生が動き出す。
●身体の感覚で感じきるとネガティブな感情は消えていく。
●自殺者ゼロ・鬱ゼロの世界へ
心の仕組みや、ネガティブな感情の取り扱い方について発信しています。
websiteはこちら