国立能楽堂です。

先週に引き続き、能楽囃子大倉流大鼓方、重要無形文化財総合指定保持者の大倉正之助さんからお誘いを受けて、本日も拝見いたしました。

本日は国立能楽堂という由緒ある能楽舞台で、西洋と東洋の融合という最先端の新しい文化の融合というべく、この能舞台でシェークスピアのマクベスが。。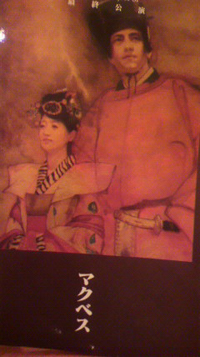
能とオペラの融合だなんて凄い挑戦。
その素晴らしさは後で書きます。
こちらは終演後楽屋にて。
さすが能楽堂は、このように火鉢があり、その傍らで大鼓の皮を焙じるためにこの部屋があります。
焙じる(ほうじる)とは使いなれない日本語で
「えっ?」と聞いてしまいましたが、出演前の大鼓を焙じて皮を温める、コンマ何度の温度の差で音が変わるそうです。
すごい・・・日本文化って凄いですよね。

今日の舞台は素晴らしい。先週のピアニストとタップの融合もすごかったですが今日は神がかりでした。さすがです。
 こちらは
こちらは
桃山時代から使っているそうです。
それって凄いですね。何代前のおじい様から引き継がれたのか?
時空を超えて。

マクベスはオペラ歌手の方と一流の狂言師の方がたが揃い共演饗宴競演です。
大鼓の鳴り響く打つ音とともに掛け声という本来の能楽の要素に加えて、空気を変えてしまう声と言うものを知りました。
低音でずっと効果音のようにある一定の音程で声を発していて、音楽という音楽はその大倉さんの声だけですが、静寂の中耳を澄ますと、確かに聴こえるのでした、私には。
驚愕の旋律が。
男性の低い大倉さんの発する声とは別にメロディーを背景で奏でるような旋律が。裏舞台のほうで小さな音で奏でているピアノかハープか、鉄琴のような音が毎回毎回その声のシーンとともにメロディーを奏でているのです。
カバン持ち出来ていたスタッフは聴こえないと言いました。
私には確かに聴こえるのです。
磁場を変え空気を変えなにかの違う領域になったその空間でその旋律が聴こえ続けているのです。でも何回もあるそのシーンで確実に声と重なり聴こえるこのタイミングは舞台裏の音響効果音だとしたらずいぶんうまく重なる奇跡。
だとすると??????
楽屋にて「大倉さんの声の後ろで小さなメロディーが聴こえたんですが舞台裏でメロディーを流しているのかと思いましたが、私には不思議に聴こえたんですが・・」とお尋ねしたら「ふふふ聴こえた?音楽担当は僕一人だよ。」
と。
すかさず楽屋にいたどなたかが、「一人何役もされている・・・背後霊が何人もいたんですね」と。
冗談とも本気ともつかないお答え。
でも本当にそうだと思いました。
いつか神主さんにも聞いたことがありますが、祝詞を読みながら同時進行で別の祝詞や速度の異なる祝詞を重ねていくつか読むことがあると。でも普通の人間の耳には聴こえてくるのはこの祝詞だけ・・・とか。
そう言う話を思い出し、聴こえないものが聴こえたのだと思いました。
超一流の方の作り出す空気感世界感は所作一つにしても本当に素晴らしく勉強になりました。
KAORUKOとの競演共演饗宴の日が楽しみです。!

先週に引き続き、能楽囃子大倉流大鼓方、重要無形文化財総合指定保持者の大倉正之助さんからお誘いを受けて、本日も拝見いたしました。

本日は国立能楽堂という由緒ある能楽舞台で、西洋と東洋の融合という最先端の新しい文化の融合というべく、この能舞台でシェークスピアのマクベスが。。
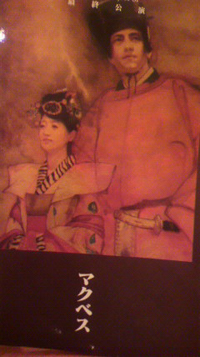
能とオペラの融合だなんて凄い挑戦。
その素晴らしさは後で書きます。
こちらは終演後楽屋にて。
さすが能楽堂は、このように火鉢があり、その傍らで大鼓の皮を焙じるためにこの部屋があります。
焙じる(ほうじる)とは使いなれない日本語で
「えっ?」と聞いてしまいましたが、出演前の大鼓を焙じて皮を温める、コンマ何度の温度の差で音が変わるそうです。
すごい・・・日本文化って凄いですよね。

今日の舞台は素晴らしい。先週のピアニストとタップの融合もすごかったですが今日は神がかりでした。さすがです。
 こちらは
こちらは桃山時代から使っているそうです。
それって凄いですね。何代前のおじい様から引き継がれたのか?
時空を超えて。

マクベスはオペラ歌手の方と一流の狂言師の方がたが揃い共演饗宴競演です。
大鼓の鳴り響く打つ音とともに掛け声という本来の能楽の要素に加えて、空気を変えてしまう声と言うものを知りました。
低音でずっと効果音のようにある一定の音程で声を発していて、音楽という音楽はその大倉さんの声だけですが、静寂の中耳を澄ますと、確かに聴こえるのでした、私には。
驚愕の旋律が。
男性の低い大倉さんの発する声とは別にメロディーを背景で奏でるような旋律が。裏舞台のほうで小さな音で奏でているピアノかハープか、鉄琴のような音が毎回毎回その声のシーンとともにメロディーを奏でているのです。
カバン持ち出来ていたスタッフは聴こえないと言いました。
私には確かに聴こえるのです。
磁場を変え空気を変えなにかの違う領域になったその空間でその旋律が聴こえ続けているのです。でも何回もあるそのシーンで確実に声と重なり聴こえるこのタイミングは舞台裏の音響効果音だとしたらずいぶんうまく重なる奇跡。
だとすると??????
楽屋にて「大倉さんの声の後ろで小さなメロディーが聴こえたんですが舞台裏でメロディーを流しているのかと思いましたが、私には不思議に聴こえたんですが・・」とお尋ねしたら「ふふふ聴こえた?音楽担当は僕一人だよ。」
と。
すかさず楽屋にいたどなたかが、「一人何役もされている・・・背後霊が何人もいたんですね」と。
冗談とも本気ともつかないお答え。
でも本当にそうだと思いました。
いつか神主さんにも聞いたことがありますが、祝詞を読みながら同時進行で別の祝詞や速度の異なる祝詞を重ねていくつか読むことがあると。でも普通の人間の耳には聴こえてくるのはこの祝詞だけ・・・とか。
そう言う話を思い出し、聴こえないものが聴こえたのだと思いました。
超一流の方の作り出す空気感世界感は所作一つにしても本当に素晴らしく勉強になりました。
KAORUKOとの競演共演饗宴の日が楽しみです。!