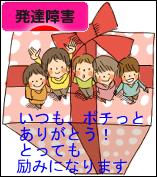にほんブログ村】 クリック励みになります!
今日は、「共感的感性・態度の乏しさ」について、我が家の長男と次男を例に、その育みについて記事にしてみたいと思います。というのも、この2人は基本気質において、まるで正反対の様なところがあり、それぞれの子が違った特性を持ちながら、周囲のどんな関わりのおかげで成長してきているのか・・・ということについては、考えさせられるところが多いのです。今日はそんな記事です。
【正反対な2人の性格】
さて、この二人がどう正反対かというと、
長男は、生まれ持っての人懐っこさがあり、
どこへ行っても、何となく可愛がられて、
周囲から助けてもらえるような徳な面を持っているのです。
発達障害の診断を受けてはいても、
彼の障害は、認知や思考と、状況判断の問題が主で、
対人的には恵まれているのかもしれません。
反して、次男はというと、
生まれついて長男とは様子が違っていて、
どこか気持ちの共有の部分に乏しさを持ち合わせていたのです。
なので、1歳半~2歳になった頃の彼は、感情表現も乏しい感じで、
どこか、淡々としたような気質を感じさせる子だったのです。
まだ、2歳なので、対人トラブルに出くわすわけではありませんが、
何となく、将来苦労するんじゃないかと、思わせる雰囲気なのです。
【周囲のかかわりで育まれていく共感性】
ただ、うちの子たちが恵まれているのは、
住んでいる場所が、この時代に珍しいほど、
コミュニティーが残っている地域であるところです。
そんな環境下で、次男のどこか淡々としたような気質は、
別段、取り立てて特別扱いされることもなく、
むしろ、周囲の方々からどんどん声掛けをしてもらい、
関わってくださることで、次男は心を傷つけられることもなく、
彼らしくのびのびと生きつつも、徐々に、共感性も育まれており、
コミュニケーションの能力も獲得して行っているように感じるのです。
また、この春から通っている保育園の対応にも、
随分と助けられていると感じています。
次男は、自分の思い込んだことへのこだわりの強いところがあり、
必ずしも、集団にすんなり馴染んでいるとはいえない様子です。
ただ、そんな彼も、先生方のあたたかい関わりにより、
少しずつ自分の世界を広げ、
同級生との関係も芽生え始めているように感じます。
先日、近所の夏祭りに行った時には、
左手はママと、右手は同年代の子と、
仲良く手を繋いで、歩く姿がありました。
(右手の子の更に右側には、その子のママが手を繋いでおり、
4人が手を繋いで歩く姿は、とても微笑ましかったんです。)
僕はこれまで、次男のそんな姿を見たことがなかったので、
なんかだ、嬉しくて仕方なかったんですよね。
次男はまだ未診断なので、
発達障害があるのかないのかは定かではないので、
彼の「共感性の乏しさ」は単なる性格なのか、障害特性なのかは、
今はまだわかっていません。
ただ、彼がそのいずれであったにせよ、
ご近所や保育園で、彼のちょっと気むずかし様なところが、
取り立てて問題視されずに、受け入れられていることが、
彼なりのゆっくりとしたペースであっても、
除々に進んでいる成長に、無関係だとは思えないのです。
【自らも、周囲に共感を求め始めた次男】
そして、最近の次男は、
以前は乏しかった反応も、
少しずつ出てくるようになってきているのです。
それは、自分が何かを出来た時に、
チラッと大人を見て、一緒に喜んで欲しいと要求する行動です。
以前は、自分が嬉しいことは、
自分の内心で喜んで完結するだけだったのが、
「ほら、できたでしょう!」と、大人をチラッと見るようになったのです。
もちろん、こちらが一緒に喜ぶと、満足そうに本人も手を叩いて喜びます。
彼のこんな姿を見ていると、
「共感性の乏しさ」を元来持っていたとしても、
周囲の関わりひとつで、ゆっくりとそれは育まれ、
行動として、本人に根付いて行くのだなぁ、
とつくづく思うのです。
【学校やご近所が、親子を追い込まないことの大切さ】
そして今日の記事の最後に、
僕はこうした共感性の育みに、学校やご近所が、
親子を追い込まないことの大切さを書きたいと思います。
長男にしても、元来の人懐っこさはあるとはいえ、
彼の「共感性の乏しさ」は、
自分ペースの強さとして出てしまうタイプです。
ですから、時に周囲の子に強く自己主張をしすぎたりして、
トラブルになることもあるのですが、
そんな元気すぎる彼の個性も、
周囲の方は、あたたかく受け止めてくださっています。
ご近所や保育園、学校がこの様に受け止めてくださるおかげで、
僕達夫婦は、そんな彼等の特性を、
何とかしようと躍起にならなくても済んでいると感じます。
僕は、支援団体で多くの方の悩みをお聞きしますが、
そんな中で、親御さんの躾が、
お子さんを二次障害に追い込んだケースに出くわすことがあります。
ただ、その親御さんのお話しをしっかり聞いていくと、
やはり世間の厳しい目や、周囲の雰囲気の中で、
子どもに対しておおらかになれなかった部分を、感じることがあります。
ともすれば、集団からはみ出してしまうような子、
また、元来、共感性の弱さを抱えている子が、
周囲から厳しい目で見られたなら、
その子は、ますます集団に入っていける自分を、
見つけられずに育つのではと感じます。
発達障害者が、集団の中に馴染めないところに、
本人や親の責任ばかりを責められないのではと、
僕が感じるのはそんなところです。
発達障害は、「共感性に弱さ」があっても、
そこは周囲のかかわり方で、育んでいける・・・と思うのは、
こんな長男・次男の成長振りを見るからなのです。
この社会が、いつのまにか特性のある子を受け入れなくなり、
集団からはじいても、誰も何も感じなくなっている部分の方にこそ、
僕は病巣が有るのではないかと感じる、今日この頃です。
【告知です!】
日頃の生活を離れ、ゆったりと過ごすお時間はいかがでしょうか
同じ境遇を持つもの同士、悩みを語ったり、
判らないことを聞いてみたり、
互いの経験を交換し合って、問題をひとつひとつほどいていく・・・・
そんなグループを目指して、開催しています。
【参加ご予約はこちらから】
http://cocopv.jpn.org/yoyaku.html
2011.08.12(金) 10:00~14:00
大阪市北区・中央区の貸し会議室にて開催!
少人数(10人)制 要予約
発達障害を共に考える会のご案内
当事者・家族・支援者のいずれもが参加出来て、
共に互いの思いを感じ、理解を深める為のワークです。
2011.9.19(月曜・祝) 13:30~17:45(開場13:15)
テーマ「発達障害の誤診問題と精神科薬との付き合い方」
定員30名(要予約)
40代の男性当事者さんをお迎えして開催します。
発達障害の確定診断を受けるまでに
17年を要したと言う苦悩と混沌の日々。
その後、セカンドオピニオンの医師の指導の下、
自分にあった精神科薬の種類・量を
模索する日々を過ごし、数年を掛けて、
その組み合わせを見つけるまでの日々。
そんな貴重なお話を語っていただきます。
フェルデンクライス・ボディーワーク教室のご案内
ゆったりとした時間の中で、
ココロとからだの調和を取り戻していく教室です。
無理な姿勢や激しい運動は一切ないので、
お気軽にご参加いただけます。
2011.8.2(火) 18:30~20:30
2011.8.23(火) 18:30~20:30
大阪市北区・中央区の貸し会議室にて開催!
少人数(6~8人)制 要予約