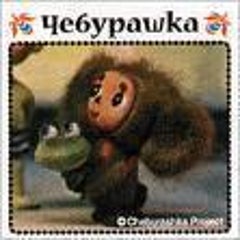映画「アメリカン・エピック エピソード2 『血と土』過酷な労働から生まれたブラック・ミュージック 」 2022(令和4)年11月18日公開 ★★☆☆☆
(字幕翻訳 星加久実、 字幕監修 ピーター・バラカン)

① ゴスペルの先駆者 エルダーJ・Eバーチ)

サウスカロライナ州チローの教会で聖歌隊をつくり
レコーディングもしていたエルダー(長老)JEバーチについて
ソニーの資料室の書庫にはレコーディングしたときの
タイプ打ちの詳細なリストが残っていますが、
彼のことを知る人はいません。
チローを訪れると、ひとりだけバーチ長老を知る高齢男性を発見。
「背が高くてハンサム、カリスマ性があって
いつも立派な身なりをしていた長老は
9歳の子どもだった私には憧れの存在だった。」
「70年も前の話だけどね」
パーチは1876年生まれ、
チローで店を開き食堂で成功した彼が1924年に教会を開き
聖歌隊をつくって、音楽を通じて信者を癒していました。
人種をわけられていた当時、ここに来るのは黒人だけ。
カリスマ牧師は全米黒人地位向上協会の中心人物となり
解放の表現としての音楽の地位を確立。
黒人たちは綿花を摘みながらアメイジンググレイスを歌い
歌うことで労働の重さから解放もされていました。
有名なジャストランぺッターのディジー・ガレスピーの生家は教会のすぐそばで
そこには記念碑がたっています。(1917~1993)

全米からチローに聖歌隊が集まり、
「バーチ長老にささげる」歌を歌い始めます。
巨体の彼らが拍手し、足で床を踏み鳴らすうちに、だんだんトランス状態に・・・
②炭鉱夫の兄弟 「ウィリアムソン・ブラザーズ」

ウエストバージニア州ローガンは炭鉱の地。
炭鉱夫たちはトロッコで地下に送られ、朝から晩までそこで採掘をします。
爆発や落盤の危険もある過酷な労働。
利益のほとんども会社に吸い上げられてしまうけれど
現実を抜け出すために楽しみでやっていた音楽。
ウィリアムソン兄弟も1927年セントルイスの録音に向かい
「ロンサム・ロード・ブルース」など6曲をレコーディング
(ブルース、とありますが、ジャンルは多分カントリー)
ひとり25ドルずつもらっておしまいでしたが、当時だったらそこそこの大金?
レコーディングは1回でおわり、家族もそのことを覚えておらず。
結局彼らは無名におわりましたが、フォークソング集には今もちゃんと名前が残っています。
③ デルタブルースの先駆者 チャーリー・パトン

ミシシッピ生まれの彼もまた1926年にレコードを録音していました。
映画「ランブル」でもとりあげられ、後世に残した影響は大きいのに
彼自身の存在は謎で、上の写真1枚しか残っていません。
(これも白黒写真にあとから色をつけたようです)
ローリングストーンズにカバーされたハウリン・ウルフとのつながりとか
いろいろエピソードが出てきますが、音楽詳しくないのでよくわかりませんでした。
(あらすじ ここまで)
しりすぼみのあらすじですみません。
実は、私の早とちりもあったんですが、
エピソード2で扱う年代が最初からつかめず・・・・
最初のバーチ長老のところで、黒人のおじいさんが登場し
「今から70年前、私は9歳の少年でした」
というので、この時点で
エピソード1は100年前だったから、
エピソード2は70年前の話と理解してしまったんですが、
バーチ長老は1876年生まれだから、計算があわない!
(結局、エピソード1も2も今から100年前の話でした)
そうすると考えられるのは
①昔のインタビューをひっぱりだしてきた
②インタビューは今のだけど、彼が会ったのは
かなり高齢になってからの長老
私は①だと思って、年齢計算しなおしながら見てたんですが
この映画の企画のひとつと思われる聖歌隊の集合のとき、彼の姿もあったから
②のほうが正解だったかも。
(9歳の子どもが70代のおじいさんに憧れるか?とも思いますが)
たしかに「背が高くて話がうまい」しかいってなかったですよね。
エピソード1では、
インタビューに答えるのがカーター家の人やラルフ・ピアの孫とか、
音楽業界に詳しそうな人たちの話は非常にわかりやすかったですが、
エピソード2では、無理くり探し出したような人たちだから
悪いけど、どれもエピソードが薄い!
特に、(上には書かなかったけど)
「子孫」として登場した若い男女は、普通の人権団体とかの人?
当時の人種差別と彼らが音楽に救われたことを「解説」するだけで
せめて何かネタを提供して欲しかったし、
そもそも、あなたたち、誰??
ウィリアムソン・ブラザーズでは、この中央でウクレレ?を弾いている
人物にそっくりの息子がインタビューに答えていて
「あのころの炭鉱の坑道は狭くてきつい仕事だった」
「父が音楽をやってたなんて知らなかった」
っていうんですが、
知らないのは不自然だし、1920年代に25ドルもらったら
家族は大騒ぎのはずですよね~
それにそもそもこのインタビューは何年前??
と思っていたら、ピーター・バラカンさんの記事のなかで
インタビューに答えているのは彼の「孫」とありました。
「うちのオヤジ(祖父)が音楽やってた」なんて、
(彼の息子である)うちの父からは何も聞いていない」ということかな?
わかりづらっ!
1920年代にレコード作った人の息子は存命なら今100歳くらい?
孫でも70歳くらいになってそうだけど、彼はもっとずっと若そうでした。
いずれにせよ、これに関しては(この映画のために新たに撮影したものではなく)
「古いインタビュー映像をひっぱりだしてきた」というのが正しそうです。
もう年齢計算で私はくたくたで、
最後のチャーリー・パトンで登場した
90代トリオの元気なお爺ちゃんたちの会話は
全然頭に入ってきませんでした。
フィクション映画では、わざと時系列をわかりづらくする手法もありますけど
ドキュメンタリーは、その辺、はっきりさせてください!
5W1Hですよ! (←古!)
今まで誰も手をつけなかった
アメリカの音楽の黎明期に光を当てる・・・
という素敵な企画。
パート3,4と、12月1日までの限定上映作が続きますが、
とりあえず私はここで降ります。