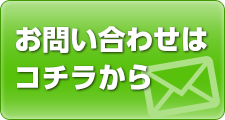「家のおばあちゃんの要介護度って
どうやって決められているの?」
こんなこと
考えたことってありませんか?
全開の記事で
※前回の記事
「介護認定調査」についてお伝えしましたが
今回は
認定調査も終わった
で、その後
肝心の「要介護度」が
どのように決められていくのか?
この、「要介護度」が決まっていくまでの
流れについてお伝えしていこうと思います。
下に記した図を
ちょっと眺めてみてください。
初めて見る方が殆どだと思いますので
簡単にご説明します。
この図は
「認定調査員」さんが来られ
聞き取り調査を終えてから、その後
どのような流れで
肝心の「要介護度」が決められていくのか?
その流れを記した図解になっているんです。
図だけ見ていても
「これ、なに?」だと思いますので
認定調査から、介護度が決まるまでの
簡単な流れをご説明します。
まず
「認定調査」が無事終わると
調査をおこなった「調査員さん」が
聞き取りの内容を「調査票」にまとめて
市区町村に提出します。
そして
「認定調査」と同時に
「医師の意見書」というものが同じくして
市区町村に提出されます。
この
「医師の意見書」とは何?
ですが
認定調査を受けられた
ご本人さんが
普段かかられている
かかりつけのお医者さんがいると思います。
その
「かかりつけのお医者さん」
言い方を変えると
「主治医の先生」となるわけですが
「認定調査員さん」は直接
ご本人と介護者さんから聞き取りを行い
聞き取りの内容を、調査票にまとめて提出する。
同時に
「主治医の先生」も
普段の診察の様子や
※(認定調査の前後1か月の様子)
物忘れの症状があるか?
主治医から見て
どんな介護サービスが必要と思われるか?
今後、どんなことに注意が必要か?
※(転倒して骨折する恐れはないか?
物忘れが進む可能性は無いか?)
など
主治医から見た
ご本人の状態を「意見書」という書面にして
市区町村に提出します。

この2つ
(医師の意見書と認定調査票)がそろった段階で
調査票の内容は、コンピューターに入力され
※コンピューターによる判定の仕組みはこれ!
その結果
「1次判定」として
「要介護度が(ここで決定ではありません)判定されます」
※1次判定の仕組み
そして
1次判定が決定されると
「1次判定の結果」
「医師の意見書」の内容などをもとに
「介護認定審査会」という
※介護認定審査会とは?
医療・介護・栄養士など
各分野の専門家から構成される会議で
審査、判定され
ここで、2次判定という形で
最終的に、「要介護度」が決定されます。
図解で説明しますと
この部分になります。
↓ ↓

ここまで
かなりザックリとした説明になってしまいましたが
これが
「要介護度」が決定するまでの流れです。
ここで
前回お伝えできなかった
補足をお伝えします。
認定調査の時に
「調査員さん」に
「介護の困り事などや
最近あった出来事を上手く伝えてください」と
お伝えしましたが
ここでもう1人
介護認定の結果に
大きく影響する人物
それは
かかりつけの先生(主治医)なんですね。
先ほどからお伝えしていますが
主治医は
「医師の意見書」というものを作成するわけです。
ここには
「物忘れの症状」や
「身体の状態」
「医師の目から見た、必要と思われる介護サービス」などが
記載されるんです。
ですから
日頃、
かかりつけの先生に診察を受けるときなどに
「介護で困っていること」や
「物忘れの症状」など
介護にかかわることも
良くお伝えしておいてくださいね。
最後までお付き合いくださり
こころから感謝いたします。
たつや
この記事の感想や
在宅介護の悩み
在宅介護で困っていること
ご質問などありましたら
こちらから