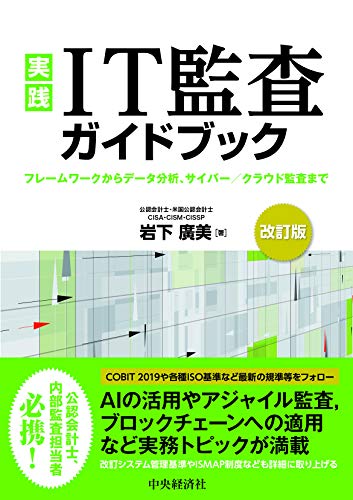中公新書の「読む技法」を読んでいる。
その本の中で出された課題が、芥川龍之介「蜜柑」と、梶井基次郎「檸檬」を比較して、共通する構造を抽出するということだった。
「蜜柑」は1919年発表の、芥川27歳の作品である。
青空文庫に掲載された作品は、10分程度で読み終わった掌編である。
僕は「蜜柑」のような、一場面を切り取ったような、情報が少なく感覚的なものに訴える短編を読むのがあまり得意ではない。
やっぱりぴんと来ないなと思いながら「読む技法」を読んでみる。
「読む技法」が提示する視点では「感情というのは、なんらかの外部からの刺激によって変化するものなので、きっかけとなる出来事と感情の変化」を辿ることが「小説を読む場合の基本中の基本」とある。
「蜜柑」は一貫して主人公の独白で語られる物語なのだが「きっかけとなる出来事と感情の変化」が、色彩で強く結びつけられているところに特色がある。
他者の視点を借りることで、こういう小説の読み方があることを知る。
芥川龍之介の他の作品にも「羅生門」の「赤」と「黒」の対比構造など、視覚に訴える色彩豊かな物語があるという。
芥川龍之介は僕の好きな作家であり、そういうものは無意識的に理解していたのだとは思う。
しかし、今回こうやって言語化され、納得したことを意識して、これからの読みを深めていきたい。
12月の読書の振り返り
読書時間:41時間
読書ページ:1690ページ
読書感想文:12時間(11記事)
去年の目標が、1日2時間の読書をする、ということでした。
本当はもっと読みたいから当面の目標と考えていました。
しかし振り返ってみると、去年は一度として1日2時間を越えた月はありませんでした。
今年はなんとしても1日平均2時間の読書時間の確保がしたい。
そのための初戦、勝負の1月と思ってます。
2時間越えられなかった理由は2つあります。
仕事の繁忙期は疲れてしまって本を手に取る気になれなかったこと。
繁忙期以外の閑散期に気分的に解放され、何も手につかなかったこと。
実は1月は、1年の中で一番の繁忙期。
だから、1月は難易度の高い月なのです。
一方で書く方は、感想を書かずに放置していた専門書も含め、去年読んだ本の感想はすべて書くことができました。
積み残しなく、今年は気分よくスタートできます。
感想を書くというゴールに向かって、しっかり読み込んでいきたいと思います。
前回記事で今年の抱負を書いたので、今回は今月の目標の再確認。
朝、通勤までの時間をダラダラしないで1時間、仕事が終わったあと心身ともに疲れ切った自分にムチ打って1時間。
日々のトレーニングの成果は目に見えないのと同じく、日々の読書の成果はなかなか実感がわきにくいです。
だけど、この1ページが自分の血肉を作ると信じて、執念を持って読みます。
2026年あけましておめでとうございます。
年の始まりなので、今年の抱負を語りたいと思います。
まず、今年も、良い本を読んで書く、このことに徹したいと思います。
去年の反省点として、読むということに対して、読まない時期、というのをなくしていきたいと思います。
仕事ですごく忙しい時は読書から離れがちなのは理解してますが、逆に、繁忙期を終わって時間が取れる時も読書を離れがち、という自分の弱さを認識しました。
1ページでも2ページでも、日々継続の読書の一年でありたいと思ってます。
今度は、書くということに対してです。
ブログの記事を書く、ということが、だんだんつらくなっているというのがありました。
ただ、これは、書くこと自体よりも、書きはじめまでが大変ということを認識しました。
読み終わってから、なるべく早い時間で書きはじめたいと思います。
最後に、読書の量についてです。
2025年は51冊の本を読了しました。
かつては、冊数を目標にすると、本のレベルを下げて、読みやすい本で読了数を稼ぐということをしてしまっていた時期がありました。
ただ、去年は、読むのが大変な専門書を月1冊ペースの12冊読めていて、本の内容も充実してきました。
2025年は平均の読書時間が80分程度でした。
今の当面の1日の読書時間目標が120分なので、この目標を1年間達成できれば、単純比率で、77冊になります。
僕は、専門家として、専門書を読みこなしたいというのがあるので、77冊のうち専門書は、月2冊ペースの24冊にしたいと思います。
去年は、今までの中で一番、高い意識を持って読書に取り組めたと思います。
それだけに、去年の数字は自分の限界であったと思います。ここを越える、というのは、大きな挑戦が必要だということも痛感しました。
年77冊は、月平均6.4冊になります。
このペースを崩さないように1年読み通したいと思います。
読書は、訓練であり、修行でありますが、人類の叡智に迫る、最高の娯楽でもあると思います。
つらくても続ける。でも、読書を楽しむことは忘れない。
こういうスタンスで1年頑張ります。
皆様よろしくお願いします。
4巻は1961年をメインに語られる。
山本伸一が会長になって1年。創価学会に一番勢いがあった時だと思う。
読んでいて元気になる言葉がたくさんあった。
強い人生の根底には強い信仰が必要だと感じた。これからの人生を自分の手で切り開きたいと思った。
自分に負けそうになる時、一歩を踏み出す勇気になった。
今回も、たくさんの付箋を貼った中から、残しておきたい言葉を記すことにする。
「人間は、たった一言の言葉で、悩むこともあれば、傷つくこともある。また安らぎも感じれば、勇気を奮い起こしもする。ゆえに、言葉が大事になる。言葉への気遣いは、人間としての配慮の深さにほかならない」(P23)
「青年にとって大事なことは、どういう立場、どういう境遇にあろうが、自らを卑下しないことです。
(中略)
もし、自分なんかだめなんだと思えば、その瞬間から、自分の可能性を、自ら摘み取ってしまうことになる。未来をどう開くかの鍵は、すべて、現在のわが一念にある」(P81)
「人の一生には限りがあります。そして、人生の価値は、その一生をなんのために使うかによって決定づけられていきます」(P110)
「結論を先に言えば、いかなる状態にあっても、必ず、すべてをやりきると決め、一歩も退かない決意をもつことです。人間は厳しい状況下に置かれると、ともすれば、具体的にどうするかという前に、もう駄目だと思い込み、諦めてしまう。つまり、戦わずして、心で敗北を宣言しているものなんです。実は、そこにこそ、すべての敗因がある」(P167ー168)
「およそ、青年を触発する何かを与え続けることほど、難しいことはない。
伸一は、それを可能にするには、自分が、自身の原点であり、規範である師の戸田を、永遠に見失わないことだと思った。源を離れて大河はないからだ。また、求道と挑戦の心を忘れることなく、自己教育に徹し、常に自分を磨き、高め、成長させていく以外にないと感じていた」(P243)
「人間の人生には、苦労はつきものです。
(中略)
しかし、そのなかに、意義を見いだし、生きがいをつくり、目標を定め、はつらつと挑戦し、苦労を楽しみながら、瞬間、瞬間を最高に有意義に、楽しみきって生きていける人が、人生の達人なのです。結局、幸福とは、外にあるのではない。私たちの心のなかにある。それを教えているのが仏法です」(P258)
――フレームワークからデータ分析、サイバー/クラウド監査まで
お仕事読書。
現代会計の前提にはITがある。
どんなに小さな会社でも、伝票入力から試算表の作成まですべて紙で行っている会社はまれであろう。
僕の仕事は会計監査である。
会計の前提となるITの理解なしに、その業務を全うすることはできない。
そのため、高度なIT業務は、社内のIT専門家と呼ばれる人を利用しているが、最終的な責任は、監査人が負うことになるため、彼らの業務の内容の把握や、必要な作業については協議の上、具体的に指示する必要がある。
IT自体に高度な専門性があることから、IT監査に対して心理的なハードルがあったのは否定しない。IT業務への理解を高めるために本書を手に取った。
500ページあるIT監査の専門書を読むことは意欲的な挑戦であり、勇気を奮い起こした。
本書の内容は専門性が高いので、ここに学びの成果物を具体的に示すことはしない。
読書ブログらしく、自分が本書から得たと感じたことを、3つ残しておきたいと思う。
まず、IT監査のフレームワークを理解することができた。
IT監査は僕が関係する会計監査のために限られない幅広い分野のものである。
そのIT監査がよって立つ考え方や、監査の基準、目的、どのように実施されるのかなど、基礎的な部分を一連の流れとして理解できたことは大きかった。
そして上述した通り、IT業務に対する心理的ハードルは高く、それゆえ、自分が業務の関わりの中で、消極的、受動的な部分があった。
しかし、本書を読み通して感じたのは、IT監査自体は、僕の会計監査の知識の延長でほとんど理解できることだ。
僕は、もっと主体的に積極的にIT専門家の業務に関わり、議論する必要があると思った。
IT専門家を使いこなすところまでが、監査人の責任分野である。
最後に少し視点を変えて、IT監査そのものではなく、ITを利用した監査について書く。
ITを利用した監査は、従来、CAAT(コンピュータ利用監査技法)と言われていたが、昨今はビッグデータの分析で使われるDA(Data Analytics)という言葉が使われ始めている。
今までも、ITを利用した監査というのは常に考えていた。
しかし、生成AIの利用も含めた可能性が本書では言及されている。その流れは思っているよりも早い。今までとは違う次元でITの利用を検討する必要があることを痛感した。
ここからは私見だが、ITを利用した監査が進化すれば、今まで監査人が行っている業務は大幅に削減されると思っている。その時間を、監査人の専門的知見を活かした検討、判断に費やすのだ。
それが、質の高い監査の実施につながると信じる。
本書を開いたときは、最後まで読み通せるか不安があった。
しかし読み終わってみればIT監査は、会計士が習得すべき最重要分野であった。
今まで目をそらしていたその事実を直視したのである。
本書を読んで感じたことを、一緒に仕事をするIT専門家と話す機会があり、大いに触発を受けた。
業務に直結する学びとして、今後もこの分野の知見を深く広くしていきたい。