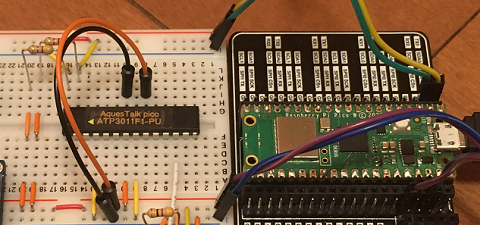■ねらい:
現場端末で音声メッセージを出す
PCの場合は下記記事のようにpythonで音声合成読上げ可能。
マイコンを使って同様のことを実現したい。
■参考出典
出典1:MicroPython:音声合成LSI(ATP3011F4-PU)を使う
(だいちゃまめさんブログ)
↑I2C接続、micropythonです。
接続図はありませんが、写真からだいたい読めます。
ラズパイPICOの3.3VでATP3011を駆動していらっしゃいます。
出典2:Arduinoで音声出力をはじめよう!「入門編」
↑2012年の記事ですが、回路図があります。
■使用端末
・開発環境:Thonny、Windows11pro
・マイコン:ラズパイPICO-W(今回、無線を使いませんのでPICOでも同じ)
・音声合成IC:ATP3011F1(ゆっくり女性版)
秋月電子から購入しました。IC周りの抵抗、キャパシタも同様です。
出典1はATP3011F4ですが、音声が異なるだけですので、
主プログラム、ライブラリともデッドコピーさせていただきました。
■配線とプログラム
・配線は出典2、プログラムは出典1からそのまま使わせていただきました。
■結果
・アクティブスピーカーから「ゆっくり」の声が出てきました。
驚くほど簡単です。いろいろと現場で使えそうです。
■注意点
・最初は「ERROR5:EIO」が出て困りました。
最初は回路図どおりではなく、I2CのSDA、SCLにプルアップを設けずに
配線し、アドレスが「0X2E」であることまで確認できていました。
「ERROR5:EIO」でぐぐると、、、
出典3:
↑これには、とにかくちゃんとプルアップしろ、と。
ということで、回路図どおりに4.7kΩでSDA、SCLともプルアップすると、、、
動きました!!!
これまで多数のI2Cデバイスを使ってきましたが、
すべてプルアップなしで動作
していたのですが、やはり先達のいうとおりに
きっちり回路を固めること
が肝要といまさらながら勉強になりました。
■250222追記
↑音声合成回路基板のほうをブレッドボードからはんだ付けにしました。
ピンジャック端子もはんだ付けして物理的に安定できました。

↑ATP3011の音声の種類を変えるにはICごと交換になるので、
脱着可能なようにロングピンソケット差しにしました。
ICのピン長さがやや短く、ギリギリで接続している感があります。
仕様確定できるならばピンソケットを適正にする、
あるいは直付けがよいと思います。
また、基板間をジャンパーワイヤで接続していますが、
接続不安定要因として残ってしまっていますので、
基板コネクタにするほうがより確実に動作するでしょう。
以上