
EL34三極接続パラ・シングル(設計編)
EL34(6CA7)のパラ・シングル・モノラルです。初段は6SL7のSRPPです。
各部電圧は、バイアスを-27Vに調整したときの、実測値(一時間通電の後)を入れてあります。
水魚堂さんのBSchを使って入力しています。
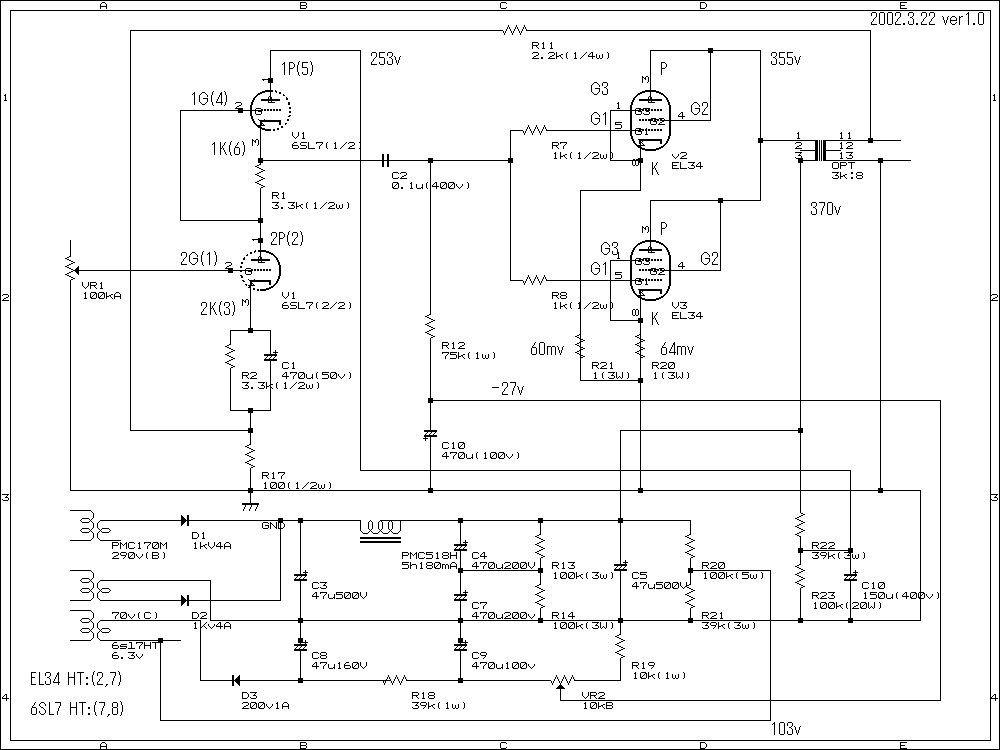
設計のポイントは以下のとおり
- JJスロバキヤのEL34が安く買えた
- 出力トランス(ULタップなし)の都合がついた
- 初段はSRPPかパラレルか?
- 自己バイアスか固定バイアスか?

1本税込み1500円で、気持ち高めだけれども6本まとめて買えたので、これでプッシュプルをと思ったけれど、パラ・シングルにして様子を見ることにしました。
ちなみに、EL34は、日本では6CA7という呼び名で、松下やNECも作っていてポピュラーな球です。よって、うまく作った他人のアンプを聴いたりすると、「自分もこういうの作りたい」と思うことが、これまでによくありました。

TU-873から外したトランスを使うことにしました。
これでおわかりの方が多かったとおもいますが、TU-873は300Bなので、出力トランスに、UL接続のためのタップがありません。必然的に「三極接続」になりました。
ここが勘所で、最初最小段数狙い(早口言葉?)で6SL7のパラレルを考えましたが、TU-898の初段の設計(回路図)が、実にみごとだったので、SRPPを一度作ってみることにしました。これだと300B vs EL34の比較ができ、作る意味があります。
ただし、SRPPだと6SL7のプレート・ヒータ電圧差の定格を守るためのバイアス(カサ上げ)をどこかから取ってくるのが課題になります。
あれこれ考えているうちに、2本(パラ)だとカソード抵抗が巨大になるので、固定バイアスにしました。
ところが、OPTの定格がわからないので(測るか?)Ipの計測用に結局1Ωをカソ-ドに入れました。これで球の選別に使えるかも??
これに限らず、計算しても抵抗のあるなしで適当なのを入れるので、最後実測調整になるとおもいます。
まずは部品集めですが、一番お金の無い2月なので、電源トランス以外はあり合せで済ませました。
まったくの衝動で作った50BM8シングルの経験から、以下のとおりとしました。
- <構成品>片チャンネル一台分
- 電源トランスは、ひとつ大きめの新品
- ダイオード整流
- ボンネットつきケース
- 耐圧1.5倍の容量の大きすぎ電解コンデンサー
| 部品名 | 大体の値段 | 入手先 |
| JJスロバキヤ EL34 | 1500円×2 | やふおく |
| JANフィリップス 6SL7 | 1000円 | やふおく |
| ケース | 5000円 | 小坂井 |
| 電源トランス | 8000円 | ノグチ |
| チョークトランス | 3000円 | ノグチ |
| 出力トランス | 不明 | TU-873から取り外し |
| 電解コンデンサー | 新規が2千円くらい | ジャンク、小坂井 |
| 抵抗、ボリューム他 | 全部で4千円くらい | クニ産業と小坂井 |
| GTソケット | 240円×3 | やふおく |
| ネジ類 | 千円くらい | 東急ハンズ |
| 新規合計 | 約2万8千円 | ただしモノラル |
電源は、音を聞いてからカットアンドトライがあるので、50BM8シングルの時のように、臭い思いをしないように、ノグチのPMC-170Mに、ちゃんとPMC-518のチョークコイルを、秋葉原ノグチから新品で買うことにしました。
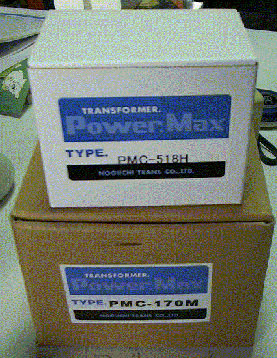
C電源が取れる70Vの端子が出ているので、これを使いました。
出力管より整流管のほうが高いというのは困り者なので、またまたダイオード整流です。
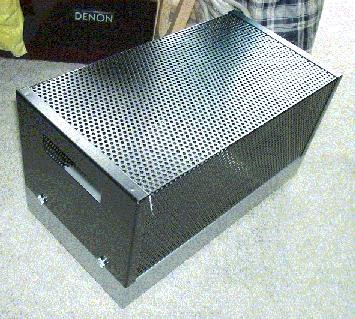
5千円のリードのケースが大須小坂井にあったので、これにしました。このおかげで、以下の危ない電解コンデンサーをまた使うことができます。
耐圧200V、470μFという中途半端なスプラグの電解コンデンサーが、残り6個あるので、これを消化することにしました。一応ブリーズバルブらしきものがあるし、ケースにボンネットがあるので、酷いことにはならないとおもいます。
実は、50BM8シングルで4個使っていて、280VDCにも耐えている(熱くならない)ので、MIL表記かなんかで、1.5倍までいけるのではないかとおもいます。
問題は整流の一発目には大きすぎて、突入電流でヒューズが飛ぶくらいだとおもいます。
上記回路図の使い方により、耐電圧の低い電解コンデンサーが利用できるのですが、実はこれ、前回の50BM8シングルを見た毛唐から、メールで今回のような「本来の使い方」というのを教えてもらいました。何KVの回路でも使えるように、わかりやすい200Vなのだそうで、一発で高い電圧に耐える高価なコンデンサーを尊ぶのは日本人くらいだそうです。日本はまだまだ抵抗が高いから??
Now JJ0WAJ
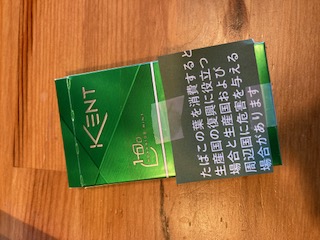 平成14年3月15日 de jp3exe ex je2egz
平成14年3月15日 de jp3exe ex je2egz

